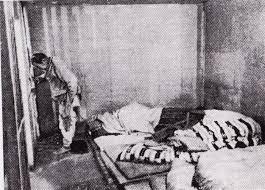
1: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)17:35:39 ID:62z
3週間に1回のペースで通院してるよ
3ヶ月で50万ちょっとだよ
働いてたけど入院を機に退職したから今は無職だよ
仕事のストレスでOD(大量服薬)して失神して
目が覚めたら親が入院許可出しててそのまま入院になったよ
随分と大変だったじゃないか
何歳?
25歳だよ
失神してたから覚えてないけど救急車来て肺炎にもかかってて大変だったらしいよ
今、病気を隠して普通に就活するか
障害者雇用で就活するか迷ってる最中だよ
入院中はネット禁止だったから今その反動でネットしまくりなんだ
いただきます
窓に鉄格子ついてて職員から「絶対に光るものを患者に見せないでください」って注意された
リアルSIRENとかバイオハザードみたいで怖かった
20: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)17:56:29 ID:62z
「今もまだ死にたいですか?」って医者に聞かれた
自殺しようとしたと思われたらしい
「はい、少し」って答えてしまった
それが運命の分かれ道だった
正直すぎワロタ
まずベッドに両手と腰をベルトで固定されて身動き取れない状態にされた
ちんちんに管を刺しておしっこも自動で採取されるようにされた
飯は3日くらい食べてない
その間ずっと点滴で栄養補給してた
不思議とお腹はすかなかった
「あなたは入院することになりました。親の許可も得ました」って言われた
そこから地獄の部屋へ移動させられた
その部屋は外から鍵がかかる扉が二重に設置してあって
密室で窓は頑丈で叩いても割れない
部屋の中はベッドとむき出しの便器だけ
真っ白な部屋
「天井に監視カメラとマイクが付いてるから何か用があれば天井に向かって叫んでくださいね」
看護師にそう言われた
何もやる事がない
時間が流れるのが遅く感じた
一番きつかったのは食事
入院時に肺炎になってた俺はノドを心配されて液体状の食べ物しか食べさせてもらえなかった
米をすりつぶしてペースト状にしたもの
おかずも同じ
吐きそうになるほど不味かった
固形物が食べたいですって懇願してもなかなか食べさせてもらえなかった
あと精神病棟の先生ってキチガイ相手にしてるから傍若無人で
まともに近い奴が入るとその扱いにかなり参るらしいな
10年位前にどっかのサイトで見たわ
監視カメラがあるから性処理はできなかった
まあ監視カメラでむき出しの便器で用を足してる場面は見られてるから
ひらきなおって性処理しても良かったんだけどね
「なんでこんな事に」っていう後悔と
「映画みたいな部屋だな」「俺牢屋に入ってるみたい」っていう非現実感が心の中にあった
3日後くらいに医者から
「そろそろ昼間はロビーで過ごしましょうか」って言われた
昼になると看護師が迎えに来てロビーと呼ばれる場所に連れて行かれる
そこには俺以外の患者が15人くらいくつろいでた
テレビも本棚もあった
そこで気づいた
「みんなも俺と同じように隔離されて、同じ時間にこうしてロビーに来てるんだ」
残念ながら男だらけの病棟に入れられたから女はいなかった
そこには他の人もいて、テレビもある
これこそ人間社会だ
密室で過ごしてた俺にはそう思えた
医者に懇願した
「もっとロビーで過ごす時間を増やしてください」
医者はOKしてくれた
「じゃあ入院部屋を変えましょうか」
部屋は俺が入ってる密室以外に、通常の入院部屋があるらしい
そっちはロビーと繋がってて自由にロビーへ出入りできるらしい
俺は刑務所の罪人から一般人へ昇格した気分になれた
そこはきれいなベッドのある個室で例の牢屋に比べれば文化的な部屋だった
後に知ったが例の牢屋は保護室と呼ばれてて
自殺志願の気持ちの強い者や病棟で暴れた者、医者のいうことを聞かない者が入れられる特別な部屋だったらしい
どおりで、例の牢屋にいた頃は夜中によく向かいの部屋から叫び声やドアをガンガン殴る音が聞こえてた
とにもかくにも俺はようやく一般の病人として扱われるようになった
ロビーに行けばテレビも見れるしシャワーもある
ほっとした
他の患者との交流だ
色んな患者がいた
運良く仲良く慣れた同年代の人もいた
そいつから色々な情報を教えてもらえた
どうやらこの病棟は統合失調症の人間が主に集まる病棟であるとの事
俺は二重の意味で恐怖した
他の患者が怖く見えた事と、もうひとつは俺が医者から統合失調症と思われているという事実だ
その人も統合失調症だった
その人は親から強引に入院させられたらしい
ある日普通に過ごしてたら家に突然救急車が来て
「乗ってください」と言われ戸惑っていたら
「病院で軽く注射するだけですから」と言われ
乗って病院に来ると本当に注射されて、そこで意識が混濁してふらふらになって
気づいたら例の牢屋に入れられてたらしい
40: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)18:27:37 ID:62z
常に廊下を行ったり来たり歩いてる人
ずっと見てると10メートルくらいのルートをひたすら行ったり来たりしてて壊れたゲームのキャラみたいだった
朝っぱらから上半身はだかでハイキックの練習をしている人
若い兄ちゃんだったがキックするたびにおなかがぷよぷよ揺れてたから俺には面白く見えた
常にひとりごとを言ってる人、看護師にひたすら「聖書をください」と懇願してる人
色々いたけど自分だけはまともだと自負してた
もっと冷静なイメージだったんだけど
普通の人が7割
おかしい人が3割
って感じだったな
基本的にみんな平和に過ごしてた
俺が一番感じ入った事は3ヶ月の入院の中で患者同士の喧嘩を一度も見なかった事
そこに向かって椅子を投げつけるおっさんもいた
でもそんな攻撃的なおっさんも患者同士でのもめごとはしなかった
「俺は世の中の陰謀に気づいてしまった。」って言ってる2ちゃんでもよく見る陰謀史観者もいた
たまに冷蔵庫がブーンってなるじゃん
あの現象を
「世の中の真実に気づいてしまった俺への警告音なんだ」
って真剣に話してる人もいた
その人は薬をちゃんと飲まずに看護師のいうことを聞かなかったから
例の牢屋(保護室)に異動させられてた
45: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)18:32:33 ID:4cJ
俺は親が許可した保護入院だったけど
別の患者は強制入院の人もいた
刑務所から来た人も何人かいた
統合失調症の2級
信じてもらえないかもしれないけど症状は特に無い
不眠くらい
自殺したいという思いは消えた?
普通の人と同じ気持で生きてる
死にたいとは思ってない
49: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)18:36:29 ID:dr5
それは貴重な経験だw
16歳で入れられたよー
貴重なの?
松沢って都立松沢病院でしょ?あそこは日本の精神医療の要所で精神病院の中でも別格の存在だよ
そだよーい
サカキバラもいたらしいね 何病棟かわかんないけど
私62棟だった
サカキバラ居たのか!それは知らなかった
煙草とか厳しいらしいな
院内は完全禁煙だった
公衆電話があるんだけど医者が許可した相手にしか電話しちゃいけない
俺の場合は母親だけには電話してもいいって言われた
病棟の外に出れないから保護室ほどじゃないにしても
「病棟」という名の大きな牢屋と例えてもいいと思った
事実、罪人になった気分だったし仲良くなった人と一緒に脱走計画を話したりもしてた
もちろん病棟は外から鍵がかかってるから脱走計画なんてただの暇つぶしのもしも話なんだけどな
新聞やテレビで時事的な情報には触れれるのか?
うん。新聞とテレビはあった
テレビで街角の様子とか流れるたびに悔しかった
「俺は隔離されてるから街には出れないんだ」っていう無力感というか疎外感がひどかった
流石に留置所並みの環境は確保されてるんだな
患者は6時起床21時就寝だから深夜番組はみんな録画して見てた
なぜか一番人気があったのはカウントダウンTV(音楽番組)だった
ロビーにはテレビが二つ用意されてたからチャンネル争いは特になかった
ただ、ネット禁止、ゲーム機禁止だったから俺は退屈で仕方なかった
看護師に相談したら院内の売店でラジオを買ってきてくれた
(この時点で俺は自分で売店に行くのも禁止されてるくらい隔離されてたから)
それ以来、ラジオが俺の生きがいになった
71: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)18:50:54 ID:D0V
本心から死にたいと思ってる人はどう克服するんだろ
俺のは本当に魔が差した気の迷いだった
「いつになれば退院できるのか」って事だった
それが予定不明なうちはもう一生出れないんじゃないかってくらい心配だった
俺の病棟で一番長く入院してる子が1年半だった
その子は半年近く薬を飲むフリしてポケットに隠して捨てて
それがついに看護師にバレて長期入院してる子だった
そのエピソード聞いた時おれは何故か笑ってしまった
隔離されて閉じ込められてる被害者意識のせいで病院が敵に見えて
その病院に背いて薬を飲むフリしてた子をちょっと「やるじゃん」って思ってしまったからだと思う
病棟には意外と外国人もいた
覚えてる限りで、白人2人黒人2人はいた
オーストラリア人の若い子はナルト(アニメ)のファンで
録画してあるナルトのオープニング曲を何度もリピートして見てた
拳で握手してヨーヨーとか言ってくるやつが周りに沢山いそうだな
残念ながら外国人はみんな浮いてた。友達もいない感じだった…
76: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)18:56:29 ID:MtO
睡眠薬の大量服薬をしたら自殺志願者だと思われて保護入院になった
何の脈絡もなくバンプ・オブ・チキンの歌を大声で歌い始める人だった
すごい音痴で、でもいつも堂々と突然歌い出すから面白かった
1回につき10秒くらいで歌い終わるからウザさも感じなかった
ちなみに入院中に母親に電話した時
「やばいよ、俺いつ退院できるか分からないよ」って言うと親も
「とりあえず入院に了承しちゃったのよ。そんなに長くなるとは思わなかった」って謝られた
まあ謝るべきは俺の方なんだけどな
治るもん?
一般的には治らない病気って言われてるらしいね
症状を抑える事はできるから一生薬と付き合っていく事になるのかな
鍵のかかった病棟のドアに患者が並んで、鍵をあけてもらって一斉に外にでる
外と言っても院内の敷地内だけなんだが
俺は2ヶ月ぶりくらいに外の風を浴びて嬉しかった
ちょっと心が洗われた気がした
医者にも「もう死のうとする意思はない。病状も軽い」って伝わってた
これで問題なく散歩を繰り返せば、徐々にレベルが上がって外出時間が1時間、2時間と増えていくらしい
俺は問題を起こさないで散歩を楽しむ決意をした
俺が過去にも大量服薬してる、ある意味前科があったのと
今回は両親が入院に承諾しちゃったからね
精神科?内科的な症状あるなら心療内科なのかな?
俺は精神科だよ
なんでそういう病名になってる?
それは俺も聞きたいくらいだ
もともと通院してて、入院する半年くらい前に医者に「幻聴が聞こえるかも」って一言だけ漏らしたことはある
それが記録されてて統合失調症にされたのかもしれない
その辺は医者に相談してみる
個人的には不眠さえ治ればいいんだけどなぁ…
87: 名無しさん@おーぷん 2015/07/09(木)19:17:39 ID:62z
医者に文句も言わないし散歩の時間もちゃんと守るし特に問題も起こさないし
医者から一時外出許可をもらえた
1泊だけ自宅に戻れる権利だ
すごく嬉しかった
病院から出て1人で家に帰るんだけど、外を歩くのがひさびさだったせいで
なんか違和感とかあった
電車に乗るのもちょっと怖かった
でも無事に自宅に外泊できた
外泊報告シートっていう紙に、外泊中の過ごし方とか、どう感じたかとかを書く欄があるんだけど
そこにも思い切り優等生的な書き方をした
外泊したらそのまま脱走して戻ってこなくなる患者もいるらしい
でも俺はちゃんと病院に戻った
「もう大丈夫そうだから退院しちゃいましょうか?」
って言われた
そんなあっさり退院できるのかと驚いた
優等生ぶってて良かったと思った
その言葉から5日後に本当に退院できた
以上
最後疲れたから急展開でごめん
とりあえず今は自宅で普通に生活できてて嬉しい
もう二度と入院したくない
ほんとの暇は地獄だからね
退屈は本当にきつかったよ
おかげでラジオで劇団ひとりのファンになってしまった
- 引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1436430939/




 ライブドアニュース
ライブドアニュース 
 森永健一
森永健一 
