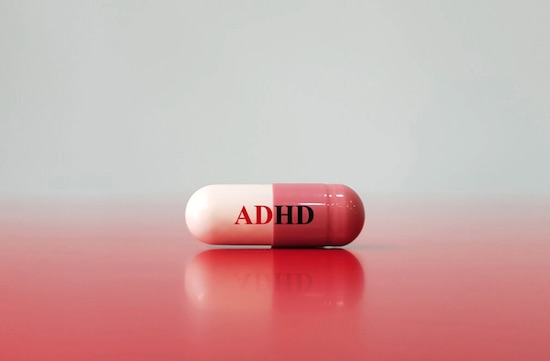[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
酔生夢人のブログ
気の赴くままにつれづれと。
[PR]
人間は野生動物以下の知能か? www
つまり、動物に有益なことは人間にも有益であり、動物は自分で自分の治療ができるだけ人間よりはるかに賢い種もいる。
ちなみに、私は化学の知識が無いので言うのだが、下の記事の中の「ナトリウム」は自然界では単体のナトリウムとして存在するだろうか。通常は塩化ナトリウム(食塩)の形で存在するのではないか。つまり、食塩は人間にとっても必須栄養素だというのが私の主張である。世界的な減塩風潮は人間の健康を損なう(病気にしてカネ儲けの対象にする)意図ではないか。
(以下引用)
飼い猫や犬は草を噛む。草には催吐作用(逆流や嘔吐を引き起こす)と瀉下作用(腸の奥に住む虫を駆除する)があるからだ。動物はさまざまな機能に対して、さまざまな種類の草を選ぶ。
草食動物であるゾウは多くのナトリウムを必要とするが、植物にはあまり含まれていない。ナトリウムがないと病気になる。そのため、ゾウはナトリウムを別の場所で確保する必要がある。ケニアには、エルゴン山と呼ばれる活火山の中腹に洞窟がいくつもある。これらの洞窟は、何世代にもわたってゾウが作り上げたものだ。この200万年間、ゾウは大量の岩を食べてきた。洞窟の中では、ゾウは膝をついて這い、ナトリウムを豊富に含む岩の塊を掘り出さなければならない。また、カルシウムやマグネシウムを含むミネラル豊富な水も飲んでいる。
ルワンダのゴリラは、乾季にヴィソーク山の斜面から掘り出した岩を食べる。ゴリラが掘り出して食べる岩には、鉄分、アルミニウム、粘土が多く含まれている。ゴリラはこの岩を薬として食べる。粘土には下痢を止める働きがあり(乾季のゴリラの食事は植物性であるため、下痢や危険な水分喪失を引き起こす)、アルミニウムには制酸作用がある。乾季になると、ゴリラは草木を見つけるために高い場所に行かなければならず、高山病を発症する可能性があるため、鉄分は有用である。
「沖の少女」あるいは「海の上の少女」
さすがにこの年になると、今から音楽の勉強をしたり科学の勉強をしたりするつもりもないが、小説を読むにしても、未読の傑作は無数にあるわけである。まあ、「食わず嫌い」を少し治すだけでも、脳内世界は広がるのである。
などと書いたのは前置きで、ここのところ、これまで知らなかった傑作に出会うことが多いので、こうした前置きを書いたわけだ。で、その傑作の多くは、市民図書館の「児童文学」コーナーでたまたま借りた本の中にあったものだ。大人向けだと、実は「純文学」が少なくて、ここ30年くらいの間に出たベストセラー大衆小説の類が多いのである。その中には傑作もあるが、残念ながら、やはり「俗臭」が付きまとうのが大半だ。ところが、児童文学には実は「純文学」の傑作が含まれていたりするのである。
先ほど、寝床の中で読んでいた「ホラー短編集3 最初の舞踏会」の中のひとつで、シュペルヴィエルという作家の「沖の少女」という作品が、その大傑作なのだが、私はこの作家の作品を読むのも初めてで、名前は聞いたこともある気がするが、まったく関心は無かった。この短編集の中に無かったら、一生この作家の作品を読むことは無かっただろう。つまり、この大傑作を一生知らずに終わるという残念なことになったわけだ。
この短編集の編者でもある平岡敦という人の翻訳だが、他の作品の翻訳も見事で、作品選択も素晴らしい。モーリス・ルブランの「怪事件」というわずか8ページで見事な不可能犯罪を描いたものなど、ルブラン嫌い(というよりルパンのキャラが嫌い)な私としては、この短編集に入ってなかったら絶対に読まなかったはずだ。まったく、どこからどう考えても絶対に不可能な犯罪で、私は最後の2ページ手前で読むのをやめ、頭を悩ませて考えたのだが、どうしても解答が見いだせずあきらめたのだが、残り2ページでのその見事な「解決」に驚き、感嘆したものである。しかも、その解答は、あらゆる推理小説、あるいはすべての不可能犯罪の解答として見事に成立するのである。まあ、騙されたと思って読んでみるといい。
話を戻して「沖の少女」だが、その作品の扉絵を佐竹美保という挿絵画家が描いていて、この人は児童文学の挿絵をたくさん描いているひとだが、この作品ではキリコの「憂愁と神秘の通り」をアレンジした絵を描いている。まさに、そのイメージを連想させる短編小説なのである。つまり、詩と神秘の世界だ。死という神秘の世界と言ってもいい。まさに、死とはこういう世界かもしれない、あるいは、死がこういう世界だとしたら、それは地獄よりも恐怖の世界かもしれない、というもので、しかし、話自体は淡々と、むしろ詩情の中で進んでいくのである。それはまさにキリコのあの絵を見ている時の気持ちなのだ。まあ、言葉を換えれば、萩原朔太郎や中原中也や立原道造や宮沢賢治の詩情を思わせる世界の中に「地下鉄のザジ」を投げ込んだ印象だろうか。ただ、ザジが実は地下鉄に一度も乗れないように、この少女も生の世界から切り離されているのである。
「向精神薬(麻薬)」によって未来の子供はほとんどが精神病かロボットかゾンビになる
(以下引用)
ここから、ジェフリー・A・タッカーさんの寄稿文です。最初、コロナワクチンの話がしばらく続くのですが、本題の部分から翻訳しています。
なぜ子どもたちに薬を投与するのか?
Why Are They Drugging the Students?
Jeffrey A. Tucker 2024/05/24
…この問題の根底にたどり着いたと思ったら、新たな情報が流れてくる。最近、私は、強制的な医療化に反対して子どもの権利を擁護する団体、エイブルチャイルドを設立したシーラ・マシューズ・ガロ氏の講演に参加する機会に恵まれた。
なぜこのようなことが必要だったのだろうか? 実は、今日の公立学校に通うほとんどの子どもが、毎日この脅威に直面しているからだ。
彼らの多くが ADHD、つまり注意欠陥・多動性障害であると特定される可能性がある。
結局、ADHD を構成する化学的に証明されたものは何もないことがわかっている。これは、チェックリストの質問票で特定された行動に基づいて適用される診断にすぎない。
チェックリストは、そわそわすること、物忘れ、退屈、課題を終わらせること、さまざまな形の行動、フラストレーションの表現などに関するものだ。
言い換えれば、ここにあるのは、特に男の子が何ヶ月も何年も机の前にじっと座り、権威ある人物から割り当てられた課題を完了するように言われたときに予想されるごく普通のすべての兆候が書かれてあるリストだといっていい。
この種の診断では、多くの子供たち、特に例外的な子供たちや、かつては「才能豊かで才能がある」と考えられていた子供たちを巻き込むことになっているだろう。
実は、今日では完全に正常な行動特性を病理化しようとする巨大な産業が存在する。これは特に男の子に非常に大きな打撃を与える。なぜなら、一般的に男の子は女の子よりもゆっくりと成長し、女の子に比べて環境適応に対する行動抵抗の傾向があるからだ。
この驚くべき現実について詳しくは、目を見張るような著作『 ADHD 詐欺:精神医学はいかにして正常な子供を「患者」にするのか』をお読みいただきたいと思う。
このような診断の目的は何なのだろうか? 皆さんもご想像のとおり、この想定される問題には薬がある。
薬の名前はさまざまだ。リタリン (メチルフェニデート)、アデロール (アンフェタミン)、デクスメチルフェニデート、リスデキサンフェタミン、クロニジン、アトモキセチンなどだ。
これらの薬のどれも、生物学的異常に対する化学的治療薬として証明されていない。これらはすべて行動調整薬、つまり向精神薬、つまり子供用の麻薬だ。
何百万人もの子供たちが、10代の 13%に及ぶほど、精神科の薬を服用している。大学生になると、その割合はさらに高くなる。成人の約 3人に 1人が精神科の薬を服用している。状況は悪化している。
そして、これらは「学校から」始まるのだ。
これらすべてを聞いて私は驚いた。しかし、ある意味では、これは私たちが知っている他のすべてのことと一致している。ここには、公立学校などの政府機関、規制当局、そして奇跡を約束して人々に薬を投与しながら、実際には人生を台無しにする医療当局と緊密な協力関係にある業界がある。
もしあなたが 7歳の頃から薬物中毒になり、向精神薬に頼って生活していたら、あなたの学生時代はどれほど違っていたか考えてみてほしい。
今日の何百万人もの子供たちは同じことに苦情を言えない。
これはまったく驚くべきことであり、大々的に暴露されるのを待っているスキャンダルだと私は思う。
ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏が最近公の場で指摘しているように、関連する要因の中には、学校での銃乱射事件とこれらの薬物の広範な流通との奇妙な関係がある。(※ コメント / 銃乱射事件を起こした子供たちの多くが何らかの向精神薬を服用しているという調査があります。こちらの過去記事でもふれています)
多くの事件はすでに知られているが、本当の問題は銃ではなく薬物製品にあることを一般の人々がますます理解しつつあるにもかかわらず、その他の事件の医療記録は公表されていない。
しかし、活動家たちは、より深く(向精神薬と銃乱射の関係を)調べるよりも銃を取り上げることに完全に集中している。
私はアデロール中毒の若者たちと個人的に接したことがある。いろいろな意味で、大学生にとって、アデロールは奇跡の薬のようだ。
大学では、時間の使い方に関する規律は優先順位が低くなる。その代わりに、長いレポートを締め切りまでに提出すること、テストで書いた翌日には忘れてしまうような膨大な資料を暗記すること、そして、ときどき集中力を維持することが求められる。
多くの学生にとって、この薬はまさに医師が処方したものだ。集中力を高めて徹夜した後、1、2日ゾンビのような気分になるが、誰もそれに気づかない。
私は、身体的なものだけでなく心理的なものも含め、依存症に陥る人を何人も知っている。薬物のない生活は、それに比べれば退屈に思えるが、誰がそんなことを望むだろうか。
こうした学生は、これを職業生活に持ち込み、同じパターンを試みている。彼らは一日中働き、夜通し起きて、驚くべき成果を上げることができるが、それはあなたが求めていたものとは少し違う。
あなたが解決策を求めても、それは実現しない。実際、彼らは何日も連絡を取らず、仕事の記憶を失って再び現れる。このパターンが繰り返される。
本当の問題は薬物にあることが徐々にわかってきた。私は、少なくとも安定した労働パターンを持ち、時間をかけて構築できるスキルを多少は覚えている、そこそこの生産性のある従業員を雇うほうがよいと結論づけている。
問題は、誰かを雇うときに「どんな薬物を飲んでいますか」といった質問をするのはあまり適切ではないということだ。結局は推測することになり、時には間違った推測をすることになる。
長年の経験から、これらの薬物は職業生活にとって大惨事だということをお伝えしたい。誰も決して服用すべきではない。
いずれにせよ、これは私の熟慮した意見であり、私は大学生に頻繁にこれらの薬物を服用しないよう警告している。大学生に当てはまることは、高校生や小学生には何千倍にも当てはまる。これらの薬物がキャンディーのように学校の子供たちに配られるというのは、まったくのスキャンダル以外のなにものでもないのだ。
親にはこのことに抵抗する権利と義務がある。
最近知ったことだが、ADHD の診断には科学的な根拠がまったくなかったこと、(コロナの際の)社会的距離の背後に科学的な根拠がまったくなかったことを知ると、なおさら驚きだ。
すべては、さまざまな命令から利益を得ている国家とそれに隣接する民間セクターのプレーヤーに奉仕するためにでっち上げられたもので、どういうわけか、結局は国民に薬を投与することになる。このすべてに私は驚愕している。
もっと広い視野で考えてみよう。私たちは公立学校を創設し、子供たちに通学を強制し、報酬の得られる仕事から彼らを締め出し、男女を一緒にし、すべての生徒が同じペースで学ぶかのように画一的なカリキュラムを押し付け、教師から裁量を奪い、巨大な官僚機構を学校に押し付けた。
子供たちが環境にうまく適応できないと、私たちは彼らを精神病者と呼び、政府とつながりのある製薬会社が利益を得られるような方法で彼らに薬を与える。
このレベルの残酷さが、まさにシステムに組み込まれている。文明社会がこれを容認できるとは驚きだ。そして、起こっているスキャンダルの全容がわかれば、減量薬、他のワクチン、奇跡の治療法、そして対症療法の仕組みそのものについて、他の疑問を抱かざるを得なくなる。
この穴はとても深い。
「スキュデリお嬢様」
前から何度か言及しているバルザックの傑作「暗黒事件」を中編にしたようなものだ。(時代的にはこちらが先。)
題名が魅力がない、と何度か書いたと思うが、森鴎外はこの作品を翻訳していて、私は未読だが、その題名が「玉を抱いて罪あり」という、作品内容を見事に表したものだ。(鴎外の翻訳小説はほとんどが彼が惚れこんだものだけに、実に面白いのである。)
ちなみに、この「マドモワゼル」は73歳の貴族老嬢で、小説家・詩人でもある。その言語能力が彼女を活躍させる(被告人弁護の)基盤にもなるわけだ。「スキュデリお嬢様の大冒険」とでもしたらいいが、それだと中期の高野文子あたりが描いたようなコメディに思われそうである。
ほとんど解決不可能な犯罪事件をいかにして解決するか、という話であるが、そこはルイ14世時代のフランスの話であるから、それ相応の解決策もある。しかし、基本的に話のすべてが合理的で、大審院判事でもあったホフマンの経験が裁判話のリアルさ(無実の被告を救う困難さ)の土台になっているようだ。裁判が被告側にいかに不利かは「暗黒事件」でも書かれている。あらゆる証拠や証言は警察と検察が握っているのである。(クリスティの「検察側の証人」は、それを引っくり返したところに面白さがあるわけだ。)
推理小説ではよく「不可能犯罪」がネタになるが、これは最後に解明されるから実は「不可能犯罪」ではない。で、「マドモワゼル・スキュデリ」は「不可能弁護」の話である。この弁護が成功するかどうかは読んでのお楽しみだ。
ホフマンは幻想文学など書かずに、こうした「リアリズム小説」をたくさん書いていたほうが大文豪になったのではないか。音楽家としても大成はしなかったのだから、「間違った方向に努力する」名人だった気がするww
若さは気から
要は、肉体だけ若返っても意味はない、という話だ。で、精神の若さというのは80歳になっても100歳になっても変わらない人は変わらない(いや、進歩し、若返りすらする)のであり、それは「幼稚さ」だと批判もできるが、これを「若さ」だと肯定的に見たらどうか。
何だか、一時期流行ったアメリカの誰かの「青春の詩」のような臭い話にしか聞こえないかもしれないが。いや、言っていることはまったく同じなのだが、これから書くことは、たぶんもう少しマシな話だ。
で、小児や幼児には不可能な娯楽が、「精神世界の娯楽」である。これはある程度以上の知識や知能が必要になるので、ふつうは年齢と共に知能は向上し、知識は増えるから「大人の娯楽」になる。小児や幼児の場合は非常に限定されるわけだ。
つまり、老化(単なる年齢的意味での老化)というのは「精神的娯楽」に関しては、むしろ喜ぶべきことなのである。
数日前に私はバルザックの「暗黒事件」を読み終えたが、これは「いい加減な読書」が普通である私としては珍しく、フランスの「大革命時代」を勉強しながら、ふたつの翻訳を同時に読んでいった、いわば「学問研究」の真似事に近い読み方だったのだが、それでも内容の8割か9割くらいしか理解できていないと思う。つまり、歴史的知識が無さすぎるのである。たとえば「七月革命」、つまりナポレオン失脚後の王政復古に続く二度目の革命などの詳細はまったく知らない。
まあ、学校教育の中では歴史とは年号と人名・地名の暗記だけだったのだから、当然である。
しかし、今朝の寝起きに枕元の本棚から適当に抜き出したホフマンの「黄金の壺」その他の入った文庫本(ほとんど未読。収録作品の題名が魅力が無い)の解説を読んで、ホフマンがナポレオン戦争時代の人間であり、その影響で悲惨な人生を送った人間であることを知って、(解説の中の作品説明からも)がぜん興味が出たのだが、つまり、手近にあっても、所持している当人がその価値を知らない宝物がたくさんあり、それが私の言う「精神世界」の宝物なのである。
で、その宝物も、私の場合はその前に「暗黒事件」を読むということが無かったら、まったく興味も惹かなかったわけだ。
誰の人生でも、RPG(ロールプレイングゲーム)的な「冒険」はあり、それが精神世界での冒険である。だが、その冒険は本(先人たちの作った精神世界)という「広大な未知の大陸」に踏み出す者だけに与えられる冒険だ。
さて、一度読んだ本でも、その大半は未熟な精神での読書で、その価値の半分どころか100分の1しか味わっていないのは確実だから、そのうち、若いころ(十代のころ)に読んだ「戦争と平和」の再読でもしよう。未読の「名作古典」を含め、まさに「老後の楽しみ」は無限にあるのである。これは本だけでなく音楽も絵画も諸学問も「その本当の価値を知らないまま生きて来た」意味では同じことだ。つまり世界は宝に溢れている。
(以下引用)文中の「じいさんばあさん」はたぶん「ぢいさんばあさん」が正しい表記。
私なら、同じ若返りでも、山本周五郎の「大久保彦左衛門実記」をアニメ化する。これは、太平の世になって、戦国時代の質実剛健の気風を失った武士たちの姿を怒り、我が身の老いへの鬱屈とで世をすねていた大久保彦左衛門が、甥の若侍に騙されて、自分が昔書いた(実はその若侍の創作)実録を読んで興奮し、徳川家の御意見番として活躍するうちに、武芸の鍛練によって心身共に若返るというユーモア小説である。つまり、若さは心構えから、という話で、現代の高齢社会にウケルのではないか。
ちなみに、若返りはしないが、武士の老年新婚夫婦(事情があって、新婚早々別離していたが、何十年ぶりに再会して熱々の新婚生活を送っている)を描いた森鴎外の「じいさんばあさん」はしみじみと感動するというか、ニヤニヤしたくなる、ほほえましい名短編なので一読をお勧めする。芝居にもなっているようだ。
分子レベルの論拠の現代生物学(医学)学説はすべて嘘?
長い記事で画像や動画も多いので末尾だけ載せる。この引用部分の画像も一部省略するかもしれない。
(以下引用)

 ウイルスの存在を主張する側がこの実験をやって結果(ウイルスは出て来ない)を認めることは決してないでしょう。
ウイルスの存在を主張する側がこの実験をやって結果(ウイルスは出て来ない)を認めることは決してないでしょう。それをやればワクチン、ウイルス関係の薬、治療方など、これまでのすべてが終わってしまうからです。
それを食い止めるため、今後も「検体にはウイルスが少なすぎる」「ウイルスは生きた細胞内でしか増殖できない」などと言いわけをし、検体から直接ウイルスを発見するのではなくそれをの腎臓細胞に混ぜ、そこから「ウイルスを発見」し続けるのでしょう。
ウイルスの存在証明というと難しい話のような気がしますが、たったこれだけのことができないということです。
わかってみればこんなわかりやすい詐欺に何十年も騙されていたのです。


そのようなサンプルを純粋化しても言い訳は同じで、そこにはウイルスは見つからないらしい。 つまり「患者の身体は何兆ものウイルス粒子であふれかえっているはずなのに、その表面からも内部からも何も見つからない」ということなのだ。
昔のウイルス学者たちは、電子顕微鏡写真とより効率的な純粋化技術の出現により、病人の中からあらゆる種類のウイルスを見つけ出すことができると確信していた。
しかし20世紀の中頃になってもこの試みは実を結ばず、ウイルスは発見されなかったので、このプロセスは断念せざるを得なくなった。
純粋化されていない試料を撮った電子顕微鏡写真、そこからコンピューターで作成された仮説のゲノム、そのシミュレーションに合わせて作られたPCRテストなどは忘れること。これらのどの作業も実際のウイルスの存在がなくても可能だからだ。

その2
[補足:電子顕微鏡の問題点]
対象物に対する電子線の放射は有機物を瞬時に炭素化、つまり燃焼して炭素に変えてしまいます。したがって当初、人に雷を落として写真を撮るようなものと揶揄されました。
(写真)国立感染症研究所で分離に成功した新型コロナウイルスだそうです 1/5⬇️
 燃焼により発生する揮発性ガスは解像度を著しく低下させるため、標本を脱水して粉末状にしておく必要があります。
燃焼により発生する揮発性ガスは解像度を著しく低下させるため、標本を脱水して粉末状にしておく必要があります。細胞は劇的に縮み、変形し、破壊され原型を留めません。
さらに、電子線は放射線ですから活性酸素種が大量発生し、細胞内小器官は破壊され、細胞は死滅します。
2/5⬇️

したがって、生きた細胞をそのまま電子顕微鏡で観察することは原理的に不可能です。
そこで、凍結固定や化学固定が発案されましたが結果に大差はありませんでした。
※細胞に二重膜があるように錯覚するのも化学固定の際に使用されるオスミウム酸染色によるアーチファクト(人工操作物)です。 3/5⬇️

このようにウィルスと誤認する数多の人工物が出来上がり、「電子顕微鏡は自分の探したいものが何でも見つかるオモチャ」と揶揄されるのです。
4/5⬇️

いわんや、ウィルスが存在すると仮定されている細胞培養液の懸濁液(ホモジネート)には多数のバクテリア、細胞の破片、エクソソームが混在しますから、一体何を見ているのか本当のところは分らないというのが実情です。
(写真)SARS-CoV-2感染の瞬間だそうです

「通俗道徳批判」という、上級国民らしいデコイ(偽物の的)
言っていることはやや偽善的というか、大学教師らしい自己防衛的言語修飾もあると感じるが、かなりまともである。しかし、発言の中で出口なおの言葉をしばしば引用するなど、怪し気でもある。大本教信者か? だが、「言っていること」よりも、「言っていないこと」のほうがより問題だろう。
一番の問題は、日本の問題を経済問題でなく「精神の問題」にしてしまっている、いや、意図的にそうしていることで、そうなると「日本人が精神的に変われば幸福な社会になる」という、宗教的煽動にしかならないのである。
日本人の劣化が精神ではなく貧しさからくるものであることは自明だろう。つまり、「貧すれば鈍する」である。他人に構っている余裕など庶民には無いのだ。自分やその周辺が生きるだけで精一杯なのである。「勤労精神」が悪いと言うなら、遊んで暮らせる社会をどのようにすれば実現可能なのか提言しないと、「きれいごと」だけ言って終わりという、いかにも「先生様」のお言葉でしかない。さすがに、上級国民の生産工場である慶応の先生だ。
下記記事でこの先生は長々と御託を言っているが、要は「国民が悪い」「通俗道徳が悪い」としか言っていないのである。
(以下引用)
慶応義塾大学経済学部 教授 井手英策氏
東日本大震災という歴史的な惨事が起き、世界から日本の「絆」が賞賛されたことは記憶に新しい。しかし、「がんばろう」という大合唱とは裏腹に、私たちの社会はズタズタに分断されている。所得階層間、雇用形態間、性別間、政府間、地域間、世代間などの対立が激化し、私たちはバラバラな存在に追いやられている。日本社会は先進国と呼ぶのが痛々しいほどくたびれ、多くの日本人は、生きづらさ、閉塞感、未来を見通せない不安に怯えている。では、この社会を覆い尽くしている漠然とした重苦しさはどこから来るのか。私たちはこの「分断社会」を終わらせることができるのか。
新進気鋭の財政社会学者、慶応義塾大学経済学部の井手英策教授に聞いた。井手先生は近著『分断社会を終わらせる』(共著 筑摩選書)において、この命題に迫りその解決策を提唱している。
理不尽な社会を次世代に残してはいけない
――今、先生の近著『分断社会を終わらせる』(共著 筑摩選書)や『分断社会・日本』(共編 岩波ブックレット)が巷で大変な話題になっています。まず、その執筆動機からお聞かせ頂けますか。
井手英策氏(以下、井手) 執筆動機は大きく分けて2つあります。1つ目の動機は「理不尽な社会を終わらせたい」と思ったからです。最近よく巷では、格差が大きくなったという声が聞かれ、新聞、雑誌などでもこの話題が取り上げられることが増えました。国民の多くが漠然と格差は広がったと感じています。しかし、現在の日本と高度経済成長時代の日本を比べれば、明らかに格差は小さくなっています。それでは、なぜ日本社会は先進国と呼ぶのが痛々しいほどくたびれ、多くの日本人は生きづらさ、閉塞感、未来を見通せない不安に怯えているのでしょうか。
 <
<慶応義塾大学経済学部 井手 英策 教授
第8回の「世界青年意識調査」(内閣府2009)によれば、他国と比べて日本の若年層(18歳~24歳)は社会で成功する要因として、「運やチャンス」をあげる人が多くなっています。
運やチャンスで人生が決まるということは、親の所得や環境によって自分の未来が決まるということです。
私は生まれた時に「運が悪かった」という理由だけで、その人の人生が決まる社会というのは、それは格差が大きいとか小さいとかの問題ではなく、とてもおかしいと思います。裕福な家に生まれる、貧しい家に生まれる、男性に生まれる、女性に生まれる、障害を持たずに生まれる、障害を持って生まれるなどはすべて運です。私は、運が悪かっただけで、その人の人生が決まってしまう社会を「理不尽な社会」と呼んでいます。現在の日本社会は、まさにそれにあたります。
運が悪かった人たちも、運が良かった人たちと一緒に生存競争の輪に加わり、その後の努力や頑張り次第で自分たちの生き方を決めていくことができる社会をつくる必要があります。運が悪かった人たちに感情的に「かわいそう」と手を差しのべるのは学者の仕事ではありません。私は財政社会学の立場から、このような理不尽な社会をなくす方策を研究、そして提言していきたいと考えています。
子どもたちの未来に不安を感じた
2つ目の動機は「子どもたちの未来に不安を感じた」からです。私には今3人の子ども(8歳、4歳、0歳)がいます。3人の子どもたちの生きていく世の中を考えたときに、言いようのない不安に襲われることがあります。それは、もし私が運悪く今日帰宅の途中で車に跳ねられ、死亡とか、障害を負うようになった場合、「妻や3人の子どもたちは安心してこの日本社会で生きていくことができるのだろうか」と考えるわけです。
今日、本の生活保障システムでは、義務教育や子どもの医療費を除き、現役世代にとってのサービスはゼロに等しい状態にあります。残された3人のどもたちが、塾はもちろん高等教育さえ受けられなくなる状況がパッと浮かびます。そのような社会を私たちは次世代の子どもたちに残してはいけない、何とかしなければいけないと考えています。
勤労が義務である国は先進国で日本と韓国だけ
――そもそも、今回のテーマである「分断社会」は、どのように形成されてきたのですか。
井手 日本国憲法第27条に「勤労の権利と義務」というのがあります。勤労とは単に働くことではなく勤勉に(industrious)働くことを意味しています。おそらく「労働や就労が義務」の国はあったとしても「勤労が義務」である国は、先進国では日本と韓国だけだと思います。このことは、なぜ日本社会は引き裂かれ、分断されているかを考えるときにとても重要になってきます。
1.すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。(日本国憲法第27条「勤労の権利と義務」)
この「勤労」という言葉は、戦時中の国家総動員体制のもと、定着した概念であるにもかかわらず、日本人の心性に訴えかける言葉として左派にも好んで用いられています。
1945年11月に出された日本社会党の綱領には、「わが党は勤労階層の結合体」であると最初に記され、翌月に出された日本共産党の運動綱領でも、勤労大衆、勤労者、勤労同胞など、勤労と言う言葉が8度も用いられています。
経済的な失敗者は、道徳的な敗北者になる
歴史を遡ると、江戸時代の後期の民衆の間に広く定着していた「通俗道徳」的倫理観に注目することができます。江戸時代後期の商品経済の急速な浸透によって、民衆は商品経済に巻き込まれ、「家」まるごと没落の危機に直面しました。そうした事態に直面した民衆は、勤勉、倹約、謙譲、分度などの規範を内面化し、それに従うことで家没落の危機を回避しようとしたのです。こうした勤勉、倹約、謙譲、分度などの規範が「通俗道徳」と言われるものです。
その後、この「通俗道徳」というイデオロギーが今日に至るまで、日本国民を縛り続けていくことになります。市場経済において、努力したにもかかわらず、失敗する人間は常に存在します。しかし、通俗道徳、すなわち「勤勉に働き、倹約に務め、努力するものは成功する」というイデオロギーを前提とすると、経済的な失敗者は、そのまま道徳的な敗北者になります。高度経済成長を牽引した、時の内閣総理大臣池田勇人は、「救済金を出して貧乏人を救うという考え方」を批判して、占領期の社会政策を「贅沢過ぎ」だと断罪しています。それは、経済的弱者を救うことは「濫救」「惰眠」を増加させるものだとみなされていたからです。
生き馬の目を抜く万人の万人に対する戦争
通俗道徳が支配する社会とは、「努力が必ず報われる」という建前のもとで、勝者と敗者が存在する社会です。しかし、個別の人生1つひとつを取りあげてみれば、そこには多くの偶然が介在しますので、実際には努力が必ず報われるという保証はありません。それにもかかわらず、人びとは、自らが通俗道徳を実践したことを証明し、社会的な承認を勝ち取るために経済的に成功しなければなりません。
その結果、勤勉、倹約、自己規律を求める通俗道徳は、逆説的に、生き馬の目を抜くような、「万人の万人に対する戦争状態」としてのホッブズ的世界を招き寄せてしまうのです。それが、極端な競争社会に全面化するのは、明治維新によって、江戸幕府が崩壊し、それまで人々の行動に枠をはめていた江戸時代の身分制的秩序が崩壊した後のことです。現在の「分断社会」の原型はこの明治時代に生まれています。そして、この状況を大本教の教祖である出口なおは「獣の世」(※)と呼んだのです。
通俗道徳は皇国勤労観へ変貌して延命した
通俗道徳的な規範に立脚した社会はアジア・太平洋戦争の敗戦で最大の危機を迎えます。
しかし、通俗道徳は、この危機の時代を「勤労」や「倹約の美徳」の思想となって生き延びることになります。日本政府は1つひとつの通俗道徳の実践という従来の価値観を「家の存続と個人の立身出世」を目的とするものから「国家」を目的とするものへと変換させました。それが「皇国勤労観」です。これは後に、労働への義務意識が染み込んだ日本の「勤労国家レジーム」の成立につながっていきます。
「勤労国家レジーム」のもとでは、勤労者への減税と勤労の機会を保障する公共投資を骨格とし、社会保障には多くの予算を組みませんでした。社会保障は就労ができない人向けの現金給付に集中し、サービスすなわち現物給付の占める割合は「限定」されることになりました。しかも、限られた資源を配ろうとすれば、低所得層や高齢者、地方部といった具合に、分配の対象を「選別」せざるを得なくなります。そして、この限定性、選別性の背景には「自分でできることは自分でしなさい」という「自己責任」の論理が徹底的に貫かれています。
このことは、現役世代にとって、生活の必要、すなわち、住宅、教育、老後の生活等に必要な費用を、自分たちで稼得しなければならないことを意味していたのです。
しかし、バブルが崩壊後、状況は一変した
一時は奇跡的とも言うべき高度経済成長による所得増大によって、多くの人々は自らの責任で生活の安定を確保することができました。人々は、「勤労国家レジーム」に基づき、
「倹約の美徳」を称賛し、将来に備えるため「貯蓄」に励みました。勤労を前提として、社会保障を限定する自己責任型の福祉国家を維持することができたのです。ここでは出口なおの案じた「獣の世」は、限定的にしか現れてきませんでした。
しかし、バブルが崩壊後、状況は一変します。減税と公共事業に支えられた勤労国家の発動も虚しく、国際的な賃金下落圧力が景気回復を妨げ、巨額の政府債務が積み上がりました。また、少子高齢化が進み、専業主婦世帯と共働き世帯の地位も逆転、近代家族モデルは完全に破綻しました。さらにバブル崩壊に追い打ちをかけるように、市場原理や競争原理、自己責任論が持ち込まれました。
今、日本社会は通俗道徳の実践にエネルギーを費やした多くの敗者で溢れています。働くことは苦痛でしかなく、勤労の先に待ち構えるのは貧困のリスクなのです。まさに「獣の世」の再来と言えます。
(つづく)
【金木 亮憲】
(※)明治日本は一般的には、政治指導者から1人ひとりの国民までが一致団結して「近代化」を追い求めた、つまり「価値観が共有された時代」と言われる。しかし、その一方で、この明治日本を「獣の世」と喝破した人物がいる。大本教の教祖である出口なおである。
『外国は獣類(けもの)の世、強いもの勝ちの、悪魔ばかりの国であるぞよ。日本も獣の世になりて居るぞよ。外国人にばかされて、尻の毛まで抜かれて居りても、未だ目が覚めん暗がりの世になりて居るぞよ・・・』(出口なお 1837‐1918)
「獣の世」(「分断社会」はその顕在化の1つ)は明治日本から始まり、一時高度経済成長の陰に隠れて見えなくなっていた。しかしバブルが崩壊、そして今、近代そして資本主義の終焉が近づくにつれて、「新自由主義」などと姿を変えて再びその牙を剥き始めている。
温かみのある、情熱や思いやりに満ちた社会、他者への配慮にあふれ、仲間のために行動することをよしとする誇りある社会、そんな日本社会はもはや昔話になった。そして、今や「貧困」や「格差」という言葉が日本社会を語る日常的なキーワードになりつつある。
<プロフィール>
井手 英策氏(いで・えいさく)
慶應義塾大学経済学部教授。専門は財政社会学。1972年 福岡県久留米市生まれ。東京大学大学院経済研究科博士課程単位取得退学。博士(経済学)。著書に『経済の時代の終焉』(岩波書店、大佛次郎論壇賞受賞)、共著に『分断社会を終わらせる』(筑摩選書)、共編に『分断社会・日本』(岩波ブックレット)、『Deficits and Debt in Industrialized Democracies』(Routledge)など多数。