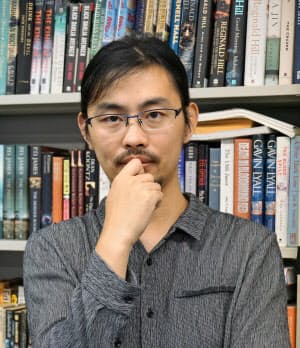[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
酔生夢人のブログ
気の赴くままにつれづれと。
[PR]
×
形式は正しいが意味がない、ということ(「色のない緑」)
この作家は、推理小説の書き手としてではなく、「小説」の書き手として巨大な才能を持っていると思う。つまり、ジャンルに限定される才能ではない。
とある「SFアンソロジー」(「百合SFアンソロジー」という副題があるwww)の中の彼の作品「色のない緑」を読んで、その頭脳の緻密さと表現力に驚嘆したので、ここにメモしておく。
なお、「色のない緑」とは
colorless green ideas sleep furiously
(色のない緑の思考が猛烈に眠る)
という、文法としてはまったく正しいが、意味をなさない文に由来するらしく、言語学や、特に人工知能を使った翻訳の大きな問題であるようだ。
(以下引用)
「女の子の青春描く」中国発・本格ミステリー
とある「SFアンソロジー」(「百合SFアンソロジー」という副題があるwww)の中の彼の作品「色のない緑」を読んで、その頭脳の緻密さと表現力に驚嘆したので、ここにメモしておく。
なお、「色のない緑」とは
colorless green ideas sleep furiously
(色のない緑の思考が猛烈に眠る)
という、文法としてはまったく正しいが、意味をなさない文に由来するらしく、言語学や、特に人工知能を使った翻訳の大きな問題であるようだ。
(以下引用)
「女の子の青春描く」中国発・本格ミステリー
- 2019/10/21 2:00
PR