某サイトから、「歌会始」レポートである。
歌というものは表の意味と、暗示されたものが同居していることもあるから、こうして深読み裏読みを解釈して楽しむことができる。まあ、不敬とも言える解釈もあるが、知的娯楽と思えばいい。
で、陛下の歌だが、確かになかなか暗示的だ。凄みがある、とも言える。
夕やみのせまる田に入り稔りたる稲の根本に鎌をあてがふごく単純な陰謀論的解釈なら、「田」は「田布施システム」であり、「田布施システムに夕闇が迫っている今、私はそれを根本から刈り取るつもりだ。(刈り取りたい気持ちだ。)」
となる。(笑)
まさか、「稲」が「稲田朋美」とかいうチンケな右翼政治家ではあるまい。
皇室の継嗣問題の比喩だという説がコメント中にあるが、それは完全な妄想だろう。
ごく普通の解釈をすれば、「夕闇のせまる田」は、ご自分の老境を表し、そろそろ一生を締めくくる頃だ、と淡々と述懐している歌だ、となりそうだ。もう少し言えば、「稲の根本に鎌をあてがふ」は、最後に何か思い切ったことをしようという決意を表しているようにも思える。
しかし、「本」というお題なら誰でも「book」を題に詠むことしか考えないだろう。そこに「根本」という語を持ってきたのは驚かされる。ここに何か尋常でない意図がある、と思うのは考え過ぎか。まあ、考え過ぎだろう。(笑)
(以下引用)
295: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:04:41.73 ID:0ONtH2350
歌会始の陛下と皇族方の歌ざっくりレポ。
仮名遣いなど間違いがあったらごめんなさい。
-----------
平成二十七年 歌会始 皇居正殿松の間
御題 「本」
承子のひめみこ(承子女王)
霧立ちて紅葉の燃ゆる大池に鳥の音響く日本の秋は
日嗣の御子のみめ(雅子妃殿下)
恩師より贈られし本ひもとけば若き学びの日々のなつかし
日嗣の御子(皇太子殿下)
山あひの紅葉深まる学び舎に本読み聞かす声はさやけし
后の宮の御歌
来し方に本とふ文の林ありてその下陰に幾度いこひし
大御歌(御製)
夕やみのせまる田に入り稔りたる稲の根本に鎌をあてがふ

298: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:09:44.38 ID:A3KKB1+50
>>295
皇太子が、山は紅葉
皇后陛下が、文に憩う
天皇陛下が、夕闇せまる
334: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:45:37.35 ID:3SPWQo440
>>298
皇后陛下の「文」は秋篠宮殿下のこと?文仁親王。

344: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:49:42.20 ID:A3KKB1+50
>>334
わざと入れてるでしょうね
428: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 14:07:33.18 ID:HTTliFBb0
御製は品格があり、自然な流れるような調べといい、実体験の強さといい、周囲の空気感までありありと伝わってまことに素晴らしい。御製かくあるべし。僭越ながら。
また、あえて「夕闇の」と発せられたところに、お心の何かがあるのだろう。
「根本に鎌をあてがう」というのも、ご決意の表れか?と忖度申し上げる。
皇后陛下の御歌は、意外にも、「来し方」という大きなものを扱われていた。
あえて「文という名の林ありて」「その下陰に幾度いこひし」と秋篠宮家に感謝のお気持ちを表されたと思う。
434: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 14:11:49.22 ID:ZB4NqTBj0
>>428
>あえて「文という名の林ありて」「その下陰に幾度いこひし」と秋篠宮家に
>感謝のお気持ちを表されたと思う
そう感じた奥様方、多そう
277: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 11:47:17.90 ID:rN1MHIJC0
陛下のお歌は皇太子を切るって意味に思えたんだけど、希望的観測すぎるかな。
280: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 11:48:54.10 ID:Fi2EtgGb0
>>277
私もそんな風に深読みしちゃったw
288: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 11:55:25.89 ID:A3KKB1+50
陛下の御歌は、鎌のところより
夕闇がせまるっていうところが怖い
302: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:17:42.45 ID:rN1MHIJC0
>>280
>>288
>夕やみせまる田
次代の日本。皇太子の次代は闇の世界
>稔りたる稲
皇太子
>根本に鎌をあてがふ
いつでも切れますよ
と思ったんだけど、陛下ほどの人が素人が簡単に読み取れるようなお歌は歌わないかな…
329: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:38:53.07 ID:JsBPoI380
>>302
ちょっと思いましたよ
「刈り取ること」がそのまま「稔りを受け取ること」なのよね…意味深
337: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 12:46:52.64 ID:3SPWQo440
>>302
ですよね・・・人生の夕闇が迫る・・・刈り取らなくては、の思い。
陛下の人生をたとえてらっしゃいます。
381: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 13:13:45.84 ID:aGah/AyU0
>>280
>>302
>>329
>>337
同じように感じた方が、こんなにいらしたとは!
419: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 13:58:47.25 ID:8Qkh8XSd0
仕事終わって、歌会始の様子、今拝見しました。
陛下の御製、
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」が座右の銘だったあのヒトを根本から刈りとる、という意味かしら、
と、ちょっと鳥肌が立ちましたです。
(深読みが過ぎますかしら)
(*「実るほど頭を垂れる稲穂かな」が座右の銘だったあのヒト・・・マ○コさまのこと)
430: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 14:08:15.07 ID:yeyP94fo0
>>419
私も一瞬あのヒトのことが脳裏をよぎったわ。
でも他の意味もあるのかな。
隠された意味を色々考えるのは、楽しかったり恐ろしかったり。
424: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 14:01:15.84 ID:kxUVCF3D0
和歌は短い言葉の中にいかに色んな意味を込めるのか、
またその込めた意味を相手が気づいて理解して、ほほぅ~っとなれるか
知識や教養、タイミング、そういう粋なやりとりを楽しむものよね。
低俗とか下衆の勘繰りだってシャットアウトして字面だけしか見ない人にはわからないだろうな。
陛下の歌を聞いた時のナルさんの顔も、何も感じてなさそうだったw
468: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 16:16:36.68 ID:JdLxBYVE0
佳子様と色がかぶりまくりの女官?、イヤリングも無駄に大きかったけど、有りなのかしら?
私の両親は俗に言うお百姓だったけど、夕闇せまる田畑で刃物は使わなかった。
むしろ禁忌に近かったと記憶している。手製の道具も使うから、うっかり作業中に刃が柄からスポって離れたりすることもあるらしい。
探す手間や万が一怪我をしたりを考えると、切りの良い所で田んぼからあがちゃって翌日に備える。
そもそも夕やみがせまる時間って何時頃だろ?
534: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 18:38:47.12 ID:84DqbPx10
>>468
興味深い話だね。
確かに、暗くなってからも農作業している人は見たことない。
陛下の歌の「夕やみのせまる田に入り 」という箇所。
農作業を長時間やっていて暗くなった、という感じではなく、わざわざ暗くなった田んぼに入って行ったと読み取れる。
542: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 18:49:21.60 ID:EKe15G060
>>534
公務の合間を縫ってとかじゃないの?
お百姓さんはそれだけが仕事だけど陛下は色々あるだろうし
545: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 18:55:27.47 ID:rzqxkbxA0
>>542
夕方に稲刈りすることもあるのかもしれないけど
ニュースとかで出てくる映像は昼のものだし
わざわざ夕方をしめす言葉を使ってるんだから
なにか意味はあるのかと
560: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 19:09:13.82 ID:84DqbPx10
>>545
そうだよね。
暗くなってから何かをするとか、お公家さんが一番嫌がるイメージ。
物の怪とか来そうだし。
こういうのって、分かる人には分かる暗号なんでしょうね。
477: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 16:30:27.50 ID:tkmc+jyR0
夕やみのせまる田に入り
→人生の終わりも近くなり
稔りたる稲の根元に鎌をあてがふ
→これまで種を蒔いて育てた稲を刈り取るときが来た。
(自分のやってきたことの責任を取り、後継問題に決着をつける)
このように解釈しました。
皇后陛下のみうたも、秋篠宮殿下のことを詠まれたかに思いました。
543: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 18:52:29.66 ID:I4Yz+my80
>>477奥様と同じ解釈をしました。
この時ばかりは言霊を信じたくなりました。
478: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 16:30:41.44 ID:7LfdaN+m0
「夕やみのせまる田に入り 稔りたる稲の根本に 鎌をあてがふ」 この裏の意味を私なりに解釈してみました。
①なぜ「夕やみ」なのか?
デレビで以前に稲を刈り取られる陛下の映像を流したことがありましたが、まだ明るく夕闇ではありませんでした。
何故新年早々の歌で不吉な匂いのする「夕闇」なのか疑問です。
「太陽」は天皇陛下を表す比喩表現としてよく使われますが老境にあるご自身を『夕闇の(頃の太陽)』に例えられたのかもしれません。
494: 可愛い奥様 投稿日:2015/01/14(水) 16:59:01.80 ID:yTgOlurH0
>>478 もう太陽が東にはなく西に移ってなくなろうとしているのでは。
そしてとうとう根本(こんぽん)に鎌をお入れになるのよ。
・・・と解釈









 宋 文洲
宋 文洲 






 As I was wrapping up my travels in Asia, an extremely sad event unfolded in Paris during which 12 people were murdered at the office of satire magazine Charlie Hebdo. Just four days later, another sad and pathetic event occurred. A swarm of politicians, many of whom are professional authoritarians, shamelessly descended onto the streets of Paris to “join millions of protesters” in a rally for free speech and solidarity with the victims of the barbaric attack.
As I was wrapping up my travels in Asia, an extremely sad event unfolded in Paris during which 12 people were murdered at the office of satire magazine Charlie Hebdo. Just four days later, another sad and pathetic event occurred. A swarm of politicians, many of whom are professional authoritarians, shamelessly descended onto the streets of Paris to “join millions of protesters” in a rally for free speech and solidarity with the victims of the barbaric attack.







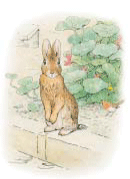 1月11日にフランス全土で展開された「反テロ・共和政擁護」の大示威行動の様子を伝えるフランスのテレビ、france2 の同日20時のニュースのリンクを貼ります。
1月11日にフランス全土で展開された「反テロ・共和政擁護」の大示威行動の様子を伝えるフランスのテレビ、france2 の同日20時のニュースのリンクを貼ります。