憲法解釈の変更による実質的改憲、つまり解釈改憲は、本物の改憲以上に害が大きい。それはつまり法の根本が成り立たなくなることだからだ。言い換えれば「法的安定性」を失うからだ。その法的安定性を軽視する発言をした磯崎補佐官は、罷免されて当然だろう。公務員の役目は法を遵守し、遵守させることにあるからだ。政令(行政命令)も、法に違反すれば成り立たないし、法は憲法に違反すれば成り立たない。つまり、国家の土台は憲法にある。その憲法が時の政権の一存で勝手に解釈できるならば、国家が成り立つはずがない。
「論語」の言葉で言えば、「信無くんば立たず」、国家に「信」というものが無ければ、国家は成り立たない、ということだ。その「信」を与党政治家たちはことごとく投げ捨ててきた。そんな国家が成り立つはずがあろうか。
https://twitter.com/kahajime法的安定性を軽視する政府は国民からの信用を失う。
政府が今日言っていることを明日も同じように言うとは限らない、と思われてしまうからだ。
たとえば、法的安定性を軽視している政府が「徴兵制は憲法違反」と断言しても、信用されるはずがない。
是非ご一読を。「法的安定性を損なう、『馬鹿』の所業」⇒篠原さんのツイッターまとめ
⇒
http://togetter.com/li/835871仮に法廷だったら、裁判長から「余計なことを言わず、質問に端的に答えなさい」と言われまくるだろう。
安倍首相の答弁。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
http://togetter.com/li/835871shinshinohara氏
https://twitter.com/ShinShinohara「馬鹿」の起源・・・法的安定性を損なう「馬鹿」の所業
「馬鹿」の起源をご存じだろうか。
秦の始皇帝の死去後、絶大な権力を握った趙高は、朝廷に鹿を連れてきた。
鹿を趙高は「馬だ」といった。
鹿だ、と答えた人間は皆殺しにした。
趙高の権力を恐れた秦の大臣たちは口をそろえて「馬でございます」と答えた。
この瞬間、秦の法治は崩壊した。
秦は春秋戦国時代の強国の中でも独特の統治だった。
「法治」。
その他の国は、優れた王や大臣が現れると栄えるが、その人物が死んだ途端に国力が低下する、という盛衰を繰り返した。
孔子は「礼(儀式化)」によって国を治めることを提案し、法治国家へのヒントを提示したが、まだ十分ではなかった。
法治で国が栄えることを示したのが管仲。
ルールを明確に定め、君主の気分で罰せられることがないようにし、豊かな生活を送るにはどう行動すべきかを全国民に示した。
これにより斉は中華一の強国にのし上がる。
しかし管仲の事業は十分理解されず、死後、あっさりと法治は失われ、斉は弱体化していった。
秦は意識的に法治国家となった。
商鞅は秦国の法律を明確に定め、国民はおろか、総理大臣に至るまで法に従うよう定めた。
商鞅は自ら定めた法律により死罪となるという皮肉な結果を招いたが、秦はこの後、着実に国力を増した。
君主や大臣、武将が誰になろうと。
秦の法治主義を完成させたのが韓非子。
のちに始皇帝となる秦王はその著作を読み、いたく感激した。
法によって国を統べることにより、秦は並ぶものなき強国となった。
そのほかの国が君主の能力によって栄枯盛衰を繰り返したのと比べて、好対象であった。
なぜ法治主義だと栄えることができるのだろうか?信賞必罰のルールが明確だからだ。
他の国では、君主の気分次第で罰せられたり褒められたりして、庶民はそのつど惑乱していた。
君主が入れ替わるたび、それまでの努力が水の泡になったりしたのだ。
秦の強国ぶりは、大臣でさえ法に従わなければならぬ、という法治主義によって達成された。
君主が少々愚かでも、大臣がパッとしなくても、法に従って行動すればそこそこのパフォーマンスが得られるよう、法が設計されていた。
秦は法治国家だったからこそ、強国にのし上がれたのだと言える。
国際政治経済学者のスーザン・ストレンジが指摘したのも、まさにこのことだ。
秦以外の王国は、ストレンジが指摘する「関係性権力」で統治されていた。
君主の気分で栄えたり衰えたり。
君主の優劣で盛衰が決まるので、国全体としての継続的発展ができなかった。
しかし秦は法治構造を構築し、その構造の中で人々がどうふるまうべきか、ルールを明確にした。
こうすることで君主が入れ替わっても庶民に迷いがなくなり、今まで通り商売ができるようになった。
ルールさえ明確であれば、努力を重ねることができ、ますます栄える。
これが構造的権力だ。
現代の民主主義国家は、すべて法治による構造的権力で統治している。
どうふるまえば犯罪となり、どうふるまえば正々堂々と豊かになれるのか。
そのルールが明確だから、人々は迷いなく努力を続けられるのである。
だから民主主義国家では、法的安定性をことのほか重視する。
冒頭に戻ろう。
趙高は「馬鹿」事件により、秦の法治主義を葬り去り、権力者の気分で左右される権力主義に転換させてしまった。
このため、秦の人々は何に従うべきか、惑乱するようになった。
始皇帝の死後、わずかな年数で秦が崩壊したのは「法的安定性の喪失」があったからだといえる。
秦ののちに成立した漢は反省に立ち、法治を採用した。
その後、漢は400年もの平和と繁栄を築いた。
以後、どの王朝も法治をとった。
秦末期のあまりに些末な法律への反省もあり、老荘思想を一部導入しおおらかな法律にしたという違いはあれど、法治は国を栄えさせるのに必須だという共通認識となった。
法治を選択し、法的安定性の維持に努めれば、愚かな君主・大臣が現れても国力を大きく損なわずにすむ。
これが、秦とその後の王朝が教えた教訓である。
欧米ではモンテスキューが「法の精神」で訴えた。
ルールが明確だから、人々は迷いなく努力を続けられる。
継続した努力が、国を栄えさせるのである。
しかし法的安定性を損なうと、人々は何で罰せられるか分からなくなる。
何かの秘密を暴いた罪で囚われても、その秘密が何なのか明かされないまま、罰せられる恐怖があれば、人々は萎縮する。
法が法を否定するような矛盾が起きると、法的安定性が失われ、人々はどう生きていくべきか、困惑する。
人々が困惑すれば、どう努力すれば財産を失わずに済むのか、分からなくなる。
権力者のご機嫌を損なわないように、という「関係性権力」で国が支配されるようなる。
愚かな君主になれば、北朝鮮そっくりになる。
君主の気分次第で処刑されてしまうのだ。
現在、安全保障関連法案について、憲法学者の大多数が違憲だと述べている。
これに対し高村氏は砂川判決を根拠として合憲だとするが、それを支持する憲法学者はごく少数にとどまるようである。
与党議員は「合憲」で口をそろえる。
何かに怯えるように。
趙高が「鹿」を「馬」だと言い張ったのと似てはいまいか。
並み居る政治家たちが「馬でございます」と口をそろえるのも。
「馬鹿」がまかり通れば、失われるのは法的安定性である。
法的安定性が失われた時、強国であったはずの秦はあっという間に滅びた故事を、私たちは忘れるべきではないのではないか。
法治を放棄した後、秦ではすぐに陳勝・呉広の乱が勃発する。
自ら法的安定性を損ねておきながら、庶民には些末な法律を押し付ける矛盾に我慢しきれなくなった庶民が、全国で蜂起した。
リーダーが法を守らないのに、なぜ庶民が守らねばならぬのだろう?関係性権力の脆弱さはここにある。
憲法が権力者を縛るのは、法的安定性の要諦だからだ。
もし権力者が憲法を無視し、権力の好むままに法律を乱造すれば、結果として権力者の気分で国が支配されるようになり、法的安定性が揺らぎ、法律を守って行動することがバカバカしくなる。
反乱が起きるのは、権力が法治を否定することから始まる。
日本でも「馬鹿」事件は起きてしまうのか。
我々はどう行動すべきか。
「馬鹿」は法治を損ない、国を亡ぼす。
戦争で自分の国を守る前に、国が内部から瓦解するのである。
今や国は法治によってのみ維持されていることを、失念してはいけない。
法的安定性を損なうことは、国の自殺行為である。

 広瀬すずさん=山本和生撮影
広瀬すずさん=山本和生撮影









 小田嶋隆
小田嶋隆 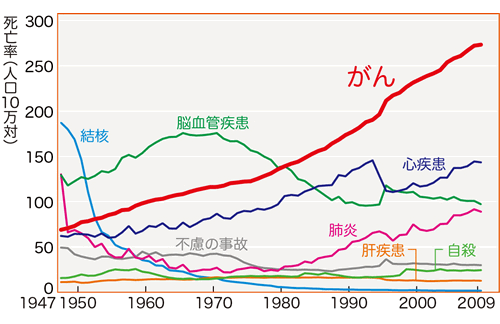
Is Japan's Emperor Akihito Trying To Stop Abe?
http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2015/08/04/is-japans-emperor-akihito-trying-to-stop-abe/
ちょっち、期待し過ぎだと思うが・・
法案が可決成立したら、天皇が奏上の日から30日以内に公布することになっている
天皇に国事行為の拒否権はあるかってえと、昔の国会答弁では拒否権はないらしいw
でも法律は「国民のために」交付するのだから「国民のためにならない」と天皇が考えたりした場合、内閣に質問することはできるらしいww
30日間連続質問攻めも良いなあwww
無理かなあw
第061回国会 内閣委員会 第7号
昭和四十四年三月十四日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/061/0020/06103140020007a.html
○藤田委員長 受田新吉君。
○受田委員 今度御提出に相なっております宮内庁法の一部改正法案、これをお尋ねをする前提として、まず国の基本的な問題として、憲法第一条にある国民統合の象徴であられる天皇の御地位並びにこれに関係する諸問題をお尋ねしたいと思います。
憲法第一条の規定する象徴天皇というお立場は、一切の行政上の責任、そういうものを持たない立場のお方が天皇であるという形になるのか。またある程度の天皇に対する、統治というきびしいことばでなくして、憲法第一条の規定による陛下御自身の責任問題がどこかにひそんでおるのかどうか、ひとつ御答弁願いたいと思います。
○宇佐美説明員 象徴たる天皇の御地位あるいはその権能、これは申し上げるまでもなく憲法によってその権能は制限的に列挙されておるものと存じます。しかもこれにつきましては、常に内閣の助言と承認ということでございますので、行政的な問題につきましては当然お触れにならないという考え方であると理解をいたしております。
○受田委員 憲法第七条には「天皇は、内閣の助一言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と、「国民のために」こういうことが書いてあるわけですから、国民のためにならない国事行為は行なうことができないというまた裏の解釈ができるかどうかです。
○宇佐美説明員 内閣の助言と承認そのものが国民のためでなければならないというふうにも読めるわけでございます。内閣の助言と承認がある揚台にそれがはたして国民のためかどうかという御判断は、内閣が責任を持ってそろいう立場で助言と承認をしておられるというふうに私どもは考えるほかはないと思います。
○受田委員 憲法の規定からは、天皇に対しては、内閣の助言と承認がありたる事項に関する拒否権は一切ない、こういうことですね。
○宇佐美説明員 一言にしていえばそういう関係であろうと思います。
○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり)
○宇佐美説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。