「日々平安録」から転載。
音楽の知識はゼロだが、「日常の基本事項の謎と推理」というのが好きなので、こういう話は面白い。
私は、そもそも小学校の音楽の授業で挫折した口なので、「和音」とは何か、という定義すら知らない。何やら、「ドミソ」「ドファラ」「シレソ」とかぼんやりと覚えているが、音を三つ、同時に、あるいは連続して鳴らせば和音なのだろうか。「和」とは「足し算」のことだから、「音の足し算」が和音なのか。だが、なぜ「ドミソ」や「ドファラ」や「シレソ」で、「ドレミ」や「ドレファ」などではいけないのか、さっぱり分からない。
経験的に発見された「気持ちのいい和音」と「気持ちの悪い和音」があるのか、とも思うが、それなら、私から見て(聴いて)「わざわざ気持ちの悪い音の連続を作っている」としか思えない「現代音楽」(クラシックの現代音楽、というのも奇妙な言い方だが)というものがなぜあるのか。
「カデンツ」が西洋音楽の基本、というのも薄ぼんやりとだがイメージはある。つまり、明確な「起・承・転・結」で曲を構成することではないか。そして、「起」にはそれにふさわしい音(和音)が決まっており「承」も「転」も「結」も同様、ということかと思う。
なお、今、ギターで確認したら、「ドミソ」がCコードで、「ドファラ」がFコードであった。G7は「シレソ」がほとんどだが、それに最高音に「ファ」がくっついているだけだから、ほとんど「シレソ」と言っていいか。で、このCとFとG7三つを組み合わせれば、なかなか気持ちのいい音の連続になるのは確かだ。やはり、「主要3和音」というのは嘘ではないようだ。
なお、G7の「ファ」を一音上の「ソ」にしたら(つまり「完全シレソ」にしたら)、Gコードになる。つまり、主音とは「ド」の音で、C。下属音とは「ファ」の音で、F。属音とは「ソ」の音で、G、ということか。それなら、下の記述にあるように、ファはドから数えて「第4音」になり、ソはドから数えて「第5音」になる。アルファベットでFはCから4番目、GはCから5番目である。
「下属音」とか「属音」とかいう名称は、「門外漢」を音楽世界から遠ざけるものだろう。それに、なぜドレミファのアルファベット表記をAから始めなかったのか、いまだに疑問である。西洋音楽の表記法がドレミファより先に存在したとはいえ、「ド」を主音とするなら、それをAから始めて当然だろう。この「ドレミファがAから始まらない」のために小学校の音楽の授業に疎外感を感じ、クラシック音楽や「音楽理論」に興味をなくした子供は無数にいるのではないか。
英文法の用語も科学用語もそうだが、「専門用語」には、無神経で、無意味に人を悩ませるものが多い、と思う。
(以下引用)
■[雑]今日入手した本
R・パワーズ「オルフェオ」
これも日曜の朝日新聞の読書欄で紹介されていた本。もう届いた。早い。
パワーズの本は氏の処女作「舞踏会に向かう三人の農夫」を多くの批評家や文学者(記憶では例えば高橋源一郎さん)が賞賛していたので、何だか読まないといけないような気がして手にした記憶があるが、ちっとも面白くなくて途中で抛りだした記憶がある。
本書は新聞での紹介によれば、聴衆よりも演奏家のほうが多い演奏会といった現代の先鋭的な作曲家を主人公にして、それを科学と結びつけるといった趣向の小説のようであり、こちらの関心とあっているなあと思い、読もうかなと思った。
若いころ、芸大の作曲科卒のかたがたと少しおつきあいしたことがあるが、ある方は「ブーレ―ズの曲は楽譜で見るととても面白いのですよ」というようなことをいい、あるひとは作曲するとは、新しい音色を発見することだと思っているようであった。楽譜で見ると面白いが演奏して聴くとつまらない曲とは? 作曲とは形式と様式の追求ではないの? 問題は、西欧古典音楽の分野においては、やるべきことはもうすべてなされてしまったのではないのかという問題なのかと思った。西洋の進歩史観において、音楽だけは(美術ではまだそうでもないかもしれない)18世紀から19世紀に頂点をむかえてしまったのではないかということである。そのときからこの問題には関心があるし、西洋の秘密は音楽と科学のなかにあるのではないかと思っているので、その双方を同時にあつあっているらしい本書のテーマはいかにも魅力的に思えた。
まだとりあえず60ページくらいまで読んだだけであるが、つまらない。ほとんど主人公のモノローグが延々と続いていて、そもそも小説的な感興がまったくわいてこない。
とにかく、ある程度の音楽にかんする知識がないと書いてあることがほとんど理解できないだろうと思う。音楽を言葉で表現することの絶望的な困難ということを痛感する。今まで読んだ部分ではたとえばモツアルトのジュピターの終楽章とかマーラーの「亡き子を偲ぶ歌」が出てくるのだが、それを全然きいたこともないひとにはただもうちんぷんかんぷんであろう。そんな無知蒙昧な読者などはそもそも相手にしとらんよということなのかもしれないが、そういう態度こそが、現代音楽の衰退を招いたのだと思う。現代文学だってやるべきことはすべてやられてしまって、すべての書は読まれてしまっているので、こういう手しかもう残されていないのだよ、ということなのかもしれないが・・。
西洋音楽の根幹をなすカデンツの構造、ピタゴラス音階、純正調と平均律、20世紀の音楽の歴史のあらましといった予備知識が必須である。26ページに「主音。下属音。属音。この連中はもっと新しいコードを勉強する必要がある」というところがある。これはポピュラー音楽が相も変わらぬカデンツの進行で曲ができていることを未来の作曲家である小さな子どもが批判している部分なのだが、ここで主音というのには注がなく、下属音に「各音階の第四音。主音、属音に次いで重要な役割を果たす」、属音について「各音階の第五音で、主音に次いで大切な、調を支配する音」という(おそらく訳者の)注がついている。しかし、ここではコードということがいわれているのだから、「主和音、下属和音、属和音」と訳さねばいけないところだろうと思う。「主和音、下属和音、属和音」そしてそれが主和音に解決というのがカデンツの構造で、それが西洋古典音楽のすべてを規定している。
昔、属啓成さんの「作曲技法」という本を読んでいて、そのはじめが「カデンツ」で、ベートーベンの皇帝協奏曲を例に引いて、曲の最初、オーケストラがジャーンと和音をならす。そこにピアノが指ならしのようにはいってきて、ひとしきりするとまた、オーケストラが次の和音をならす、またピアノが走句を弾き、やがてまたオケが和音で、またピアノが動き回った後、次の和音から主題がはじまる、その三つの和音が主和音と下属和音と属和音で、それが主和音に解決していく、それが西洋の古典音楽の根幹であると書いてあるのを見て、へえーと感心したことがある。そんなことにいわれてはじめて気がつくくらいだから、こちらの音楽の感受性がいかに乏しいかであるが、とにかくこの26ページの記述を読んでカデンツの進行が身体的に感じられるひとでないと本書で書かれていることはほとんどお経のようなものに感じられるだろう思う。少しは頭の知識はもっているわたくしが読んで全然面白くないのだから、どういうひとがこれを面白がるのか見当がつかない。
そもそも何でこういう問題をなぜ小説というかたちであつかうのかというのが根本的な疑問である。エッセイで書けばいいのではないか? そうしたら問題の焦点をきちっと論じられるのではないか? すごく大切なテーマのはずなのである。そもそも、パワーズは西洋の音楽を普遍的なものと思っているのだろうか?(今までのところではそう思える) 西洋ローカルなものとは思っていないのだろうか? おそらくカデンツの構造は倍音という物理学、ピタゴラスの発見した弦の振動という純粋な物理に由来している。その物理現象は世界のどこでもみられるものであるはずなのに、なぜそれが西洋でのみ発達したのだろう。倍音に依存するということは音楽の基礎が低音(根音)にあるということである。西洋くらい低音を演奏することに特化した楽器が多く存在するところはないのではないか? 雅楽などは高音しかないのでは?
この本も中途で抛りだすことになるのだろうか? 先にほうでは上に述べた問題も議論されているのだろうか?

PR






 よしまさこ2号
よしまさこ2号  Cdb
Cdb 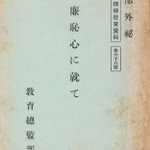
 Hicetubique0ham
Hicetubique0ham


















 各務原 夕 秋はキノコ狩りの季節
各務原 夕 秋はキノコ狩りの季節  欺瞞動画の会社
欺瞞動画の会社  たられば
たられば  鳴海圭矢
鳴海圭矢  Q/重力波天文学徒
Q/重力波天文学徒  高橋裕行
高橋裕行  知花 竜海
知花 竜海  リアリズムと防衛のBOT
リアリズムと防衛のBOT  うりゅう@四国スト2親方
うりゅう@四国スト2親方  fj197099
fj197099  Q崎
Q崎  高城(たかぎ)悠紀
高城(たかぎ)悠紀  山口二郎
山口二郎  本条靖竹
本条靖竹  マイナー名言bot
マイナー名言bot  早川タダノリ
早川タダノリ 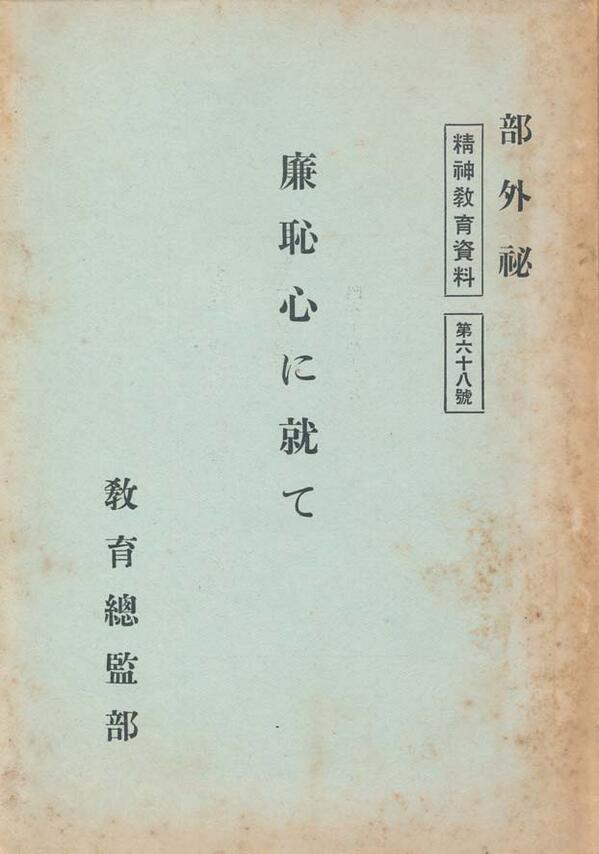
 山内太地
山内太地  サガミ
サガミ  ふみたけ
ふみたけ 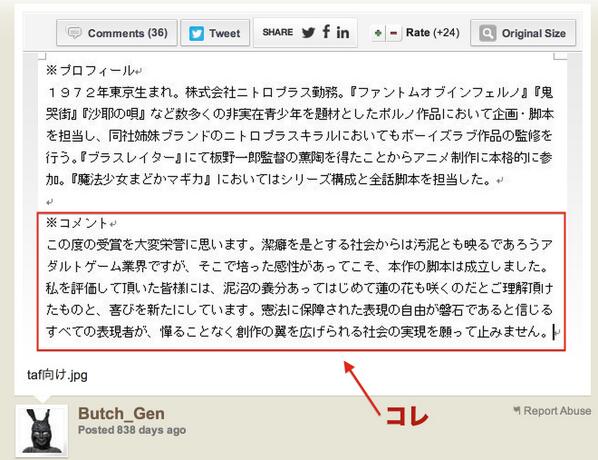
 ヨーゼフP
ヨーゼフP  toru shimada
toru shimada 