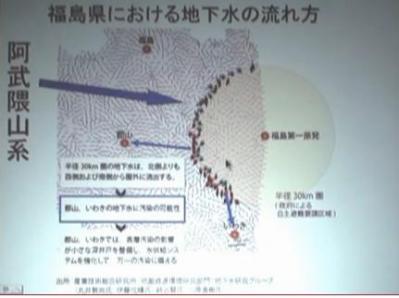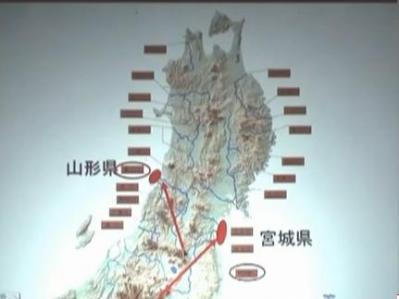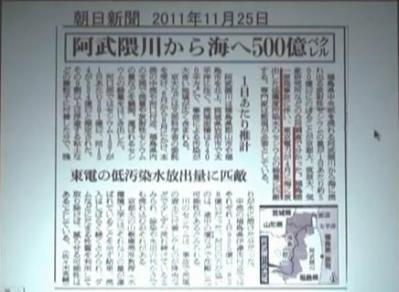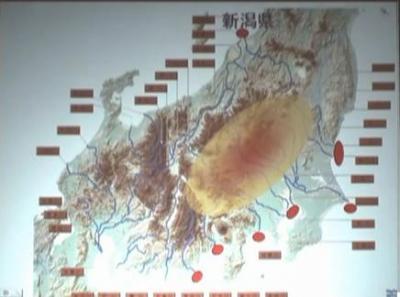麻生発言について私が読んだ中で、もっとも深い内容を持っているのが、下の「晴耕雨読」記事である。筆者は日本生まれの韓国人らしいが、それだけに通常の日本人とは異なる「外部の目」で日本を冷静に分析できているようだ。麻生の笑顔がチャーミングである、という評価は、言われてみればその通りで、普段のドスの利いたギャング顔との落差がまた一種の魅力でもある。それに、あの馬鹿さ加減も、けっして人に嫌われるものではない。むしろ、人間は自分より知能の劣る存在を愛するものだ。人が赤ん坊や犬や猫を可愛く思う理由の一つは、自分がそれらより上位であり、余裕をもって接することができるからだろう。だが、政治家においては頭の悪さや常識の無さ、道義心の欠如は最悪の欠点だろう。いくら笑顔が可愛くても赤ん坊を一国の総理や副総理にしておくわけにはいかない。(笑)
(追記)書いたものを今読みなおしたが、「赤ん坊」は不適切だった。それほど無邪気なものではない。多少は人がましくなり、悪ずれした年齢、つまり小学校高学年くらいだろうか。ただし、その中でもかなり質の悪い部類だ。私の知っている小学生の8割までは彼より頭が良く、適切な判断力もあった。
(以下引用)
http://toyokeizai.net/articles/-/16867
麻生氏は、なぜこうも”お粗末”なのか
グローバルエリートが麻生副総理に喝!
ムーギー・キム:プライベートエクイティ投資家2013年8月2日
グローバル化の進展により、国の枠を超えて活躍する「グローバルエリート」が生まれている。しかし、そのリアルな姿はなかなか伝わってこない。グローバルエリートたちは何を考え、何に悩み、どんな日々を送っているのか? 日本生まれの韓国人であり、国際金融マンとして、シンガポール、香港、欧州を舞台に活動する著者が、経済、ビジネス、キャリア、そして、身近な生活ネタを縦横無尽につづる。
数々の失言で、日本の国益を毀損する麻生氏(写真:ロイター/アフロ)
「あちゃちゃ~、おなじみの失言癖、また大炸裂させとる~!!」
私がモスクワから香港に到着したその日の新聞で麻生氏の“憲法改正の手法はナチスに学べるのではないか”という趣旨の妄言で国内外から大きな批判を浴びていた。当然香港のテレビでも日本の再軍備を可能にする“変憲”(改憲、と書くとまるで憲法を良くするかのような語弊がある)の文脈で大きく報道されており、同時にドイツと比較した日本の歴史認識が再度批判されている。
私は麻生さんが別にナチスを賛美しているとは思わないが、発言全部を読んでも憲法改正の手法をナチスに学ぼうと明確に発言しているのは確かだ。また憲法を変えるという重大無比で、本来ならば徹底的な議論と透明性と国民の理解が前提となる作業を、国民の支持が得られないのでこっそり強行できるようにしよう、という恐ろしい意図が感じ取れる。これらの発言に対し「誤解を招いたのなら撤回する」という苦しい釈明は、橋下徹氏の従軍慰安婦発言を“誤解・メディアの誤報”と強弁した不誠実な幕引き方法を髣髴とさせる。
なお橋下氏は麻生氏の発言を擁護するためか、“行き過ぎたジョーク”と言っているが、ナチスの賛美ともとらえられかねないジョークも大問題であり、全然擁護になっておらず失笑を誘った。
そもそも政治家は自分の言葉への責任感が極めて希薄で、失言すれば(もっといえば、一般には知られたくない自分の真意がついうっかり外に出てしまえば)、誤解だとか、メディアの誤報とかで逃げるのがまかり通っているのは残念だ。
多くの新聞やテレビのメディアは追及が甘く、政治家にもおもねて、民意にもおもねるので“おなじみの失言と、撤回で幕引き”みたいな空気と“いつものことだから仕方がない”みたいな不感症を感じるが、来香したてのグローバルエリートが到着直後で眠たい眼をこすりつつ、麻生問題に参戦させていただこう。
麻生さんの長大な”失言の歴史“
さて、麻生さんって、今までどんな“失言”をしてきたっけ?
検索するとあまりにもたくさん情報が出てきてネット回線がパンクするので、急ぎで送らなければならないメールは送った後で、回線パンク覚悟でグーグル検索してみよう。
まず過酷な強制連行で多くの隣国人を徴用しその命を紙クズのように扱い、巨額の利益を上げた麻生炭鉱の麻生さんは(グーグルするとたくさん出てきます)、実家が担った隣国への加害の歴史責任を回避する言動を一貫して続けてきた。この手の精神構造は、東篠家の孫が東篠英機を擁護したり、安倍氏がA級戦犯であった祖父を尊敬したりするのと同じで、親族の罪を公平に直視することが難しく、その正当化に“歴史認識の修正”を使おうとするのは、ある意味理解できる。しかし麻生氏の問題発言の数々は歴史認識だけに限らない。
以前、米価をめぐる問題で“国内外の米価を比較する例えとして「7万8000円と1万6000円はどちらが高いか。アルツハイマーの人でもわかる」と発言し、物議を醸した。かつては同じ自民党の野中広務氏に関し、「野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ」と発言したことでも知られているし、終末医療費負担の増大に対し、「さっさと死ねるようにしてもらうなど、いろいろと考えないと解決しない」と発言。また女性に関しても、「婦人に参政権を与えたのが最大の失敗だった」との発言録がたくさん出てくる。
麻生氏はなぜ権力の中枢に居座り続けられるのか
さすがにこのレベルの暴言が続くと、麻生氏が首相や財務大臣、副総理を歴任するほどの能力や人格を持ち合わせていないのは確度100%のことだと思う。しかしなぜこんな麻生氏があらゆる場面で、権力の中枢に居続けることができるのだろうか。日本は優秀で賢い人格者がいくらでもいる人材大国なだけに、麻生氏に限らず権力者の極めて低い資質は、大変不思議である。やはり利権と支持基盤が世襲される、政界独特の参入障壁のおかげだろうか。
以前、某政府関係者に、麻生氏の適性について聞いてみたところ、「麻生さんは金持ちだというのが確実に影響していて、たとえば1000万円を包んで持ってくる人はたくさんいるだろうが、そういったおカネは絶対に受け取らない」と言っておられたので、金銭問題で足を引っ張られる可能性がないのは一つの強みなのだろう。
また数がモノを言う政治で力が強いのも確かである。安倍政権にとってチームメンバーの資質を問うべき筆頭候補が麻生氏だと思うのだが、安倍氏は泡沫候補だった総裁選で麻生氏のグループなど幅広い政治家の支援を取り付けて票を集めたので、麻生氏がいかに迷惑な存在だったとしても、麻生氏の顔色を窺わなければならない。
たとえば麻生氏のこの発言は安倍氏の悲願である“変憲と再軍備”に冷や水を浴びせるわけだが、麻生氏がすごいのはおそらく周囲に散々失言に気を付けるように言われ続けているだろうに、いまだにメガトン級の失言を繰り返してくれるところだ。
麻生氏の強み、日本社会への付加価値とは何か?
ちなみに麻生氏ならではの貢献や、麻生氏だからこそ社会のためにできることは、「麻生氏が口をつぐむこと」以外に思い浮かばないのだが、麻生氏が政治の中枢に居続けることの日本社会にとっての付加価値は何なのか、まさに“世界ふしぎ発見“モノである。
香港で昼食のディンサムを食べながら考えていた時、いつもながら無愛想な店員の表情を見て思いついたのだが、一つ麻生氏ならではの強みがあるとしたら、“チャーミングな笑顔”でないか。これは石原慎太郎氏とも共通するのだが、言動はめちゃくちゃで国益を毀損する失策をひたすら続けているのだが、笑顔だけはチャーミングなのだ。笑ってる場合じゃないだろう、という気もするのだが、実際の資質や言動への悪印象を和らげるため、笑顔だけは真面目にトレーニングなさったのだろうか。
ただ有権者の皆様におかれましては、見せかけの笑顔や“漫画好き”、べらんめぇ口調などのどうでもいい理由や印象で支持するのではなく、日本を代表する頭脳や品性といったまっとうな理由で政治家を支持していただきたい。どんな理由で判断するかに、自身の知的レベルが反映され、それが選ばれる政治家の知的レベルを決めるのだから。
麻生氏の今回の発言と責任なき幕引きは、実は麻生さん自身の深刻な欠陥を物語るのみならず、なぜ日本ほどの大国に、この程度の政治家しかいないのか、というより本質的な問題を突きつけている。
金持ちでも“天才”でいられる秘訣とは
麻生さんのように金持ちと政治家に囲まれた極めて恵まれた環境に育ちながら、これだけ品と知性がない人物に見えるのは、それはそれで世界ふしぎ発見のネタになるのだが、今回のナチス発言のようにユダヤ人社会や欧米社会からも唾棄されるような失言で国の威信を傷つける麻生氏は、国粋色の強い右派やネトウヨの皆さんからも見放されていいレベルだと思うのだが、いかがだろう。
橋下氏にも共通しているが、自分が話している内容が国際的にどう重大に受け止められるか、というセンスがこれだけ長年政界にいても欠如しているのだから、これはある意味天才である。
経済政策に関しても、セメントで稼がれたご実家の影響だろうか、財政拡大のハナシをなんやらの一つ覚えみたいにしている印象がある。確かに財政拡大で公共投資を高めれば建設業界やセメント会社に国民のお金が移動するので、御周辺のセメント業界は潤うだろうし、ご自身への支持基盤は固められるだろうが、その他への影響に対する深慮遠謀のなさは、ナチス発言に対する浅はかさとの共通点を感じる。
私は人をバカだというのは好きではないし、個人がバカなのは罪ではないが、一国を代表し、指導し、国益を増進する立場にある人間がバカであるのは犯罪だと思っている。
麻生氏は犯罪的失言を直ちにやめ、日本のためにご自身だからこそできる付加価値は何なのか真摯にお考えになられることをお考えいただきたい。そしてその答えが賢明にも私の仮説である“口をつぐむこと”であれば、自主的に恥を知って公職をお退きいただき、秋葉原で漫画を読むなり、ご自宅で漢字を勉強されるなり、ご自由に余生をお楽しみいただきたい。