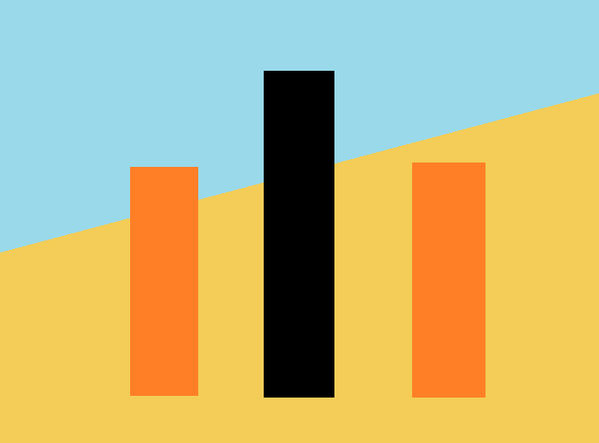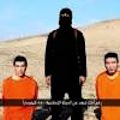© Business Journal 提供
© Business Journal 提供 昨年6月にベネッセホールディングス(HD)会長兼社長に就任した原田泳幸氏が打ち出した構造改革は、ダイレクトメール(DM)に頼らない新しいマーケティング戦略と新規事業の展開だ。700人の配置転換で新規事業に大量の人材を投入する一方、300人の希望退職で社員数を適正化し、販売管理費の削減、高コスト構造の刷新を図り、業績をV字回復させるというシナリオだ。ベネッセグループの正社員は約2万人。退職日は3月末で、特別退職金を支給する。そのため、リストラ関連費用50億円を構造改革費の名目で特別損失として計上している。
さらにベネッセHDは、 1月中をメドに11人の執行役員のうち6人を外部から招く。最高法務責任者(CLO)にパナソニックで情報セキュリティ本部長を務めた金子啓子氏が昨年10月1日に就いたほか、今年1月1日付でマッキンゼー・アンド・カンパニー出身の上田浩太郎氏が最高戦略責任者(CSO)に就任した。最高財務責任者(CFO)は外国人2人を起用する。データベースの保守・運営のために立ち上げる子会社のトップも外部から招聘する。
ベネッセグループ社員が進研ゼミ会員の相談に乗る施設「エリアベネッセ」も開設する。4月までに全国500カ所に設置する予定だ。これまで主力にしてきたDMによる新規会員獲得からエリアベネッセでの営業活動にシフトするという触れ込みだ。グループ各社から700人をエリアベネッセと介護子会社ベネッセスタイルケアに3月末までに移籍させる。今後、グループ各社の人事・経理など間接部門の機能を統合し、900人いる間接部門の人員を450人に半減する。併せて本社やグループ40社の間接部門から300人の希望退職者を募集する。ベネッセHDが希望退職者を募るのは、1955年の創業以来初めてのことだ。
幹部を総入れ替えして、人員を減らし、社員の再配置を行う。ベネッセグループを根底から変えようとする荒療治だ。
昨年12月2日の発表資料には「既にこれまでで最大規模の公募を実施済みで150人が異動、12月付で250人が決定しており、1月までに合計700人の異動を完了する予定」と書いてある。「40歳以上の社員には再就職斡旋のパンフレットが配られている」(ベネッセグループ社員)という。発表文には「転進支援については、希望者に対して期間無制限で行います。これにより社員が自分のキャリアの選択の道をグループ内外に持つことができるように支援します。選択は全て社員の意思に委ね、会社はそのサポートに徹します。退職勧奨はしません」とうたっている。ちなみに昨年7月に発覚した顧客情報流出事件を受け、社内の指名・報酬委員会で役員報酬の引き下げが検討されたが、「原田氏がこれにストップをかけた。2億円以上とされる自らの報酬を下げて、本社社員、グループ会社の社員と痛みを共有する気など原田氏にはない」(ベネッセグループ関係者)という。
●敵を徹底的に攻撃
原田氏が日本マクドナルドHDのCEO(最高経営責任者)に就いたのは2004年5月。米アップルコンピュータ日本法人社長と米本社副社長を兼務していた原田氏は、米マクドナルド本社にヘッドハンティングされた。当時、日本マクドナルドHDは債務超過50億円という、どん底状態にあった。同社の体質を根底からつくり替えるのに、うってつけの人物ということで原田氏は送り込まれた。
「今から新しいバスが出発する。新しいバスのチケットを買いたい人は買え。買いたくない人は乗らなくてかまわない」
原田氏が同社本社の全社員を集めて発した第一声だ。原田氏の経営手法は、味方と敵を明確にして、敵に攻撃を仕掛けるところに特徴があるとされる。原田氏が最大の敵と定めたのは日本法人の創業者で初代社長の藤田田氏だ。原田氏は藤田氏がつくり上げた経営システムと人脈を、ことごとく破壊した。多くの社員の役職を解き、新たな仕事を与えるなどの荒療治に、身内から反発が噴出。「米国の手先、原田の横暴を許すな」と書かれた怪文書まで流れる事態となった。
しかし原田氏はそうした反発をものともせず、フランチャイズ店(FC店)拡大を経営刷新の柱に据えた。直営店をFC店に切り替えることで、3割にも満たなかったFC店比率が7割を超えた。既存の直営店をFC店に転換させるスキームは利益を膨らませる妙案だった。店長がFC店に移籍することで人件費が減る。FC化に伴う店舗売却により利益を計上した。直営店のFC化には、もうひとつの狙いがあった。
原田氏は10年2月、大胆な店舗改革を打ち出した。向こう1年間で全店舗の1割に当たる433店舗を一気に閉鎖。その後、5年以内に633店を集客が見込める立地の良い場所に移転する、というものだった。店舗の大量閉鎖の狙いは創業者の藤田田の子飼いのFC店を一掃することにあった。藤田氏は社員が将来生活していけるように、のれん分けのような制度を取り入れた。その制度を利用して店長たちは独立して、FC店を開いた。社員の独立をマックの増収につなげる、一石二鳥の善政であった。彼らは、一国一城の主に引き上げてくれた藤田氏の信奉者になった。原田氏が脱藤田路線を打ち出した時に最大の抵抗勢力となったのが、こうしたFC店のオーナーたちだった。
●一時的に利益、現場は荒廃
07年11月、FCオーナーの店舗で、サラダの賞味期限偽装事件が起きた。性急なFC化の歪みが出たと原田氏は批判された。事件は原田氏にとって大打撃になるはずだったが、事件を逆手に取った。
「オーナーの中には、ブランドを傷つけることを外に向かって行う人がいる。これまで目をつぶってきたが、時機が到来した。そういう方には撤退してもらいます」
こう宣言し、藤田氏子飼いのFC店を一気に淘汰したのである。経営陣もバスから降ろされた。原田氏の社長就任時代に役員は3回転し、藤田時代の役員はすべて去り、原田氏が外部からスカウトしてきたメンバーも今はまったく残っていない。
原田氏が日本マクドナルドHDで行った構造改革に対しては、「彼は破壊屋であって再生屋ではない。一時的に利益をもたらしたが、現場は荒廃した。マックの今日の窮状はこうして起こった。見せかけの利益を出すために、店舗のリニューアルはしていない。メニューだけでなく店舗が劣化してしまった」(同社関係者)との批判も多い。そのため、原田氏が去った後のベネッセHDも同様に荒れ地になってしまうとの見方もある。
(文=編集部)
(引用2)
原田泳幸
はらだ えいこう 原田 泳幸 | |
|---|---|
| 生誕 | 1948年12月3日(66歳) |
| 出身校 | 東海大学工学部通信工学科 ハーバード・ビジネス・スクール Advanced Management Program |
| 職業 | ベネッセホールディングス代表取締役会長兼社長 ベネッセコーポレーション代表取締役社長 日本マクドナルドホールディングス取締役会長 日本マクドナルド株式会社取締役会長 |
| 配偶者 | 谷村有美 |
原田 泳幸(はらだ えいこう、1948年12月3日[1] - )は、株式会社ベネッセホールディングス代表取締役会長兼社長。株式会社ベネッセコーポレーション代表取締役社長。日本マクドナルドホールディングス株式会社取締役会長兼日本マクドナルド株式会社株式会社取締役会長。ソニー株式会社社外取締役。
来歴[編集]
長崎県佐世保市出身。元アップルコンピュータ株式会社代表取締役社長兼米国アップルコンピュータ社副社長[1]。妻はシンガーソングライターの谷村有美。2005年6月から「原田泳幸」を自称(それ以前は「原田永幸」。戸籍上の名前も永幸のまま)。 マクドナルドから社長として迎えるという打診があり、マクドナルドからヘッドハンティングされた事で、Macintoshの略称・愛称「マック」から、「原田氏、マックからマックへ転身」等と報道された。
2009年、GQ MEN OF THE YEAR 2009を受賞[2]。
毎朝約10キロ走るなど、ランニングを趣味としている。東京マラソンに2011年から3回連続で参加し、ベストタイムは2012年の4時間2分。
2013年6月に、ソニーとベネッセホールディングスの社外取締役に就任した。
2013年8月27日付けで日本マクドナルド(事業会社)の社長をサラ・カサノバに譲り、原田は持ち株会社である日本マクドナルドホールディングスの会長兼社長と事業会社の会長に留まった[3]。また、2014年3月25日にサラ・カサノバが日本マクドナルドホールディングスの社長に就任したため[4]、原田は両企業の代表権を持たない会長になった[5]。
2014年6月21日、前年から社外取締役として在任しているベネッセホールディングスの代表取締役会長兼社長に就任した[6][7][8]。
2014年6月下旬、ベネッセHD代表取締役会長兼社長として就任直後に、2000万件余の個人情報が漏えいしたベネッセ個人情報流出事件が発覚した[9]。流出を公表した7月9日の会見では、金銭的な謝罪を考えていないことを強調するとともに、流出情報を利用した他の通信教育会社の倫理を問う発言を繰り返したが[10]、同17日の会見では報道陣から「ベネッセは被害者か加害者か、どちらなのか」との辛辣な質問が飛び、「これだけ迷惑をおかけしたという意味では、加害者と思っている」と述べたほか[11]、一転して200億円の原資を用意して金銭補償する方針を表明するなど対応が揺れた[10]。また同年7月下旬には、古巣である日本マクドナルドのナゲットに使用されている、中国からの肉の中に賞味期限切れが使われていることも発覚した[12]。
同年10月1日から、グループ全体の変革とベネッセコーポレーションの変革を一体的に進めるため、同社代表取締役社長も兼任する[13][14]。
マクドナルド経営[編集]
2004年より、日本マクドナルドCEOとなる。前任の創業者社長である藤田田が進めてきたバリュー戦略の見直しを次々に打ち出し、行き過ぎた安売りで失墜したマクドナルドのブランドイメージの建て直しに奔走、短期間で建て直した[15]。その経営手腕の評価から、2009年12月に「GQ Men of the Year 2009」の一人に選ばれ、2011年10月には日本経団連の関連組織である経済広報センターより「企業広報経営者賞」を受賞した。
2012年10月1日から「待ち時間の短縮のため」として実施したレジカウンターにおけるメニュー表の撤廃について、「利用者のことを考えておらず、不便になっただけである」という意見もあったが[16]、価格はわかっている人の意見として問題はないという意見もあった[17]。また、2013年1月4日から60秒で商品を提供できなかったら無料券を渡すというキャンペーンを実施し、「店員が時間制限に焦り、バーガーの形が崩れている」という報告もネット上にあったが[18]、「面白い試み」という意見もあった[19]。2013年7月に、1日限定・数量限定で単品1000円のハンバーガー「クォーターパウンダージュエリー」を販売。マクドナルド史上一番高い価格であった。
上述のようなマーケティング改革などに辣腕を振るったが、その一方で、行きすぎたFC化が弊害も生み[20]、訴訟に発展した他、幹部級の人材の流出も相次ぐなどして[15]、2013年11月第3四半期累計(1 - 9月)の連結経常利益は前年同期比39.1%減の108億円に落ち込み、通期計画の195億円に対する進捗率は55.6%にとどまり、5年平均の75.8%も下回った[21]。このような状況から同社が強みとしていた現場力も低下し、12年12月期以降の業績続落の原因となったとも指摘されている[22]。CEOを辞した直後の2014年にマクドナルドは初の170億円、11年ぶりの赤字決算となった[23]。
また、大量のリストラを行ったことでも知られる。リストラは幹部だけでなく、現場の社員も対象となり、4段階あり、上から2番目という平均的な評価を得ている人の中でダーゲットを決めて、一気に評価を一番下にして、自主退社を促していたとされる[24]。
学歴[編集]
- 1968年 - 長崎県立佐世保南高等学校卒業
- 1972年 - 東海大学工学部通信工学科卒業[1]
- 1995年 - ハーバード・ビジネス・スクール Advanced Management Program修了[1]
職歴[編集]
- 1972年 - 日本NCR(株)入社[1]
- 1980年 - 横河ヒューレット・パッカード(株)入社[1]
- 1983年 - シュルンベルジェ・グループ入社 取締役マーケティング部長、取締役ATE事業部長[1]
- 1990年 - アップルコンピュータ・ジャパン(株)(当時)入社 マーケティング部長[1]
- 1993年 - 同社 ビジネスマーケット事業部長 兼 マーケティング本部長就任[1]
- 1994年 - 同社 取締役マーケティング本部長就任[1]
- 1996年 - 米国アップルコンピュータ社 ワールドワイドコンシューマーマーケティング/SOHO担当バイス・プレジデント就任(米国本社勤務)
- 1997年 - アップルコンピュータ(株)代表取締役社長兼米国アップルコンピュータ社副社長就任
- 2004年 - 日本マクドナルドホールディングス(株)、日本マクドナルド(株)取締役副会長兼社長兼最高経営責任者 (CEO) 就任
- 2005年 - 日本マクドナルドホールディングス(株)、日本マクドナルド(株)代表取締役会長就任、社長及びCEO兼任
- 2013年 - ソニー(株)、(株)ベネッセホールディングス 社外取締役就任
- 2013年 - 日本マクドナルド(株)の代表権及び社長兼CEOを退任し、代表権のない取締役会長に就任(現職)
- 2014年 - 日本マクドナルドホールディングス(株)の代表権及び社長兼CEOを退任し、代表権のない取締役会長に就任(現職)
- 2014年 - (株)ベネッセホールディングス代表取締役会長兼社長、及び国内教育カンパニー長就任(現職)
- 2014年 - (株)ベネッセコーポレーション代表取締役社長就任(現職)