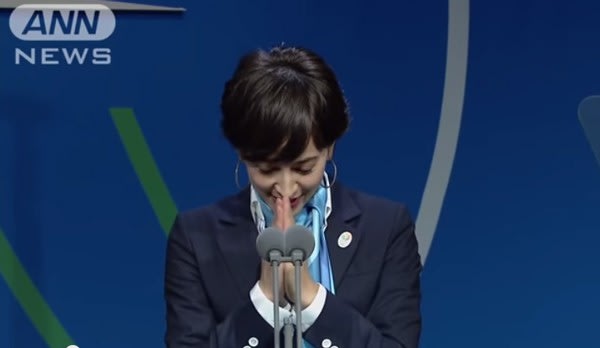日本の迅速な降伏をもたらし、太平洋戦争を終わらせる為、原子爆弾の広島と長崎への投下についての、もっともらしい軍事的必要性を、たとえ受け入れたにせよ、無警告空爆を受けた二都市における一般市民死亡者数の恐怖は、「目的の達成は手段を正当化する」とされるものに関する気掛かりな疑問を思いおこさせる。
だが、もし、アメリカのハリー・トルーマン大統領や彼の政権が喧伝した公式の軍事的論拠が、でっちあげであることが分かったらどうだろう? つまり、70年前の1945年8月6日と9日、広島と長崎に原子爆弾を投下した本当の理由が、大日本帝国を打ち破り、アメリカ軍兵士の命を救うこととほとんど関係がなかったら? 本当の理由が、アメリカによる戦後の世界覇権画定をソ連に警告する為の、ワシントンによる、計画的かつ冷酷な、むき出しの軍事力の実演だったとしたらどうだろう?
そうなれば、アメリカ公式説明が我々に信じ込ませようとしてきた結論より、遥かに酷い、極めて恐ろしい結論に到ることになる。なぜなら、それは、200,000人もの日本人一般市民を絶滅させる行為が、ひたすら政治的な狙いの周到に準備された大量虐殺事件であることを意味するからだ。あるいは言い換えれば、アメリカ合州国がおかした言語に絶する国家テロ行為だ。
アメリカによる対日本原子爆弾投下の本当の狙いに関して長年憶測がされてきた。1995年1月、ニューヨーク・タイムズはこう報じた。“実際、歴史学者達の中には、原爆投下は、戦時の敵日本を狙ったものというより、戦時の同盟国ソ連を狙って、戦後の対立関係に対する警告として行われたのだと主張する人々がいる”。
無頓着な曖昧な表現で、ニューヨーク・タイムズは、一体なぜ原子爆弾が投下されたのかについて、自ら一部認めた身の毛もよだつ意味あいを徹底的に追求することはしなかった。もし公式のアメリカの計算が、実際、ソ連に対する“戦後の対立関係に対する警告”だったならば、行為は、速やかに戦争を終わらせるという道徳的要請とは無関係な、弁解の余地のない政治的決断となる。それは上述の通り、究極のテロ行為だったことになる。
ガー・アルペロビッツ教授は、トルーマン政権は、実際 ソ連に対する政治的兵器として、原子爆弾を使用する決断をしたのだという説得力のある主張を、何十年間もかけて、まとめ上げたアメリカ人歴史学者の一人だ。
‘原子爆弾使用の決定’の筆者は、こう書いている。“大半のアメリカ国民は、事実を知らずにいるが、益々多くの歴史学者が、今や、アメリカ合州国は、1945年に日本に対する戦争を終わらせる為に、原子爆弾を使用する必要はなかったことを認識している。しかも、この根本的判断を、陸軍、海軍と、陸軍航空隊、三軍すべてのアメリカ軍部幹部指導者達の圧倒的多数が、戦争が終わった後、長年表明してきた”。
当時のアメリカ陸軍大臣ヘンリー・L・スティムソンや、ドワイト・アイゼンハワー将軍や、統合参謀本部のウィリアム・D・リーヒ提督等の軍指導者達は、日本に対する原子爆弾の使用に、はっきりと反対していたことをアルペロビッツはあげている。アイゼンハワーは、それは”全く不必要”だと述べる一方、リーヒこう言っていた。“広島と長崎におけるこの残酷な兵器の使用は、日本に対する我々の戦争において何の物質的支援にもならなかった。日本は既に敗北し、降伏しようとしている”。
これは、極めて重要なポツダム会談(1945年7月17日-8月2日)から、日本への原子爆弾投下までの三週間における、秘密の政治的意思決定を暗示している。その期間中に、トルーマンと側近達は、秘密裏に、当時は戦争同盟国だったソ連を、これ以降、戦後の、敵にすると決めた様に思われる。冷戦が形成されつつあったのだ。
ポツダム会談前の何カ月もの間、アメリカとイギリスが、ロシア指導者ヨセフ・スターリンに、ナチス・ドイツ打倒後、すぐに太平洋戦争に参戦するよう訴えていたことを銘記しよう。第三帝国が、1945年5月に打ち負かされてから、二カ月後、三大連合国間のポツダム会談で、赤軍を日本に向けて移転させるという、スターリンによる待望の確約を勝ち取った。ソ連は、8月15日に、太平洋戦争に公式に参戦する予定だった。後で分かったことだが、スターリンは予定されていた攻勢より一週間早く8月8日に、赤軍に満州進撃を命じていた。
ポツダム会談中に、ハリー・トルーマンが私信で上機嫌で書いた通り、ソ連のこの約束は“ジャップは、おしまいである”ことを意味していた。
ところが、ポツダム会談開始のわずか一日前、7月16日のニュー・メキシコ州の砂漠における、アメリカ合州国による最初の原子爆弾実験成功は、引き返し限界点だった。このすさまじい新兵器で、ソ連の太平洋戦域への参戦無しに、原子爆弾投下によって、対日戦争を終わらせられることを、アメリカの立案者達は速やかに理解したに違いない。
しかし、アメリカの主要目的は、太平洋戦争それ自体を終わらせることではなかった。アメリカとイギリス軍幹部と諜報部隊は、ロシアが対日戦争に参戦するだけで、日本の降伏を促進するだろうと確信していた。しかも、アメリカの日本本土上陸は、1945年11月まで実施しない予定だった。
当時、アジア-太平洋におけるソ連のいかなる前進を制限することが、この政権の懸念だったので、トルーマン政権が日本に対する新たな核兵器使用を急いでいたことは明らかに思える。赤軍は満州と朝鮮半島のみならず、日本本土をも占領しようとしていた。
軍事的価値の無い、二つの大都市、広島と長崎は、かくして、完膚無きまで打ちのめされていた日本に対してではなく、ソ連に対する、最もうっとりとするようなテロ行為を実演する現場として選ばれたのだ。日本への原爆投下は、それゆえ、アメリカの公式説明が主張するように、太平洋戦争の最後の行為ではなく、むしろ、発生期冷戦における、ソ連に対する、アメリカによる最初の残虐行為だったのだ。
これにより、恐ろしい出来事の、全く違う犯罪的側面を明らかにすることになる。原子爆弾攻撃は、地政学的ライバルとなる恐れがあるモスクワを恫喝するというひたすら戦略的な理由による意図的な大量虐殺行為と見なすことができるためだ。
70年後、アメリカ支配エリートのこの残酷な論理が、いまだに続いていることを、歴史が示している。ほぼ四半世紀前に冷戦が公式に終焉した後も、ワシントンが、核兵器備蓄を捨てる意図は明らかに皆無だ。実際、バラク・オバマ大統領の下で、アメリカ政府は、それぞれが、最初に日本に投下された原子爆弾の何倍も強力な、約5,000発の核弾頭備蓄の性能を高める為に、今後十年間で、3550億ドルを費やす予定だ。
しかも、ワシントンは、つい今月ペンタゴン幹部を通して、ロシアと中国は戦略上最高の敵だと公式に宣言した。
2002年の、弾道弾迎撃ミサイル制限条約からのアメリカの一方的離脱と、続行しているアメリカ・ミサイル・システムのロシア国境と太平洋への拡張と、中国に対する挑発的な言辞は、ワシントンに内在する生来の好戦的意図の証明だ。
70年前の最初で、しかもたった一度の核兵器使用で、広島と長崎でのホロコーストを引き起こしたアメリカの論理は、今日まで続く残虐な論理だ。核兵器は、70年前と同様、いまだにロシアに向けられている。
平和な国際関係は、このアメリカ独自の残酷な論理を完全に暴き出し、根絶することによってしか実現されまい。
Strategic Culture Foundation
記事原文のurl:http://www.strategic-culture.org/news/2015/08/02/america-barbaric-logic-hiroshima-70-years-on.html
(引用2「酔生夢人のブログ」所載「高校生のための『現代世界』4」より)
1943年、イタリアは降伏し、45年5月にドイツも降伏し、日本の降伏も目前になってきた同年8月、アメリカは日本に原爆を投下します。この行為は、今にもノックアウト負け寸前のボクサーの頭をピストルで打ち抜くような残虐な、そして表面的には無意味な行為であり、その真意は、新しく発明された原爆の威力を実験することにありました。原爆の威力はすでに予測されていましたが、それを世界に知らしめるためには、実際の戦争でそれを使ってみせる必要があったのです。それが戦後のアメリカの世界経営にとって必要だという判断によるものでしょう。さすがに、白人の国を相手には原爆を使うことはできなかったので、東洋の猿どもを相手にためしてみようということです。では、なぜ東京ではなく地方都市がその対象として選ばれたか。それは、たとえ敵国でも、そのエスタブリッシュメント(支配層)まで絶滅させた場合、それが歴史的な先例となり、自分たちが別の機会に同じことをされる可能性があるからでしょう。あるいは、政治経済的支配層やその配下を残しておいたほうが、占領後に彼らを自分の手足として使うことができるという計算かもしれません。あるいは、東京のお偉方とアメリカのお偉方の間に秘密の約束があったのかもしれません。どうせなら、東京に原爆を落としてくれていたほうが、日本を悲惨な戦争に追いやった張本人たちが掃除されて、日本はもっと良くなっていたかもしれませんが。