「逝きし世の面影」記事のコメント欄に管理人の宗純氏自身が書いていた
「政治ブログの質も致命的に低いが、もっとひどいのは反原発に特化したブログで、最後の最後のここにきて、にわかに怖気づく。
必死で押さえにかかってるのですね。
木下黄太のブログ が特にひどい。いまでは丸々が原子力ムラの隠れ村民の偽装工作ですね。しかも大勢を騙しているのですから罪が深い。」
という部分が興味を引いたので、木下黄太のツィッター(ブログは読んだことがない。文章が面白くなさそうだから。もっとも、彼は「反原発活動家」であり、「面白い文章」を書くことがブログの目的ではないのだろうが。)を久しぶりに読むと、(引用2)のツィートがあり、それでもう興味を失った。
「反原発活動家」なら、自分の主張を多くの人が拡散してくれることを望み、感謝すべきはずではないか。こういう姿勢では「反原発商売人」でしかない、と私は思う。反原発も売名行為にすぎなかったのではないか。そういう意味では「きっこのブログ」も同様である。社会改善(政治批判)めいた意見をあれこれ書きながら、「無断引用禁止」としているブログは、私は一切信用しない。
なお、アフィリエイトというのか、企業コマーシャルをやたらに入れているブログも同様である。
(引用1)
2015-12-06 15:43:46ネプギアソリッドさん、古西さん、こうじかびさん、
皆さん、コメント有難うございます。
これは駄目ですね。もう完全に終わっています。
マスコミですが、フクシマの真実を報道する気が最初から少しもない。
多分子供たちの命や健康よりも、『一般市民がパニックを起こさない』こと(治安対策)を最優先しているのですよ。
韓国旅客船セウォル号と同じ状態に陥った今の日本ですが、完全に沈没しない限り、目が覚めない。
マスコミが駄目でもネットが活躍すれば良いのだが、・・・均質構造の日本では事情が同じ、
グーグルの『政治』 ジャンルのランキングで取り上げているのは、この『逝きし世の面影』だけですよ。
政治ブログなのに、政治的な判断ができないのですから無茶苦茶。
騙す方と騙される方の二者がいるのではなくて、双方馴れ合いの共存関係なのでしょうか。
醜い真実よりも、美しい嘘を信じたいのですが、これでは助かるものでも助からない。
政治ブログの質も致命的に低いが、もっとひどいのは反原発に特化したブログで、最後の最後のここにきて、にわかに怖気づく。
必死で押さえにかかってるのですね。
木下黄太のブログ が特にひどい。いまでは丸々が原子力ムラの隠れ村民の偽装工作ですね。しかも大勢を騙しているのですから罪が深い。
元々が悪質な原子力ムラの偽装ブログだったのか、それとも、その結果の恐ろしさに気が付いたので、薄めようと必死になっているのかは不明だが、救いようのない低能の悪党であることだけは間違いないでしょう。
いよいよ最後のカタストロフィは目の前であり、ほんの少しの時間が残されているだけ。ここまで深刻化すれば、今までのような先送りは無理でしょう。
(引用2)
木下黄太 @KinositaKouta 






 岸本元
岸本元 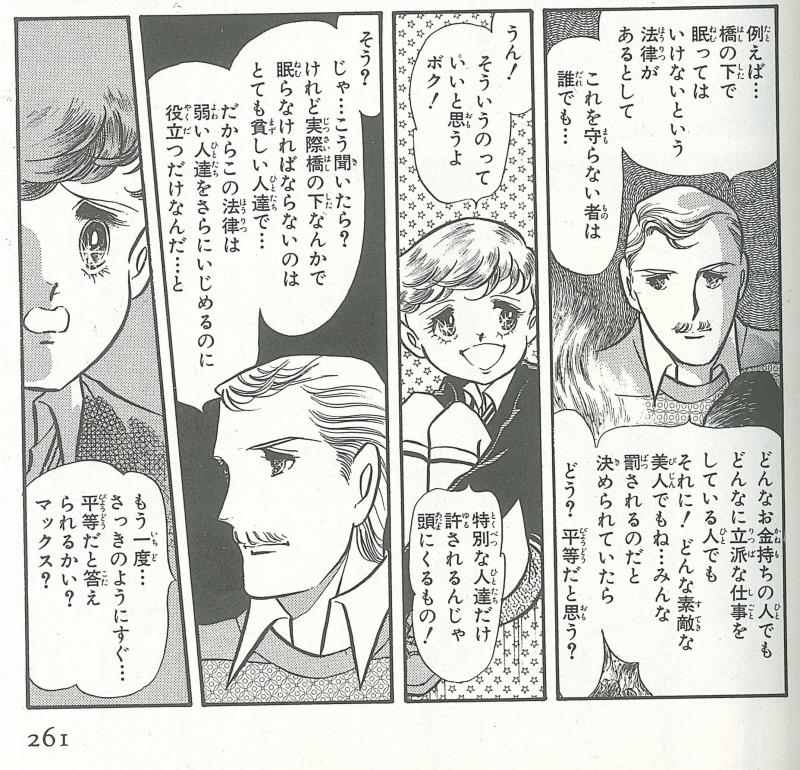
終末のタンゴ
どんな人間にも必ず終わりは来る
どんな世の中にも必ず終わりは来る。
美しい人も勇ましい人も、うけてない人もいつかは来る。
その日のために鍛えておこう。
君の覚悟のすべてを、自殺、圧殺、虐殺。
どんな愛情にも必ず終わりは来る。
どんな恍惚にも必ず終わりは来る。
大きい人も、短い人も、しつこい人もいつかは果てる。
その日のために鍛えておこう。
君の覚悟のすべてを、腹筋、海綿体、括約筋。
どんな犯罪にも必ず終わりは来る。
どんなインチキにも必ず終わりは来る。
信じた人も、夢見る人も、飲み過ぎた人もいつかは覚める。
その日のために鍛えておこう。
君の覚悟のすべてを、誤算、破産、倒産。
南無三。
https://www.youtube.com/watch?v=M2nTsblH6NU
最後にいいこと言ってます。
昭和の男でしたね。ご冥福をお祈りします。
ご冥福をお祈りします。
行った先が神様か仏様か地獄の鬼かしらんけど、ホッペタ殴ったりしないようにねw
「野坂昭如が壇上で祝辞を述べた後に大島監督に右フックを食らわせる。」
https://www.youtube.com/watch?v=n1CNy0eIzuY&feature=related
不思議な人だった
http://blog.goo.ne.jp/mardinho/e/745f2573dab355378b3968c5d9872ba6
野坂さんの小説で「オペレーションノア」てのがあって、読んだのは、若いころ
だったんですが、まるで今の日本を予見したような内容で、思い返すと寒気がします。
http://saint-maybe.cocolog-nifty.com/inevitable_tourist/2010/01/post-d29b.html
現在は絶版本だったかも。
つ~か 野坂さんは政治家やパワーエリートてのが、どれほど傲慢なバカなのかを
よく知ってたんだろな。
野坂さん 昔 「TVタックル」でオナニーしろとか言ってたから、
たぶん今頃は、あっちで大島渚とド突き合いながら、酒をチビチビ飲みつつ
オナニーしてると思う。 あ~でも仏様になると煩悩が無くなるのか
なんにしても野坂さん ご苦労様でした。
youtubeに野坂昭如がヤグザの組事務所を取材する映像があるけど、中々味わい深くて面白い。