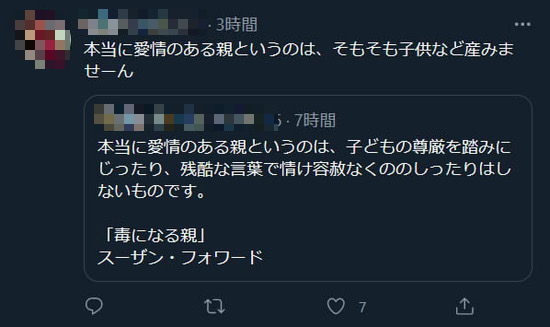安倍氏銃撃に関し漫画家の小林よしのり氏が語る
戦後初となる総理大臣経験者の暗殺事件がニッポン社会を大きく揺るがしている。なぜ悲劇が起きたのか、漫画家の小林よしのり氏が分析する。
* * *
事件の映像を見ると、犯人がマスクをしている。顔の表情に見える挙動不審感をSPも見抜けなかったのかもしれない。
マスクをしていたら、口元がニヤついているのか、緊張でこわばっているのかも分からない。目つきで分かるといったって、表情はそれぞれのパーツの連動や全体のバランスで把握するものであって、目だけ出ていたところで、睨みつけているかどうかだって分かりはしないだろう。
しかも、数多くいる聴衆がみんなマスク姿だ。誰が怪しいか、目星をつけるのは難しいに違いない。
わしは「ゴー宣道場」というイベントをやっているが、聴衆はそこではマスクをしていないので、全体を見渡せば顔の表情でだいたい警戒度が分かる。わしを睨みつけるように見ている者がいれば、反発した感情を抱いているのかもしれないと気をつけるようにするし、警備の者たちもそれとなく警戒するようになる。
マスクという覆面は、犯人にある種の自信を与えたことだろう。半分顔を覆うことで、本心を覆い隠し、周囲に溶け込めているという安心感があったはずだ。顔が出ていればそうはいかない。表情からバレるんじゃないかとビクビクしていたかもしれない。
かつては顔を覆いたくても、誰もマスクなんかしていないから目立ってしまった。今は逆だ。マスクをしてさえいれば群衆に溶け込める。マスクが犯人を助けたのだ。
ソーシャルディスタンスというものの問題点もある。犯人が撃った5メートルは「至近距離」だと報じられたが、コロナ禍で言われるソーシャルディスタンスは保ったことになる。我々は、杓子定規な距離の取り方を覚えたことで、臨機応変に間合いを感じて対応する術を失ってしまったのかもしれない。
コロナが与えた社会的変化が、事件に与えた影響は案外大きいように思う。つまり、マスクはコロナウイルスも完全には防げないし、テロも防げないということだ。
マスクが日本をおかしくしていることに、いいかげんみんな気付いたらどうだ。
※週刊ポスト2022年7月29日号