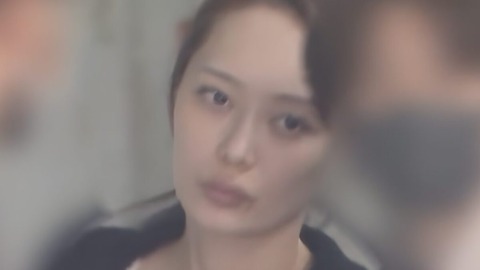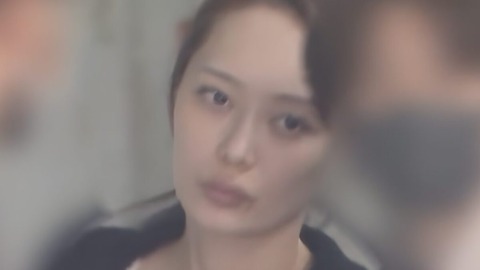
当時、ホテル内で2人がトラブルになったため、警察官が駆けつけていて部屋の中を調べたところ、ベッド付近でコカインや覚醒剤が入った袋が3つ見つかったということです。


気の赴くままにつれづれと。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
俳諧(はいかい)とは、主に江戸時代に栄えた日本文学の形式、また、その作品のこと。誹諧とも表記する。正しくは俳諧の連歌あるいは俳諧連歌と呼び、正統の連歌から分岐して、遊戯性を高めた集団文芸であり、発句や連句といった形式の総称である。
松尾芭蕉の登場により冒頭の発句の独立性が高まり、発句のみを鑑賞する事も多く行われるようになり、明治時代に成立した俳句の源流となる。時に作者個人の創作たる発句を完全に独立させた近代文芸の俳句と同一視される。専門的に俳諧に携わるひとを「俳諧師」と呼ぶ。江戸期では専業のいわゆる「業俳」が俳諧師と呼ばれていた。本業があって趣味として俳諧を楽しむ人は「遊俳」と呼ばれ、遊俳は俳諧師とは呼ばれない。
「俳諧」とは本来、滑稽と同意の戯れをさす漢語であった。佐藤勝明によれば、和歌は「(5+7)N+7(Nは任意の自然数)」と表せ、N=1が片歌、N=2が短歌、N≧3が長歌となる[1]。やがて、5・7を組み合わせる短歌が主流になると、575/77の上句と下句の対応に関心が寄せられ、上句と下句を2人で分担して詠む連歌が流行する。初期の連歌は、対話的で機知的な笑いを伴うもので、「俳諧之連歌」と呼称された[1]。連歌が流行するにつれて、2句だけの短連歌だったのが、次第に長句(5・7・5)と短句(7・7)をつなげて一定数を続ける長連歌へと変化する[1]。その後、幽玄・さび・ひえを重視する和歌的連歌(有心連歌)と連歌本来の機知的滑稽を残す俳諧連歌(無心連歌)に二分される[2]。
山崎宗鑑が俳諧連歌集の祖となる『犬筑波集(俳諧之連歌抄)』を編纂し、また、宗鑑と並び俳諧の祖と評される荒木田守武が『俳諧独吟百韻』等の俳諧集を編んだ頃から、俳諧連歌への関心が高まった。
江戸時代になると、識字率の向上や学習意欲の高まりに伴って、庶民が文化の担い手となり、俳諧連歌は人気を博す[1]。松永貞徳の貞門派や西山宗因の談林派、俳諧の新たな表現を模索する天和調といった流行が生じた後、松尾芭蕉の蕉風と呼ばれる作風が生まれた[1]。和歌や連歌が日常的な世界(俗)ではなく、貴族的・古典的な世界(雅)の文芸として大成したのに対して、芭蕉は俗な世界を扱いながら和歌や連歌に匹敵する作品を示そうと試みたのである[1]。
芭蕉没後、俳壇は宝井其角、水間沾徳らの都市型俳諧と、各務支考、志太野坡らの地方農村型俳諧に分化する一方、雑俳の流行が顕著に見られる[2]。洒落風・化鳥風・蕉風再興といった動きの中で、与謝蕪村、小林一茶といった俳諧師が活躍した[2]。だが、俳諧を嗜む人口が増えるにつれて、俳諧は徐々に趣味化していき、表現や内容が平淡になっていく[2]。
明治時代になると、正岡子規によって、俳諧は月並俳諧として批判の対象となり「発句は文学なり。連俳は文学に非ず」と断じられた[2]。これ以降、俳諧の発句が俳句と称され、伝統的な俳諧は連句と呼ばれるようになった[2]。
俳諧を文芸ジャンルとして用いる場合、発句や連句はもちろん、前句付などの雑俳や俳文、漢詩の形式を模した和詩や仮名詩が含まれる。俳諧は座の文芸とされ、宗匠・執筆(しゅひつ)・連衆で構成される一座の共同体、連衆の作句活動、宗匠の捌きによって、作品の成否と出来栄えが決定する[2]。
the********さん
国立大学の元教員です。 大学の首席というのはあり得ません。だって学部ごとに 卒業要件も異なりますからです。基準が違う人達の中か らトップを選ぶことはできません。同じ理由で学部の 首席もあり得ません。学科ごとに教育内容と卒業要件 が違うからです。 あり得るとすれば,学科の首席。でも,多くの大学では 席次は公表しませんから,わからないのが原則でしょう。 では,卒業式で工学部の総代になって学長から学位記を もらう人はどうやって決めているか。僕の勤めていた 大学工学部では,機械・土木・化学・バイオ・建築・ 電気・・・など,例えば8個くらいの学科で順番を 回しています。今年は機械,来年は土木,再来年は 化学といった具合です。ですから学部の首席ではあり 得ません。今年は機械が担当で総代だったとき,その 総代は機械科の首席か?というと,それもそうとは 限らない。学科ごとに選び方はバラバラだからです。 もしかしたら機械科には三つのコースがあったりす ると機械科首席も定義できないわけですからね。 というわけです。首席が成績優秀者とも限らない。 その学部トップとも限らない,その学科トップとも 限らない・・・その学科でたまたま選ばれた人が 総代をつとめ,首席はいないというのが,僕が勤め た大学工学部の実態です。
ここまでは序段であって、ここでの目的はーーある意図があってーー中井久夫の名エッセイ「いじめの政治学」をやや長く掲げることである(ある意図とはエアリプとしてもよい)。 |
長らくいじめは日本特有の現象であるかと思われていた。私はある時、アメリカのその方の専門家に聞いてみたら、いじめbullyingはむろんありすぎるほどあるので、こちらでは学校の中の本物のギャングが問題だという返事であった。学校に銃を持ってくるなということを注意し、実際に校門で検査しているのが一部高校の実情である。こうなっては大変であるが、銃はともかく、日本でもいじめ側の一部がギャング化しているのは高額の金員を搾取していることから察せられる。 外国では、英国のエリート学校であるいくつかのパブリック・スクールのいじめがよく知られている。英国の数学者・哲学者バートランド・ラッセルの自伝にもケンブリッジ大学への準備に通っていた学校で、これは高級軍人コースのための予備校であったからなおさらであったが、毎日いじめられては夕陽に向かって歩いていって自殺を考え「もう少し数学を知ってから死のう」と思い返す段がある。〔・・・〕 いじめは、その時その場での効果だけでなく、生涯にわたってその人の行動に影響を与えるものである。殺人は犯罪であって、軍人が戦場に臨んだ時にだけ犯罪でなくなることはよく知られている。いじめのかなりの部分は、学校という場でなければ立派に犯罪を構成する。そして、かつて兵営における下級兵いじめが治外法権のもとにおかれたような意味で学校が法の外にあるように思われるのは多くの人が共有している錯覚である。〔・・・〕 |
いじめといじめでないものとの間にはっきり一線を引いておく必要がある。冗談やからかいやふざけやたわむれが一切いじめなのではない。いじめでないかどうかを見分けるもっとも簡単な基準は、そこに相互性があるかどうかである。鬼ごっこを取り上げてみよう。鬼がジャンケンか何かのルールに従って交替するのが普通の鬼ごっこである。もし鬼が誰それと最初から決められていれば、それはいじめである。荷物を持ち合うにも、使い走りでさえも、相互性があればよく、なければいじめである。 鬼ごっこでは、いじめ型になると面白くなくなるはずだが、その代わり増大するのは一部の者にとっては権力感である。多数の者にとっては犠牲者にならなくてよかったという安心感である。多くの者は権力側につくことのよさをそこで学ぶ。 子どもの社会は権力社会であるという側面を持つ。子どもは家族や社会の中で権力を持てないだけ、いっそう権力に飢えている。子どもが家族の中で権利を制限され、権力を振るわれていることが大きければ大きいほど、子どもの飢えは増大する。 |
いじめる側の子どもにかんする研究は少ない。彼らが研究に登場するのは、家族の中で暴力を振るわれている場合である。あるいは発言したくても発言権がなくて、無力感にさいなまれている場合である。たとえば、どれだけ多くの子どもが家庭にあって、父母あるいは嫁姑の確執に対して一言いいたくて、しかしいえなくて身悶えする思いでいることか。 そういう子どもが皆いじめ側になるわけではない。いじめられる側にまわることが多く、その結果、神経症になるほうが多いだろう。最近、入院患者の病歴をとっていると、うんざりするほどいじめられ体験が多い。また、何らかの形でいじめを克服して、それが職業選択を左右しているかもしれない。もう二十年前になるが、私が精神科医仲間にそれとなく聞いてまわったところでは(私も含めてーー私は堂々たるいじめられっ子である)圧倒的にいじめられっ子出身が多かったが、一人の精神科医はいじめ側であったといい、何人も登校拒否児を作ったから罪のつぐないに子どもを診ているのだと語った。 |
しかし、いじめ方を教える塾があるわけではない。いじめ側の手口を観察していると、家庭でのいじめ、たとえば配偶者同士、嫁姑、親と年長のきょうだいのいじめ、いじめあいから学んだものが実に多い。方法だけでなく、脅かす表情や殺し文句もである。そして言うを憚ることだが、一部教師の態度からも学んでいる。一部の家庭と学校とは懇切丁寧にいじめを教える学校である。〔・・・〕 |
権力欲とはどういうものであろうか。人間にはさまざまな欲望がある。仏教をはじめ、多くの宗教は欲望をどうするかという問題と取り組んできた。しかし欲望の中には睡眠欲もあって、これは一人で満足でき、他に迷惑をかけない。食欲も基本的には同じであるが、他人の食を意識的に奪う場合もあり、知らず知らずの間に奪う場合もあり、他の生命を犠牲にすることは避けられなくて、睡眠欲ほど無邪気ではない。 情欲となると、これは基本的には二人の間の問題であり、必ずしも自分の思いどおりにならず、睡眠や食事よりも自分の中に葛藤を起こすことも少なくない。しかし、権力欲ばこれらとは比較にならないほど多くの人間、実際上無際限に多数の人を巻き込んで上限がない。その快感は思いどおりにならないはずのものを思いどおりにするところにある。自己の中の葛藤は、これに直面する代わりに、より大きい権力を獲得してからにすればきっと解決しやすくなるだろう、いやその必要さえなくなるかもしれないと思いがちであり、さらなる権力の追求という形で先延べできる。このように無際限に追求してしまうということは、「これでよい」という満足点がないということであり、権力欲には真の満足がないことを示している。権力欲には他の欲望と異なって真の快はない。そして『淮南子』にいう「それ物みな足らざるところあればすなわち鳴る」である。〔・・・〕 |
非常に多くのものが権力欲の道具になりうる。教育も治療も介護も布教もーー。多くの宗教がこれまで権力欲を最大の煩悩としてこなかったとすれば、これは不思議である。むろん権力欲自体を消滅させることはできない。その制御が問題であるが、個人、家庭から国家、国際社会まで、人類は権力欲をコントロールする道筋を見いだしているとはいいがたい。差別は純粋に権力欲の問題である。より下位のものがいることを確認するのは自らが支配の梯子を登るよりも楽であり容易であり、また競争とちがって結果が裏目に出ることがまずない。差別された者、抑圧されている者がしばしば差別者になる機微の一つでもある。〔・・・〕 いじめが権力に関係しているからには、必ず政治学がある。子どもにおけるいじめの政治学はなかなか精巧であって、子どもが政治的存在であるという面を持つことを教えてくれる。子ども社会は実に政治化された社会である。すべての大人が政治的社会をまず子どもとして子ども時代に経験することからみれば、少年少女の政治社会のほうが政治社会の原型なのかもしれない。 |
(中井久夫「いじめの政治学」初出1997年『アリアドネからの糸』所収) |