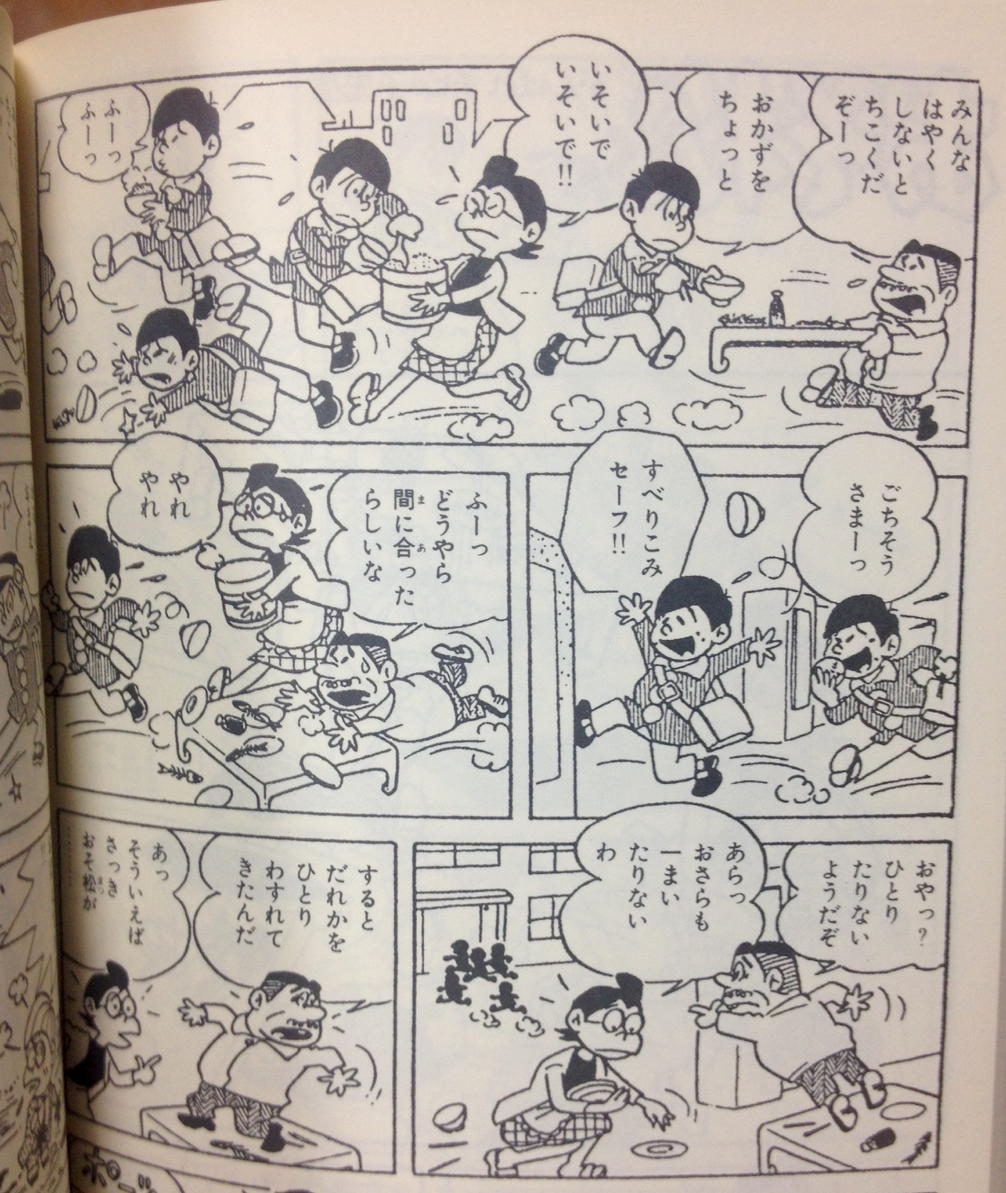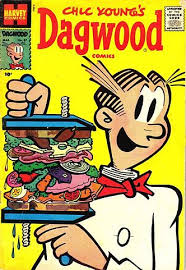世界20カ国の首脳が一堂に会する G20。テロ事件なども警戒されており、
セキュリティも万全だったはずだ。
けれども、そのセキュリティを楽々と突破したのが……ニャンコ!
なんと3匹のネコが、G20 の壇上に何食わぬ顔で登場したというではないか!
その証拠動画を見てみると……あ、本当だ。
会場はざわざわしているものの、
まだ誰もいないステージの裏から2匹のニャンコがひょっこり顔を出した!
もう1匹も、ステージの前方から現れたぞ!!
その後3匹は、しばらくウロチョロ。花の匂いを嗅いだりして、
そそくさと退場したのだった。
お堅い場で動物を見るとなんだか嬉しくなるが、どうやらその心理は世界共通のよう。
なぜなら多くの海外メディアが「G20 の壇上にネコが登場」と報じ、
3: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:27.84 ID:dA3QYUkx0.net
猫に爆弾ついてたらどうすんだ
2: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:33:56.91 ID:2RMjgDXS0.net
テロリストの新装備

4: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:28.48 ID:gWv5Dh1u0.net
キャッツアイ
63: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:41:49.09 ID:f8lYbzzp0.net
>>4
ちょうど三匹ってのがこれまた凄いよな
201: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:02:36.49 ID:l1vDWuX40.net
>>4
心を盗みにきたのか
242: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:13:30.85 ID:eiHMm5a40.net
>>201
キャッツらはとんでもないものを盗んで行きました
5: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:34:34.83 ID:oT0NphYbO.net
ニャ
10: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:35:42.65 ID:3rVdUe0V0.net
ニャロリストだな
23: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:37:27.38 ID:9+5Zd0Vr0.net
テレ東の番組かよ
26: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:01.21 ID:okDuBrzx0.net
とうとう真のG20が
31: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:19.24 ID:VlMd4O5X0.net
バッカモーンそいつがルパンだ追えー!
34: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:38:47.86 ID:Uw8G/8x20.net
全然笑えない
なにほのぼのニュースにしてんだよ
セキュリティの甘さ露呈してんじゃん
38: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:39:15.88 ID:lxncPiLJ0.net
猫に遠隔起動爆弾や盗聴器をぶら下げてたら大変だな
45: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:23.35 ID:m1BujX1v0.net
猫「さあ始めようか」
36: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:39:10.35 ID:kTY1syPt0.net
これでSPが何人か職を失いました
47: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:47.98 ID:HasUNYuY0.net
こんな所に偶然入ってくるか?
50: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:40:55.51 ID:DqPU6rhrO.net
猫の警備員を雇わないから、こんなことになる
91: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:44:21.26 ID:faVhU+oX0.net
3匹はセキュリティーだろ
忙しくて猫の手も借りたいほど(略
92: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:44:39.54 ID:ONkPd6ll0.net
えーっと・・・
和んだけど、結構シャレになってない気が・・・
102: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:45:27.46 ID:9+5Zd0Vr0.net
103: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:45:34.06 ID:t4mPA/+60.net
警備「なんだ猫か」
115: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:47:18.65 ID:zj/Nf/3yO.net
>>103
以外繰り返しであの事態か
警備態勢見直しだよ…
120: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:48:22.11 ID:GmOg/zK70.net
403: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:56:04.23 ID:a11xT7I00.net
>>120
茶猫カワイソス
132: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:50:25.44 ID:zoIfwDle0.net
ネコからしてみれば人間の作り出したセキュリティなんざ突破するのは
造作も無いってことか
160: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:54:34.94 ID:jPM9eZY40.net
誰か首脳の飼い猫だったん?
181: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:59:54.07 ID:LaJhIxOBO.net
>>160
猫の名前
ウラジーミル・プーニャン
バラク・オバニャン
もう一匹は不明
171: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 17:57:31.27 ID:l4GIoEKg0.net
訓練されたカラスが盗聴の実行犯て話がゴルゴ13であったな
214: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:05:47.69 ID:axDD+pzo0.net
こういうヤラセ逆にシラケるわ
261: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:19:10.89 ID:TVR/z1W/0.net
>>214
ヤラセって、あんた
でも、やっぱ視聴率は重要よね
215: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:06:07.07 ID:AIUxUtU40.net
普段は朝方になると公園とかで会議してるけど
場所間違えたんだな
219: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:07:04.30 ID:Z1JdMqHu0.net
軍用犬はいても軍用猫は居ないだろ
まあ、そういう事だ
227: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:09:34.84 ID:eJc4+WgF0.net
テロリストにヒント与えちゃったな
230: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:09:43.81 ID:EcuGsuW2O.net
プーチン「彼らは優秀だなぜひリクルートしたまえ」
267: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:20:31.44 ID:Tsb5TbwF0.net
侵入したのはこいつらだろ。

284: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:24:26.68 ID:7ThP+7LH0.net
>>267
例の大分のか
272: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:22:34.80 ID:PO6ycGYf0.net
「誰だ!」「にゃー」 「なんだ猫か…」
280: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:23:49.33 ID:ot1Uf9lV0.net
昔、ソ連で敵の戦車をやっつける犬爆弾というものがあってだな...
自分ちの戦車で練習したから、本番では味方の戦車の下に潜り込んで自爆してだな...
中止になってだな...
285: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:24:37.12 ID:crLw1rVC0.net
猫に爆弾付けてとか、戻ってきて狭い隙間に入って自爆がオチだろ
339: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:37:18.47 ID:V94M7gTG0.net
黒幕だったのか
358: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:41:56.27 ID:CmxL+vjD0.net
非常事態が日常です
359: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:42:15.77 ID:Fa/Z+4M/0.net
ああ、これは猫型のドローンですわ間違いない
376: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:48:17.54 ID:2WEwezBY0.net
仕込みだな
387: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:51:29.88 ID:YRrO3nMS0.net
ミッション・コンプリート

391: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:52:28.43 ID:9zMdq7Ey0.net
会議の妨害が目的。次回は20匹で襲撃。
398: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:55:05.90 ID:ski+X/D60.net
417: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:59:50.27 ID:vssEn75X0.net
>>398
パッケージ写真と実物が随分違うな
413: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 18:58:36.55 ID:ski+X/D60.net
427: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:01:23.12 ID:VyiGsUy/0.net
432: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:02:05.42 ID:gya83S720.net
猫テロはあかん
454: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:10:02.32 ID:nn/HfD100.net
近所の野良たちもサミット開催してるよ
459: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:12:20.43 ID:ski+X/D60.net
>>454 
545: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:40:02.42 ID:M32ApSIH0.net
>>459
G7だからだいぶ前の画像だな
464: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:13:17.34 ID:xBAxMex10.net
トルコ最高の警備でこれじゃ一般の施設は
こわくて行けないな
479: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:16:55.10 ID:bu2bX96r0.net
>>464
もっと猫がいっぱいいるのか
512: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:27:33.77 ID:PHsZ6/gs0.net
白鵬「猫だまし」か
562: 名無しさん@1周年 2015/11/17(火) 19:47:22.91 ID:yE2G6Df20.net
これはあざとすぎる演出









 Small Size
Small Size Large Size
Large Size



 ほうとうひろし
ほうとうひろし