2 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:26:01 ID:n97
ほれ…そこにエアコンがあるじゃろ?それを使うのじゃ3 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:26:11 ID:PoD
蒸気はガス代かかるのわでは?
お布団とゆたんぽだと行動制限的のわね4 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:44:36 ID:PhY
ガス代より炬燵の方が安上がり
スクワットすれば暖かくなるよ5 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:45:08 ID:HGF
山で芝を刈って来て焚き火
6 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:47:21 ID:Ng8
お湯はお茶にして飲めるしねぇ…
部屋にうさぎもいるから考えたい7 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:50:30 ID:QfD
窓にアルミはる8 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)08:51:22 ID:g7A
腹筋10 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)09:17:06 ID:BaX
大勢呼んで体温で暖める
人が10人集まるとストーブ一個点けてるのと同じだと聞いたよ
だから映画館とかは冬でも冷房を入れてるとか何とか11 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)10:37:48 ID:Ng8
色々あるなぁ12 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)20:32:28 ID:Ng8
今夜は鍋にしよう13 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)22:08:44 ID:Ng8
七輪は今時ダメか?45 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:50:43 ID:BmU
>>13
死ぬわ
14 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)22:09:30 ID:jev
すきま風に負けないように目貼りしてから使いなさい15 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)22:10:14 ID:G9f
電気毛布とふとん18 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)23:08:36 ID:6b9
エアコンつけて洗濯機動かしたらブレーカー落ちたわw
一人用電気カーペットいいよ19 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/26(土)23:09:32 ID:cWG
エアコンは電力凄いもんな20 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)10:49:23 ID:imM
エアコンはあまり使いたく無いな…21 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:32:42 ID:r9S
湯たんぽ底に穴空いて壊れた…22 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:33:18 ID:8Qn
俺は冷え性だから足専用電気マット使ってる
あとひざ掛け23 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:33:34 ID:oNa
蒸気なんてカビ生やすつもりか42 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:35:30 ID:fjr
>>23
これに注意な26 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:39:29 ID:9d6
パソコンでゲームやる27 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:40:54 ID:oNa
電気メーターもぶん回る36 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:27:48 ID:VQN
>>27
ワロタ28 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)22:41:33 ID:T2u
こたつ
着る毛布
電気毛布30 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)01:41:33 ID:EHW
春に手に入れた2台の暖房器具がようやく役にたってきた33 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:22:32 ID:OiT
>>30
その暖房器具貸してくれw
34 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:24:03 ID:UOM
>>30
いいなあ…56 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/12/05(月)11:43:47 ID:abg
>>30
かわいいな
ほしいいいいいいいいいいいいい!31 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)01:46:48 ID:iTH
キャンプ用の銀マットでボックス作って入ってたら暖房要らず32 名前:名無しさん@おーぷん[ ] 投稿日:2016/11/29(火)01:52:30 ID:S0r
>>31
ニートなら部屋の中で動かないで済むけれど普通の人間は部屋で身仕度したり家事したりで動き回るんだよ35 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:25:08 ID:UOM
ハロゲンヒーターが即効性あっていいのだけど火災起きても気づかないので恐い37 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:29:08 ID:r75
っ着る毛布
部屋なんか暖める必要無い38 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:35:25 ID:Wjc
筋トレw39 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)07:51:49 ID:mql
登山用防寒着フル装備40 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:08:22 ID:b9O
二重窓、壁も屋根も二重(長い目)
断熱材
部屋が広いとエアコン
電気座布団41 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:11:24 ID:r75
灯油のストーブでお湯沸かす
最近のって上に物置けないよなぁ43 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:47:36 ID:fjr
部屋の中にもう一つ部屋を作る44 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:48:45 ID:r75
>>43
ベランダやんけタマほーむw47 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)08:55:32 ID:SyU
うちは石油ストーブだな。反射式の。
上にやかんを置いておけば湯も沸くし、餅も焼けるし、
アルミホイルに包んで銀杏焼いたりもできるぞ。
エアコンも節電タイプだから、かけてもいいが
暖まるまで時間がかかる。
石油ストーブはとにかく暖かい。停電でも使える。
災害時に灯油さえあれば暖は取れる。
すぐ暖かいのはガスストーブだけど、今の家はオール電化なので
ガス栓がないのと、反射ストーブのように湯が沸かせないからなぁ。48 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/11/29(火)19:07:08 ID:OiT
蒸気ダメなの?加湿器もアウトかな
湿度高いとエアコンも効くんだがなぁ49 名前:
名無しさん@おーぷん:2016/12/01(木)20:22:39 ID:IS8
寒くなってきたなぁ…

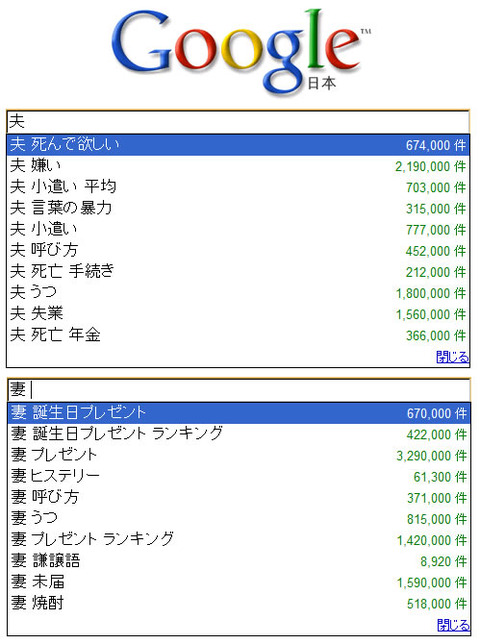
 まっきー
まっきー 


















