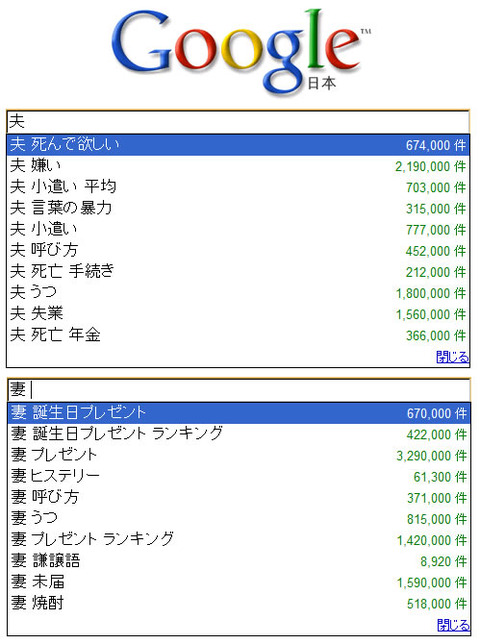2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:16.94 ID:c1+Anzf00
難しすぎでしょ
3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:22.61 ID:zWpS/bsL0
>>1
科学的考察
4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:24.68 ID:GPi5AzEF0
化学的とか難易度高杉内
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:25.72 ID:k5O9b1X80
化学的に説明しろってどうすんの?
6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:35.87 ID:cBprBGjj0
小学生の家庭科かな?
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:53:58.33 ID:mbbHKHig0
科学的になぜうまいかのとこは考察が結構難しそう
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:08.90 ID:Z5DMFGHNd
イノシン酸とグルタミン酸とか?
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:23.52 ID:HFbiYVLtd
グルタミン酸がどうとかって言えばええんか?
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:27.43 ID:00DGN/kO0
教養やったらどこもこんなもん定期
299: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:26:30.83 ID:Q+JVuRyf0
>>11
これ
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:31.65 ID:0FlH9caod
なぜ一人鍋はいけないのか
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:33.96 ID:qrw0Uqh70
家政学科とかじゃないの?
14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:34.32 ID:QpgALWyr0
一人鍋できないじゃぁんm
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:37.42 ID:4x7Kvpawa
家族も友達もおらんのやが
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:42.20 ID:zpvzrtaMp
化学関係無く陰キャには難易度クッソ高そう
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:45.69 ID:bauq9ImTd
A41枚とか逆に難しいちゃうん
49: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:50.28 ID:AObEhRsfd
>>17
しかも画像入れて1枚やぞ
字数800字程度でまとめなアカン
267: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:22:42.16 ID:FDeTTnjP0
>>49
就職予備校と揶揄される早慶はこういうレポート多いぞ
327: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:31:33.24 ID:UJ+gYvF7p
>>267
まーた適当なこと言ってる
341: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:33:54.30 ID:EROKkcW70
>>267
就職予備校は明治のことだぞ
18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:54:54.19 ID:Emqms2ZRa
グルタミン酸とイノシン酸で書いたら受かりそう
21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:55:21.81 ID:mbbHKHig0
美味いと感じるのは生物だから化学だけではなく生物学の知識も求められそう
368: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:38:46.35 ID:hBbiFlj9p
>>21
生化学の知識でええやん
24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:55:28.37 ID:pfgnsre40
科学的とか難しいな
25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:55:38.71 ID:n+4TwysPd
味の素どっさり入れた写真付けて化学調味料が美味い!ってやればええやろ
29: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:20.38 ID:z4F5vE85d
で、どこ大やねん
33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:30.31 ID:VKiOla3/d
難しいように見えてテキトーにかいたら単位とれるだけやろ
35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:39.25 ID:hCjBCi6Yp
京大やね
64: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:59:12.68 ID:j1mqJ9Xca
>>35
だよな
枠の柄に見覚えがある
36: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:43.50 ID:4x7Kvpawa
しかし懐かしいンゴねこういうの
39: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:52.60 ID:UD7lUYzOa
楽しそうわいの大学もこんなお茶目なのしてほC
41: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:55.44 ID:tJC0KVPE0
ぼっちでも化学的には味変わらんはずやろ
168: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:11:09.30 ID:yHRbtLF+0
>>41
せやな!
42: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:56:58.25 ID:y6qQcN760
化学的に考察するのにA4一枚ってなかなか難しいな
43: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:10.41 ID:+C6Hp3EU0
教養学部があるのはどこやろなあ
44: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:19.25 ID:PLVcry04r
旨味入れて味の素が出した旨味の論文引用したら余裕やろ
45: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:28.00 ID:pGHPTEU0a
一人鍋はダメってことだからこれコミュニケーション力も見られてるんやろ
51: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:58:09.08 ID:UD7lUYzOa
>>45
家族とやってもいいぞ
67: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:59:35.02 ID:K59s5ElEa
>>51
ガチのガチでコミュ力ない奴はそもそも家族ともコミュニケーション取らんから
ソースはワイ
68: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:59:50.97 ID:pGHPTEU0a
>>67
えぇ・・・
48: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:43.90 ID:w+UDn3tY0
一人暮らしぼっちを殺しに来てる
169: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:11:19.58 ID:veMEtweSr
>>48
脳内友人の出番やろなあ
写真には鍋だけ
180: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:12:06.42 ID:jkrqSx9+0
>>169
日本嫌いな脳内外国人いっぱいおるなんj民には余裕やな
50: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:57:59.70 ID:IzZLRa5j0
一人暮らしぼっち、死亡!w
52: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:58:13.61 ID:1HJF0jWDM
友達7人で鍋やったンゴ
53: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:58:18.40 ID:bauq9ImTd
ぼっちでも嘘くらいつけるやろ
58: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:58:44.10 ID:CsMEx0OS0
A4
1枚に写真付きとか小学生かよ
73: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:00:31.14 ID:wVS+I24da
>>58
学会発表の予稿とか大体A4一枚だけど
96: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:03:37.11 ID:CsMEx0OS0
>>73
それは予稿なんだから簡潔にまとめるのは当たり前だろ
141: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:08:17.43 ID:wVS+I24da
>>96
だからA4一枚に簡潔にまとめろという難しい課題なんだよ
ダラダラ書くだけならアホでもできる
60: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 11:58:56.61 ID:Z2s3poW1d
家族または友達って難易度高すぎぃ
83: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:01:43.96 ID:TTNh72Eg0
>>60
高くないんだよなあ
70: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:00:10.28 ID:ZhK5BBqCd
???「なぜ鍋が旨いかって?元々旨いからよ」
72: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:00:27.59 ID:g1RDEQfyd
本当のF欄はレポートすらない定期
77: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:00:51.72 ID:SsY0Y1eI0
「家族または友達と」っていう条件厳しすぎやろ...
82: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:01:43.20 ID:UmKMi+kx0
美味しいものは脂肪と糖でできているから
86: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:01:56.15 ID:IOAlPEK5d
これ京大のやつやん
ワイは友達と3人で食べたで
88: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:02:06.94 ID:5PR8BxAXd
写真ありで化学的な考察も含めA4一枚って結構大変だな
94: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:02:36.06 ID:zQ6M1Gs8d
つまり味の素を入れろってこと?
97: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:03:40.98 ID:ZyhspoAWM
ワイこの課題のために実家帰ったで
103: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:04:33.87 ID:NsKZMbG0d
>>97
悲しいなぁ
121: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:06:50.75 ID:gg3DOSb0d
>>97
パッパ「せっかく帰ってきたんやし、みんなで焼肉行くでー」
101: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:04:18.26 ID:fsEL4jLMK
レポートA41枚で良いとかふざけてるな
102: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:04:29.61 ID:jkrqSx9+0
ようは人間が感じる味覚の生物学的器官の説明とかそれの論拠も兼ねて記述しなきゃならんわけ?
普通に難しいやん
107: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:04:59.13 ID:VH9PHS7t0
うまいって完全に主観なんだがええのか?
114: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:05:47.57 ID:NsKZMbG0d
>>107
友達と食べるとうまいと感じる脳内物質が云々って書けばいいぞ
108: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:05:05.31 ID:8H7KfnH20
京大やろ
ワイもおったわ
109: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:05:22.87 ID:oE9nkpb7H
肉と野菜に入ってる異なる旨味成分によって正しい加熱の仕方をしたって書いて終わりやろ
123: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:06:51.35 ID:jkrqSx9+0
>>109
教授「その旨味成分とはなんていうものなの?そして人間の脳がそれをおいしいと感じるのは何故?」
110: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:05:28.41 ID:TTNh72Eg0
不味かった場合はどうすればいいのか
117: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:06:11.10 ID:1Dp3CMHmd
難しすぎやろこれ
120: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:06:46.20 ID:9M76cZlia
家族や友人と食べる事で脳内麻薬が出て旨くなる、はい論破
127: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:07:07.88 ID:6h8khDima

岡大か
163: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:10:29.19 ID:NZSQfEB4d
>>127
いうほどFか?東北民だから分からん
177: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:11:57.40 ID:GIFHbRyj6
>>163
いわゆる金岡千広のくくりだろ
宮廷の二つ下ぐらい
208: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:14:39.47 ID:lJW2IQfc0
>>127
Fちゃうやんけ
岡大は学科にもよるけど中四国じゃ上位やぞ
214: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:15:29.17 ID:yKjNB8xV0
>>127
岡大海定期
134: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:07:55.00 ID:E+lPkYgD0
コミュニーケーション力を育む名采配
135: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:07:56.81 ID:roovHCy80
ぼっち言うてもさすがに鍋食べる友達ぐらいおるやろ…
153: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:09:48.20 ID:2C9MoD8n6
これ留学生はどうするんやろ
現地に友達おる留学生とかよっぽどのコミュ強ぐらいしかおらんのとちゃうか
154: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:09:48.97 ID:bO5l9ZNh0
岡大やぞ

164: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:10:33.25 ID:jkrqSx9+0
>>154
アイコンコバヤシィ!にみえる
171: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:11:32.25 ID:0wtjCbvld

Fラン理系やから大手はこのくらいしか選択肢ないんやけどどこがええ?
216: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:15:56.71 ID:lJW2IQfc0
>>171
NTT、関電、中電
220: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:16:30.92 ID:1YRJTlHL0
>>171
ファナック一択
225: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:17:05.58 ID:bO5l9ZNh0
>>171
これ名工大やぞ
いつ見ても富士通で草生える
229: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:18:20.98 ID:eGVH8pqd0
>>225
見覚えしかないと思ったわ
235: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:19:26.51 ID:PllaZL/Ad
>>171
これ毎回どこがいいか意見が割れるの好き
文系でこのレベルいこうとしたら東大いかな無理やしよく知らんのもしゃーないが
273: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:23:12.26 ID:s3c23/KLM
>>171
ファナックやろ
株価狂ってて草生える
292: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:25:21.18 ID:hg6Z5f/+d
>>273
平均年収だけみてファナックすすめるやつおるけどどキーエンスの激務にど田舎に立地属性加えたみたいなもんだってわかってないんやろか
316: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:29:47.36 ID:KUhmAh/O0
>>292
それに加えてファナック山梨ではモテモテで超エリートらしいで
都会じゃなきゃ絶対やだって奴以外には優良物件やと思うけどなぁ
323: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:30:56.18 ID:HD10MtH5d
>>316
40で墓が立つキーエンスより離職率高いんだよなぁ
332: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:32:18.67 ID:KUhmAh/O0
>>323
まじで?
知らんかったわ
ファナック行く奴は激務とか覚悟して行くやろし黄色い宗教じみたのがキツイんかな
172: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:11:33.01 ID:d5TGYE0lp
大学サボり部はくこけ?
184: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:12:36.01 ID:MNjqQlKV0
>>172
サボり部は末尾0をいじめるから消えたぞ��
278: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:23:44.77 ID:dGAR9jt/d
ちなFランの就職実績
一見マシでも顔がええ女が稼いでるだけや
大卒として見られてない
全日本空輸(株) 23 男0 女23
日本航空(株) 15 男1 女14
東京海上日動火災保険(株) 9 男 0 女9
明治安田生命保険(相) 9 男1 女8
住友生命保険(相) 5 男0 女5
(株)JALスカイ 5 男0 女5
284: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:24:45.37 ID:I+mfSOcx0
>>278
フェリス女学院かな?
288: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:25:03.41 ID:EROKkcW70
>>278
用途が闇深
294: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:25:36.88 ID:bO5l9ZNh0
>>278
まさかとは思ったけど全日空男0かよ
関学ですら3人はおるのに
279: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:24:05.61 ID:WAen/G6w0
こういう事書いたらええんやろ

>肉類や魚類も時間の経過によってたんぱく質が分解されてアミノ酸の一つであるグルタミン酸が増えます。
>筋肉中にエネルギー源として蓄えられていたATPが分解されてイノシン酸になり、肉や魚に含まれるうま味成分が増えます。
290: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:25:06.79 ID:X++cU/de0
>>279
トマトに旨味あるとか言われると信憑性なくなるな
295: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:25:44.79 ID:hOvko4O2a
Fランの試験って問題自体は難しいようにみえて授業出てれば答え教えてくれてて持ち込み自由ってのが多いイメージ
305: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:27:53.53 ID:f4qqcYZdd
これ馬鹿にしてんの高卒だろ
専門じゃない一般教養系の授業ならFじゃなくても
もっと舐めたレポート課題とか普通にあるよ
307: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:28:09.61 ID:FDeTTnjP0
このレポートってどういう結論が正解なんだ?
・みんなで楽しく鍋食べることで脳内の快楽物質が分泌され美味しくなる
・色んな食材からうま味成分出るから
前者ならぼっちはD確定やろ
319: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:30:28.52 ID:WAen/G6w0
>>307
論理的に書かれてたらどっちでもOKやろ
330: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:31:53.64 ID:FDeTTnjP0
>>319
まぁ教養だしどっちでもいいのか
380: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:41:07.87 ID:hBbiFlj9p
>>307
両方とりいれて上手い具合に書いたら評価Aやろなぁ
308: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:28:15.70 ID:3arHJrK1a
だいたいこういうの考察も糞もwikiちょろっと見て提出やろ
こんな教養ごとき真面目にやるやつなんかおらん
322: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:30:55.35 ID:ujvJun4Fd
教授「グルタミン酸云々しか書いてないやつはDな」
324: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:30:56.71 ID:SePEkuuy0
流石に化学的な考察のやり方くらい講義の中で教えてるやろ
期末レポートってそういうもんちゃうん
328: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:31:47.20 ID:i/DvQeWY0
人と人との繋がりを大切にしてて草
331: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:31:57.23 ID:guVq0J3t0
一般教養ってなにやんねん
334: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:32:43.71 ID:2kg8Ddsyr
不味い鍋を作れば考察せんで済むやんけ
340: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:33:36.75 ID:MbgXGqtG0
>>334
教授「鍋まずくするとかコイツバカだわ」単位無し
344: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:34:30.90 ID:ZY547eZia
>>340
草
345: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/20(火) 12:34:41.02 ID:uL4cSVW3a
>>334
まずい鍋を作った時点でアウトやぞ