「混沌堂主人雑記」から転載。
冒頭に私のブログまで引用してくれてあったが、私は何の情報網も持たない人間であり、すべてネット上の記事の中で「考慮に値する」と自分が感じたものだけを材料に自分の妄想を書いているにすぎないことはもちろんだ。安倍総理の訪露への私の意見と、安倍総理への評価も、横井小楠流に言えば、「これは今日の考えでしかなく、明日は変わるかもしれない」ものである。
人間の本性(卑しさ、気高さなど)は変わらないものかもしれないが、政治では人間性よりも「何をしたか」が一番の問題であり、立派なことをした悪党は何もできなかった善人よりいい。好き嫌いは別の話だ。(ということで、「谷間の百合」さん、お許しをwww)自分が交際するなら、安倍や麻生や橋下は最悪の人間だろう。
安倍の対ロ接近は中露関係にくさびを打ち込むためだ、という考えももちろん考慮に値する。だが、ロシアへの対応という点では、世界政治の沼に大きな石を投げ込んだことは確かだろう。中国も、それほどロシアと仲がいいわけでもないのだから。
下記引用記事の中にもインチキ情報も多々あるとは思うが、「思考素」としては刺激的なものもある。まあ、ベンジャミン・フルフォードの発言のようなものだ。無難な、気持ちのいい内容の記事だけでなく、こうした「雑情報」に多く触れるほうが視野は広くなるのではないか。
さて、安倍訪露の意味、安倍プーチン会談の意味を重大に捉えるかどうかだが、私は重大だと捉えている。日本が対米自立を国際的に宣言したも同然の振る舞いなのだから、重大に決まっている。しかもそれは、下記記事の言葉を借りれば、G7協調の対ロ制裁に対する「スト破り」なのだから、大胆勇敢な行動であると評価していい。
あるいは、むしろ、オバマから「それ、やっていいよ」という無言のサインがあったのかもしれない。政治とはそういうものだろう。政治家の口先の言葉を馬鹿正直に信じると馬鹿を見る、というのは「真田丸」で見事に描かれているwww 特にオバマがこれまで言ったこととしたことが見事に乖離しているのはご存じだろう。安倍は「本物の政治」を学びつつあるのではないか。これは褒め過ぎかwww 人間は当事者にならないと何も分からない。総理になって学び、成長することだってあるだろう。50歳でも60歳でも精神年齢は成長する。これまでの安倍の精神年齢は6歳くらいだったのだから、なおさらだwww
(以下引用)
シャンティ・フーラ より
上記文抜粋
・・・・・・・・・・
プーチン大統領と安倍首相の会談は高評価
プーチン大統領からの情報が八咫烏・五龍会の幹部の耳へ
2016/05/11 10:19 PM
竹下雅敏氏からの情報です。
スプートニクでは、プーチン大統領と安倍首相の会談を高く評価していることがわかります。私もこの記事の見解に同意します。
ところで、文中にある“1対1の会談”ですが、“テーマは極めて建設的な雰囲気の中で取り上げられた”とあります。文章の流れから見て、このテーマとは、領土問題ということになりますが、その本質は別の意味での領土問題だと考えています。
これ以上は触れないことにしますが、プーチン大統領からの情報は、安倍首相が信頼する極めて少数の人物を介して、八咫烏・五龍会の幹部の耳に入りました。彼らはこの報告を聞いて激怒しており、これまで協力関係にあった組織を日本から排除する意向を固めたと考えています。近い将来、そうした事がはっきりとわかる事例が出て来ると思います。
(竹下雅敏)
・・・・・中略・・・・
安倍首相とプーチン大統領の会談について:日本は事実上、対ロシア制裁システムから抜け出した
引用元) sputnik 16/5/11
日本の首相は、ロシアとの平和条約交渉で本当の飛躍が訪れると確信している。安倍首相はロシア南部ソチでプーチン大統領と会談した後、与党「自民党」の委員会会合で、そのような確信を示した。
安倍首相は、「北方領土」問題に関するハイレベル対話を含む積極的な交渉プロセスを続けると指摘した。なお菅官房長官は、南クリル問題に関する日本の基本的立場に変化はないことを強調した。
(中略)
ロシア科学アカデミー極東研究所日本研究センターのワレリー・キスタノフ所長は、次のような見解を表している-
「このような声明は、すでに双方から出されていた。しかし私は、安倍首相が両国関係を70年間も陰気にさせている問題を解決したリーダーとして歴史に名を残すのを実際に夢見ていると考えている。また安倍首相の父親の安倍晋太郎氏は、外務大臣を務めていた時に、当時のソ連大統領だったゴルバチョフ氏を日本に招くために非常に多くのことを行った。その時ゴルバチョフ氏は、領土問題は存在していないというそれまでのソ連の立場から事実上離れ、少なくともそれを話し合う必要があると考えた。その時、安倍氏はがんを患っていたが、ゴルバチョフ氏と個人的に会うために病院のベッドから起き上がった。これは同問題が安倍晋太郎氏にとってどれほど重要であるかを示しており、恐らくその息子である安倍晋三氏にとっても同じであると思われる。ロシア関係における日本の現首相の行動は、実際に決断力のあるものだと述べることができる。なぜなら安倍首相は、米国側からの極めて強い圧力があるにもかかわらず、そのような行動を取っているからだ。事実上、安倍首相は現在、G7にとって『スト破り(streikbrecher)』となっている。安倍氏は共通の体制から抜け出して、ロシアへの制裁や圧力政策を無視した。
安倍氏は、ロシアとの交渉で進展を得ようという決断力に満ち溢れているかのようだ。」
またアレクサンドル・パノフ元駐日大使も、安部首相のソチ訪問は、今のところいかなる具体的な声明も表されていないものの、実際には両国関係に多くの進展をもたらしたとの見方を示し、次のように語っている-
「安倍首相のソチ訪問は、極めてポジティブなものとなった。なぜなら、すぐに両国関係にたくさんの動きを与えたからだ。その際、日本は事実上、公式には述べられなかったものの、西側の対ロシア制裁システムから抜け出した。安倍首相がソチへ持ってきた提案を見た場合、ほぼ全ての分野に飛躍的かつ非常に重要なポイントがあるのが分かる。政治的対話が盛んになってきている。今年、政治的対話はかつてなかったほど集中的に行なわれるだろう。ハイレベル会談は5回以上予定されており、安倍首相はウラジオストクで開かれる経済フォーラムへの招待を受け入れた。
安倍首相は経済でも関係発展のための日本のプランを提示した。そこでは西側の制裁下に置かれた分野も取り上げられている。それはハイテク協力や原子力エネルギーでの協力だ。シベリアと極東での協力は、インフラ建設で日本の投資が求められている。そしてこれも西側の制裁政策の下から抜け出すものだ。
領土問題だが、これについては日本の政策で何らかの新たな要素が実際に現れそうだ。いずれにせよロシアの大統領報道官は、安倍首相とプーチン大統領のソチでの一対一の会談についてコメントし、テーマは極めて建設的な雰囲気の中で取り上げられたと指摘した。安倍首相は4島返還を求める日本の立場に変わりはないと述べたが、その際、協議では過去の考えから解放された新たな立場も用いられるだろうと指摘した。そしてロシア側は、日本のこのアプローチを極めてポジティブに評価した。なぜならこれは今後交渉を実施するための新たな基盤を与えるからだ。以前は日本の変わらぬ立場によって平和条約に関するいかなる交渉もなく、ただ足踏み状態だったからだ。」
これら全てを総括し、安倍首相とプーチン大統領のソチでの会談のための新たな提案を日本が自ら作成したことを考慮した場合、これは、平和条約締結に関するロシアと日本の交渉プロセスの進展が実際に可能であると考えるきっかけを与えている。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
抜粋終わり
金玉満堂ブログ より
上記文抜粋
・・・・・・・・・・・・
プーチンとアベは 密約を交わしていた!
◆2016/05/12(木) プーチンとアベは謀議して…
密約を交わしていた!
アベがアメリカの反対を押し切って,はるばるソチまで出向いた理由・目的・会談の結果表明…,これらの全てが「さぱ~り分からない」 (記事)
『スプートニク』を読んでも,「さぱ~り分からない」
なぜか?
絶対に公表できない理由があったからだ。
PutinAbe
プーチン・アベ会談があった6日は,モスクワで開かれるアイスホッケーの世界選手権の開会式があり,プーチン大統領の出席が決まっていた。
しかし,プーチン大統領は,安倍首相との会談のために敢えて出席をキャンセルし,開会式にはメドベージェフ首相が出席した。
これは,非常に異例のことだ。
この異例さは,プーチン大統領に何か重要な目的と理由があったからだ。
『スプートニク』の記事は普段は論旨が明快であるが,プーチン・アベ会談に関しては,曖昧模糊な表現が多い。
露日首脳会談、プーチン大統領「日本は重要なパートナー」 (記事)
安倍首相とプーチン大統領の会談について:日本は事実上、対ロシア制裁システムから抜け出した。 (記事)
「プーチン大統領と安倍首相は、巨大投資プロジェクトについて話し合った」 (記事)
露日首脳会談は全方面の相互関係拡大への構えを示した。(記事)
普通は論旨が明快な記事を載せるはずの『スプートニク』だが,プーチン・アベ会談に関しては,その理由・目的・会談の結果等々について,全く具体性が無い!
その理由は…,
絶対に公表できない「秘密協定」に近い「密約」を結ぶことがソチ会談の目的だったからだ。
中国と北朝鮮の“情報分析筋”がワシに漏らしてくれた「密約」の内容を,ズバリ!書いておこう。
ひとつは…,アベとアベの官邸に強烈な圧力をかける米国戦争屋を,ロシアの在日情報機関が全力をあげて牽制する!という保障をプーチンがアベに確約したこと。
ふたつ。アベを米国の「刺客」から守る特殊作戦(人的,情報的,組織的)をプーチンはアベに提示した。
みっつ。上の目的を達成するために,アベの官邸がロシアの在日情報機関に最大限の便宜を図ること。
よっつ。上の三項目は,アベの訪露前に開始されていたことの確認。(だからこそアベは,米国の圧力を回避して訪露することが出来た!)
いつつ。米国の戦争屋に対抗するロシアの在日謀略機関の員数を増加させる策略。
むっつ。米国戦争屋の圧力を排除すれば,アベは真の独立国家の総理として,偉大な仕事が出来る。
ななつ。「偉大な仕事」とは何か? 「それを8月末までに決定しよう!」 と言うプーチンに,アベは 「ダ~!」
以上! …だが,上の「ロシアの在日謀略機関」には,中国系ロシア人や北朝鮮系ロシア人もゐる!という。
飯山一郎
上の話は…,ガセだとしても面黒いっしょ?>皆の衆
真坂!


 竹熊健太郎《一直線》
竹熊健太郎《一直線》 
 さらしる
さらしる 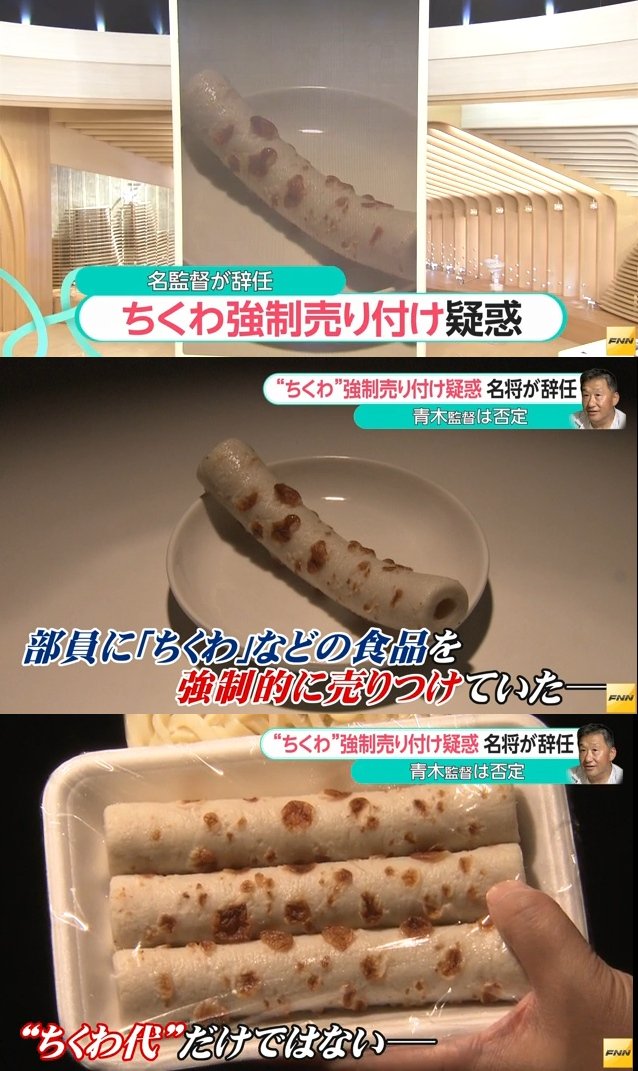
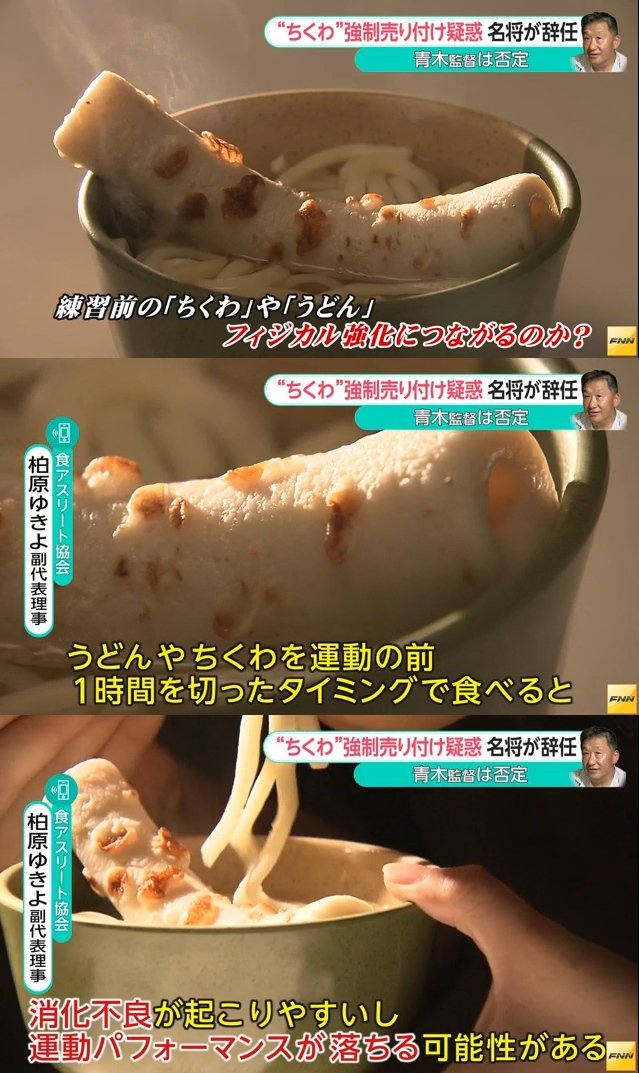
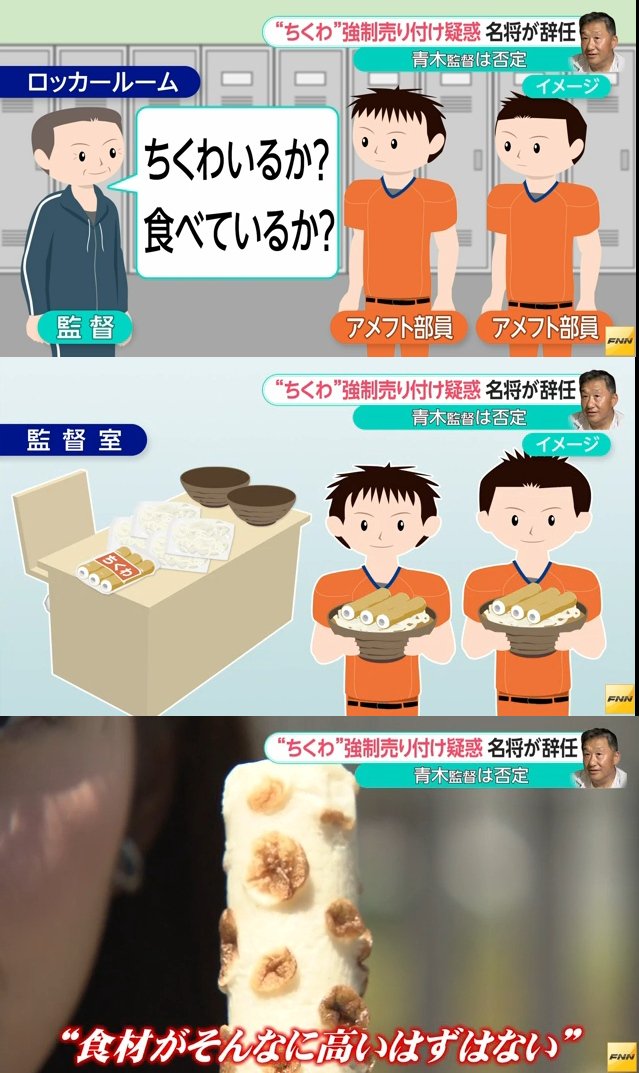

 小田嶋隆
小田嶋隆