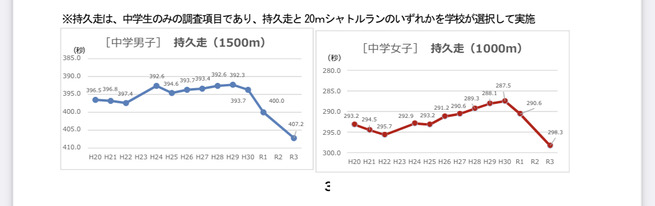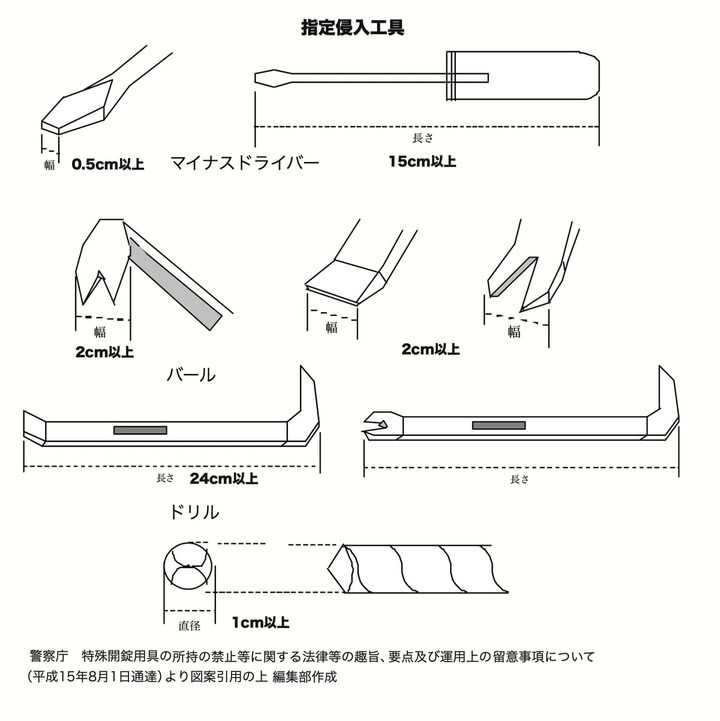昨日発表した9つのポイントを覚えているでしょうか?そこには、現在、地球上の人類に対して使われている攻撃ベクトルがあります:
1. 計画された飢饉と大量餓死
2. 電気、暖房、燃料を供給するエネルギーインフラの意図的な解体
3. 殺傷を目的とした生物兵器の多発
4. 従順な大衆に遅効性の安楽死注射を強要するための世界的なワクチン義務化
5. 生物圏を崩壊させ、世界的な不作を引き起こす惑星規模の地球工学と気象制御
6. 世界的な貧困を引き起こすために、世界の負債に基づく不換紙幣を意図的に崩壊させる
7. 世界的な紛争をエスカレートさせ、ロシアと中国を巻き込んだ世界大戦を引き起こす
8. 経済崩壊を引き起こすグローバルサプライチェーンの制御解体
9. プラスチック化学物質、農薬、ホルモン撹乱剤、LGBTグルーミング、トランスジェンダーによる生殖能力の破壊
この9つはそれぞれ、2022年~2025年にかけて積極的に加速される予定です。
殺戮の段階が始まったのです。(国の指導者たち、特にトルドーやバイデン、ヨーロッパの指導者などWEFに従順な人々のあらゆる決定は、現在から2025年末の間に最大数の人間の犠牲者を出すように設計されているのです。グローバリストたちは、Covidワクチンのおかげで、2030年までに10億~20億人の死者が出ることをすでに見越しています。飢饉、経済崩壊、内戦、生物テロ、核攻撃、グリッドダウンのシナリオを重ねると、20億から40億人程度の死者が出ることになるでしょう。
この結果、現在の人類の25%から50%が今後数年のうちに絶滅するということは、すでに「織り込み済み」で、覆すことはできないようです。例えば、ワクチン死の注射は、すでに50億人以上に投与されています。肥料不足、不作、食糧保護主義/ナショナリズムにより、人工的な飢餓と食糧不足はすでに達成されています。例えば、インドは米の輸出を禁止しようとしています。この政策は、食糧不足と飢饉という破滅的な世界的緊急事態を引き起こすでしょう。(出典:Bloomberg.com)
不換紙幣の債務崩壊も避けられない現実です。過去3年間、西側諸国では絶え間なく、ほとんど理解不能な紙幣印刷が行われており、これらの国々の財政的な支払い能力に関して言えば、もう戻れないところをはるかに超えてしまっているのです。アメリカ、EU、日本の通貨は近い将来煙に巻かれ、これらの国や地域は経済的に破たんすることになるでしょう。
重要なのは、もし各国の指導者が経済の持続可能性と健全性を維持しようと本気で考えていれば、最悪の事態を回避したり、軽減したりすることができたということです。しかし、彼らは破局を避けようとはしません・・・むしろ悪化させようとしているのです。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本、オーストラリア、ニュージーランド、その他の国々の指導者はすべて、地球上の人類文明の完全破壊を目指す反人類、反文明のグローバリストの命令を受けているグローバリストの操り人形なのです。




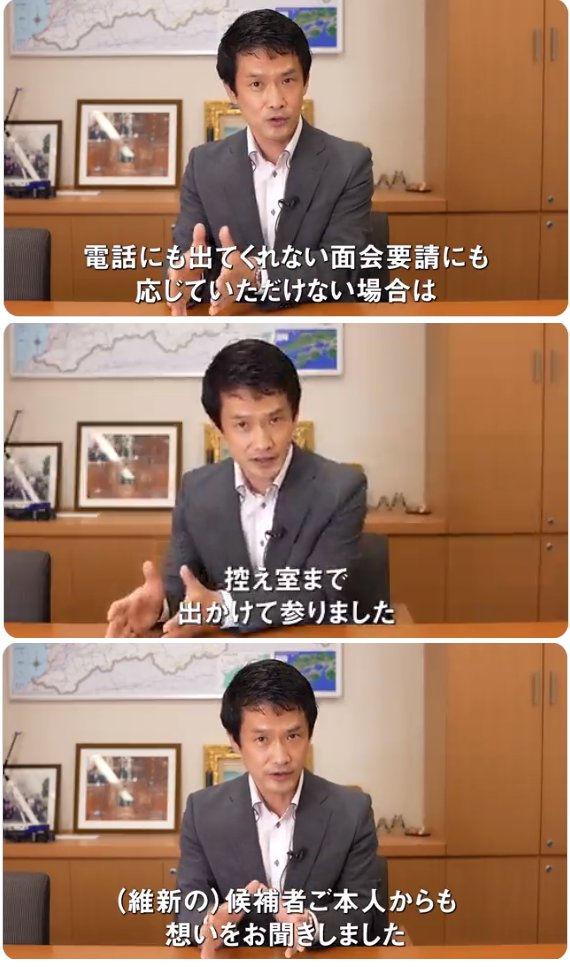





 CC110
CC110