「ネットゲリラ」から転載。
タイトルはアレだし、コメントにも氏も寝た、じゃない、下ネタが多くて少々うんざりだが、論じていること自体は面白い。
要するに、男は論理が好きで、女はコミュニケーションが好き、ということだろう。それは男女の会話の違いを見ればすぐに分かる。
女性の会話は、会話していること自体が嬉しい、つまり他人と触れ合っていること自体が嬉しいのであって、会話の中身などどうでもいいのである。いちいち、「それはどういう定義で言っているのか」「その情報のソースは何か」などと突っ込む阿呆は敬遠される。女性にとってのソースは料理のソースしかない、などと言えば女性蔑視発言になるか。ww
なお、紫式部や清少納言の昔から、日本の女性は自然や人事に関する繊細な感覚を持っていて、特に男女間のドラマに関しては、女性の方が優れたセンスがある。その反面、歴史ドラマなど、政治的要素を含むドラマやスポーツのドラマなどは女性よりも男性が得意としている。
最近のNHKの大河ドラマの失敗は、歴史ドラマの脚本を女性脚本家に書かせたことが根本的な間違いだ、というのが私の考えだ。
またしても女性蔑視発言になった気もするが、そうではない。男は女性よりも幼児的で粗雑だから、力仕事でもさせとけばいい、ということだ。政治や戦争は、あれは「ゲーム性」があるから男の子が夢中になり、得意だというだけの話。
Man must work ,woman must weep.
働かない男は男じゃない、涙を見せない女は可愛くない、と英語の諺でも言っている。まあ、これ自体、男性優越論者的な言い草だ、とフェミニストからは言われそうである。
(追記)男が論理が好きなのは、論理自体にゲーム的なものがあるからだ、というのが私が今思いついた新説。ゲームは、「規則に従って問題を解決する」という点で論理とそっくりである。
女性は、規則もへったくれもない。答えが手に入ればそれでいいのである。だから女性に論理や倫理を言ってもムダ。「好きか嫌いか、損か得か」が根本のポイント。逆に、だからこそ最短距離で答えが出る。その答えが自分に不利なら受け入れないだけのこと。(もちろん、力関係によっては受け入れるが、まったく納得はしない。)男は無駄な論理の展開そのものを味わい、答えが自分に不利でも納得し、甘んじてそれを受け入れる、ある意味阿呆である。
(以下引用)
女の子って電マに弱いよね
オンナは英語が得意で、オトコは電気が得意というんだが、オンナの関心というのはコミュニケーションにあって、語学でも文学でもない。なので、得意と言っても、どーでもいい事をパーパーしゃべってるだけです。オトコはよっぽど必要に迫られないと、外国語は覚えないし、使わない。おいらも簡単な貿易は英語使えるが、つうか、料理の注文はタイ語で出来るが、その程度。英語なんて、必要がなければ使えなくて構わない。
英語がなぜ必要かというと、国際化の時代だから英語を知らなければと言われる。
でも「必要なもの」は英語だけではない。
私などは物理の出身だから、「電気はとても大切」と思う。
生活の面でも感電したり、火災になったりする原因の一つに女性が電気に弱いということがあるのを痛感している。
しかし、私は電気がわからない若い女性に無理やり、電気を学ばせようとはしない。
おそらくは脳の構造によると思うけれど、多くの女性は中学生か高校生の時に「電気がさっぱりわからなくなる」という時期が来る。
数10年もすると脳構造が明らかになり、「女性の体には子宮があり、その反面、脳の中に電気を理解する領域がない」ということが明らかになるだろう。
それと同じことが英語で起こっている。若い男性は語学が殊のほか弱い。
特に電気や機械の男子学生は、電気、機械はよく理解するが、語学はとにかくダメで、嫌がる。
そんな男子学生に「英語ができなければダメだ」というので、多くの学生がそこで学校が嫌いになる。
文化系の女子学生に電気の勉強と合格点を強要するようなものだ。 電気は、むしろ知らないと感電して死ぬので、ちゃんと勉強しておけw おいら、真空管アンプ作ってて、400vで感電して、20kgのアンプを放り投げた事がありますw |
英語に力を入れると日本の技術力が落ちる 「女性は子宮の代わりに電気が理解出来ない」、というわけで、例によって2ちゃんねるでは無責任なネットすずめたちがピーチク騒いでおります。ニュース速報板からです。-----------------------
このスレ英語禁止にしようぜ
-----------------------
↑自分で何言ってるかわかってないだろw
-----------------------
↑オッケー!
-----------------------
↑バーカ
-----------------------
電気を勉強しようとするとある程度は、英語が出来ないと
文献や論文読めないじゃん
-----------------------
↑それが日本は母国語で理系学問の殆どのことを学べる数少ない国なんだよ
それができる言語は英語フランス語ドイツ語日本語だけ。
-----------------------
↑ノーベル賞受賞上位国だな
-----------------------
女は確かに電気系では見ないな
まああいつらカワイイで選り好みするからな
-----------------------
↑じゃあ手始めに「オームの法則かわいい」から刷り込むか
-----------------------
小5くらいから英語やってる子供たち
授業はクソの役にもたってないから安心して
-----------------------
おかしい。
理系の学生は英語もよくできる。
理系は英語、数学、理科必須
-----------------------
>数10年もすると脳構造が明らかになり、「女性の体には子宮があり、
>その反面、脳の中に電気を理解する領域がない」ということが明らかになるだろう。
いくらなんでもトンデモすぎないか
-----------------------
女が電気弱いというのは分かっている人多いと思うけどさ、学者がこれ言っちゃっていいの?
差別じゃん
-----------------------
エレクトロニクスことそ日本の経済成長力の根源だったからね
ラジオやテレビやLSIに始まり今のハイブリッドカーとかも
日本の金融やメディアや情報処理や流通産業は他国と比べて何も優れてないのに
エレクトロニクス産業が世界で圧倒的に優秀で国富稼ぎまくってるお陰で
それにおんぶして世界の一流企業の顔していられるだけ
-----------------------
理系は工学でも生物でも医薬でも化学でも論文読むのにある程度の英語力は必要
-----------------------
でも英語は女のほうが強いよね
通訳とかも大体女だし
男って英語も出来ないんだ・・・
-----------------------
男性はちんこの代わりに英語ができない
-----------------------
女は学が無くても英語が喋れる方が上と思ってるから語学留学に行きたがる
-----------------------
原始時代から、男は職人技術、
女はコミュニケーションを武器にしてきたからかと
だから男は技術系が得意で
女は語学が得意なんじゃね
-----------------------
何でこの書き出しで段落が変わったら突然まんこ叩きになるのw
-----------------------
「電気が理解できない」が意味不明だ
英語なんかコンプレックスを無くせばできるようになるよ
-----------------------
なんでもそうだけど本当に賢いやつは語学でも独学で身に付けるよな
-----------------------
日本の場合はカタカナの存在が悪いんだよ。
カタカナが日本社会から英語を駆逐してる。
この2chですらどれだけ英単語がカタカナに変換されて行きかってるか
中国も英語が日本と同じダメダメ、中国も英語を無理やり漢字に変換してるからな
-----------------------
オスは狩りに必要な単語だけ分かればあとは獲物をいかにたやすく狩れるかに専念するから、自然と物理や数学に必要な領域が発達して来た。
メスは限られた資源をいかに集落の中で分け前を得るか、時に別の集落との間で自分に有利になる様に相手とのコミュニケーションを取るかに専念するから、自然と言語能力が発達して来た。
そんだけのこと
-----------------------
女は電気が理解できないんじゃなくて、そういうのは男の仕事として必要と感じてないんだろ。
男が一般的に料理や裁縫は女のやることとして深入りしないのと同じで。
-----------------------
ハンダ付けは女の方がうまい
-----------------------
TVに出ている外人観光客、
ベルギー人やドイツ人が英語ぺらぺらでビビったわ。
ネイティヴじゃなくて学校で英語を習っただけなのに、
なんであいつら、あんなに喋れるんだよ。
-----------------------
↑あいつらにとって英語なんて方言みたいなもんだろ
日本人にとっての英語とはまったく違う
-----------------------
そもそも英語力が国力や経済力に繋がるとは思えない。
だったら、なんで外大卒の女子大生の進路はあんなに地味なんだ?
本当に語学力が重宝されるならば、
京大や阪大なみに一流の民間企業に就職してるはずだろ?
-----------------------
最近支那人が多すぎるのでしょうがなく支那語勉強し始めたのだが意外と簡単でワロてるw
-----------------------
長渕剛「今の日本はアメリカかぶれが酷くてやたら横文字を使ったりする。
英霊が護った美しき国土と文化を破壊する行為。
60年前の戦いに殉じた日本の男たちに対する鎮魂歌
『クローズ・ユア・アイズ』
聴いてくれ
-----------------------
電気なんかさっぱりわからん
掃除洗濯料理が大好きな俺は完全に女脳
-----------------------
ちんこのまんこの違いだけでそんな学問に差が出るとは思えんがな
社会に求められている像に従っているだけのような気がす
-----------------------
英語なんてまんこに習得させて
それを安く使えばいいんだよな
----------------------- ノーベル賞の上位国は、「自国語で高級学問が学べる国」というのは、なかなか鋭い。そう考えると、中国や韓国がなかなかノーベル賞取れないというのも理解できる。選び抜かれた超エリートだけが、海外で、それも外国語で学ぶのでは、底辺が広がらない。日本は、圧倒的に底辺が広い。ノーベル賞取ったのも、東大以外の、地方の国立大学出身者が多いですね。
-----------------------
電気なんか簡単だろ
オームの法則、キルヒホッフの法則だけだろ
交流回路では位相差に注意すれば良い
-----------------------
言葉って文化の結晶だからさ
英語で考えたら英語圏の奴に勝てるわけがないんだよね
-----------------------
確かに主婦に必要なのは電気と化学の知識だよな。たこ足配線、混ぜるな危険。
-----------------------
マレーシアやシンガポールの理系男性はマルチリンガルで電気も理解出来る...
つか、ココまで英語が苦手なのは「団塊世代の日本人理系男性」だと思う。
-----------------------
論文を書くのは無理だが、読むのは単語さえ調べれば言ってる意味は大体わかる。英語もできる技術者はエリートだけで、ほとんど出来ないよ。
受験は矛盾だらけなのはいまに始まった話じゃない。受験が修行なら、苦手な分野やらせるほうがいいのにね。
-----------------------
まあスマホで自動翻訳はあと5年もすれば完璧になるよ
語学の壁なんて無くなる
英語ごときでドヤ顔してる奴らは全員無職にww
-----------------------
英語教育は必要だけど、小学生にやらせるのは問題あると思う。
まずは母国語での表現を学ばないと。
あと自動翻訳は5年じゃ実用レベルにならない。
いまの段階じゃまだどうすれば一段実用性が上がるかという
ブレイクスルーが見えてないから。特に日本語→多国語の場合。
-----------------------
技術者なら自分の専門分野の英語ぐらい理解できるだろ
-----------------------
小学校の英語なんて無駄そのもの。
英会話は楽器やスポーツと同じで
週1回ちまちまやっても、ぜんぜんダメ。
短期集中で2週間英語漬けみたいなやり方の
ほうが絶対身につく。週1回ちまちまってのは
単に英語の先生が生活しやすいという
ドーデもいい理由によってる。
-----------------------
女の子って電気に弱いよね
えっちなビデオでガクガクしてるのみたもん
-----------------------
ソフトウエア業界は無茶な直訳でするから、さっぱり意味がわからない
むしろ英語のままの方が伝わる
-----------------------
電気? 寝る前にちゃんと消してるし大丈夫だよ!
-----------------------
>「女性の体には子宮があり、その反面、脳の中に電気を理解する領域がない」
言いたいことは解るが、この言い方はすごくバカっぽく聞こえる
-----------------------
女はやりたくないことは覚えないから
-----------------------
英語よりも日本語
専門書とかの英語は必要になれば読める
-----------------------
ランチパックのCMで、卵をタマァゴゥとか英語訛りの日本語で言うのやめろw
-----------------------
安易な多言語環境は、一言語あたりのボキャブラリーを狭く浅くするだけ。
そしてボキャブラリーの広さ深さはそのまま思考する力の担保になる。
-----------------------
ノーベル物理学賞、益川敏英
「英語、まったくわからない。
今まで1回も使っていない。
だから海外にも行かない。w」
-----------------------
正直英語できたところで頭は良くはならないからな
英語以外に強みがなきゃ(要は馬鹿なら)単なる翻訳家としての使いっ走りだからw
-----------------------
何で英語圏の連中に認めてもらわなきゃならんの?
秘密にしとけよ
-----------------------
学校のテストで点を取る為の英語はもうやめろ
完全に時間の無駄
-----------------------
バブル期に一時もてはやされた帰国子女は酷かったな
-----------------------
受験程度の理数系なんて大して時間かからなかった
最後まで足引っ張ったのは英語だったな
-----------------------
技術職だと英語文献の読解は必須だけどね
英語資料と日本語資料だと、質、量、速さすべてで誇張じゃなく一桁差がある
日本語文献しか読めないだけでとてつもなく大きいディスアドバンテージになる
----------------------- 基礎的な学問をすべて、自分の国で、自分のネイティブな言葉で学べるというのは、物凄いアドバンテージだ。世の中には、それが出来ない人が多い。つうか、日本語がちゃんと出来れば、英語なんてそんなに難しくない。つうか、語学が出来なきゃ、教科書も理解でない、という事ですw 語学は苦手だけど、電気や物理は得意です、なんてヤツはいませんw |


 ふどあ
ふどあ 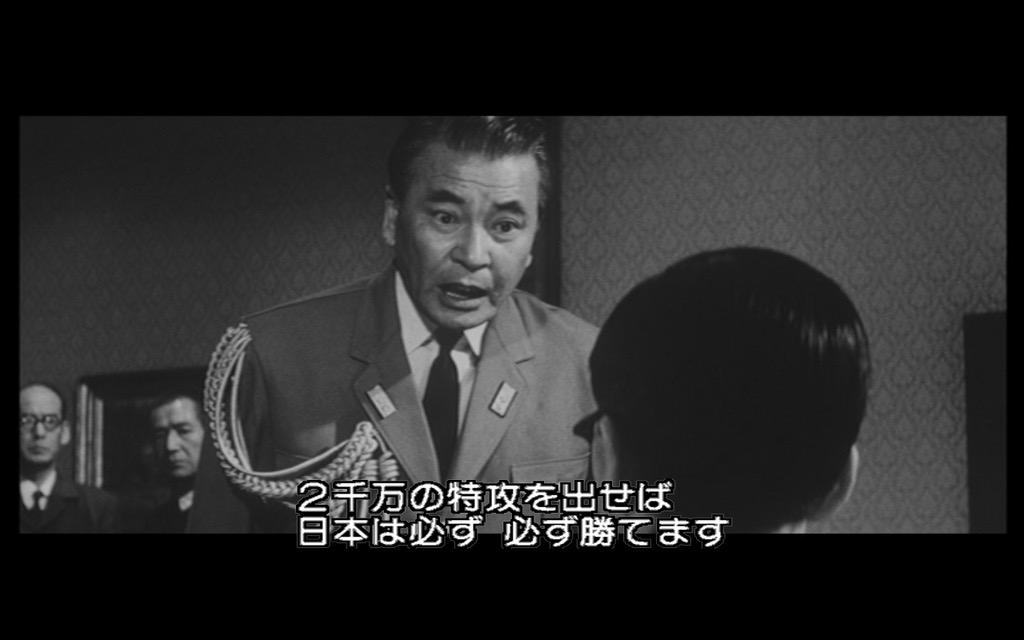


 盛田隆二
盛田隆二