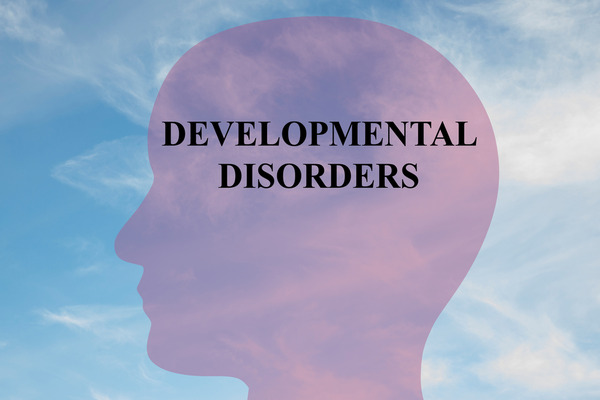784 : sage 2017/08/29(火)01:25:14 ID:oLQ
先日久々に再会した友人A子の心を恐らくプチ修羅場にしてしまった。
A子とは小学校低学年からの付き合いでそこそこ仲が良かったと思う。
小学校5年生春のある日曜日、A子の家に遊びに行ったときのこと。
A子の部屋へ行く前にいつもリビング(台所併設)に寄って、飲み物とお菓子を分担して持っていく私たち。
その日もA子と一緒にリビングに入ると、そこには彼女の父親がいた。
私はお邪魔しますと軽く挨拶するとA子が飲み物などを用意してくれるのを待っていた。
スペースの都合上、A父の座るソファーの脇だったのだけど・・・
A父「私ちゃん、お〇ぱい大きいね」
という言葉と共にソファーに座ったA父が極自然な感じで胸を揉んできた。
揉むというか摘まむ?指3、4本で膨らみはじめの部分をフニフニされて少し痛かった覚えがある。
当時そういうことの意味がよく分かっていなかった(自分と性的な行為とが結び付かなかった)ボケボケの私は「え?はあ、まあ・・・?」と薄っすい反応しか出来なかったのだけど、まずA子がすごい悲鳴を上げて準備してたコップやお菓子を置き去りに私の腕をつかんでA父から遠ざけた。
A子「最低!クソ親父!最低!最低!!最低!!!」
A父「いや、ノーブラだなと思って、つい」←??
A子「最低!!!!!」
というやりとり(?)の後A子に引っ張られるまま家を出て、結局私たちは公園で遊ぶことに。
ごめんね、と何度も涙目で謝ってきたA子に、やっぱりよく分からないまでも何か大変な事なんだなとは理解した私は「ダイジョブ、ダイジョブ」と軽〜く明るく言ってたはず。
当日こそA子との間に微妙な空気があったけど、それから仲が悪くなるようなこともなく普通に友達してた。
人に話すようなことでもないしこのことは話題にも上らなかったんだよね。
でもその数ヶ月後の夏休み明け、A子両親が離婚した。
わざわざA子の母親が私のところに来て『怖いおじさんはいなくなったから安心してね』って。
これはA子から聞いたことだけれど、A子は元々A父親があまり好きではなくて、私にした変態行為からはいよいよもって気持ち悪くて仕方なくなり、吐きそうになりながらA母親に相談したんだそうだ。
そしたら程なくしてA子はA母親の実家に預けられて(夏休み開始直後)学校のプールもそっちから通いつつ一月過ごして家に帰ったら父親がいなくなってたんだと。(夏休み終了直前)
どうもA父親は自宅にも変なものを大量に隠し持ってたらしい。
『変なもの』が何なのかは怖くて聞けなかったけど、さほど時間もかからず離婚を成立させてA父親を追い出せるような負のパワーアイテムだったんだろう。
以後、A父親を見かけることは一度もなかった。
まあそれらの事柄とは関係なくA子とは高校で進学先が別れて段々と疎遠になってたんだけど。近所でもなかったし。
ここまでが長い前提。
A子とは小学校低学年からの付き合いでそこそこ仲が良かったと思う。
小学校5年生春のある日曜日、A子の家に遊びに行ったときのこと。
A子の部屋へ行く前にいつもリビング(台所併設)に寄って、飲み物とお菓子を分担して持っていく私たち。
その日もA子と一緒にリビングに入ると、そこには彼女の父親がいた。
私はお邪魔しますと軽く挨拶するとA子が飲み物などを用意してくれるのを待っていた。
スペースの都合上、A父の座るソファーの脇だったのだけど・・・
A父「私ちゃん、お〇ぱい大きいね」
という言葉と共にソファーに座ったA父が極自然な感じで胸を揉んできた。
揉むというか摘まむ?指3、4本で膨らみはじめの部分をフニフニされて少し痛かった覚えがある。
当時そういうことの意味がよく分かっていなかった(自分と性的な行為とが結び付かなかった)ボケボケの私は「え?はあ、まあ・・・?」と薄っすい反応しか出来なかったのだけど、まずA子がすごい悲鳴を上げて準備してたコップやお菓子を置き去りに私の腕をつかんでA父から遠ざけた。
A子「最低!クソ親父!最低!最低!!最低!!!」
A父「いや、ノーブラだなと思って、つい」←??
A子「最低!!!!!」
というやりとり(?)の後A子に引っ張られるまま家を出て、結局私たちは公園で遊ぶことに。
ごめんね、と何度も涙目で謝ってきたA子に、やっぱりよく分からないまでも何か大変な事なんだなとは理解した私は「ダイジョブ、ダイジョブ」と軽〜く明るく言ってたはず。
当日こそA子との間に微妙な空気があったけど、それから仲が悪くなるようなこともなく普通に友達してた。
人に話すようなことでもないしこのことは話題にも上らなかったんだよね。
でもその数ヶ月後の夏休み明け、A子両親が離婚した。
わざわざA子の母親が私のところに来て『怖いおじさんはいなくなったから安心してね』って。
これはA子から聞いたことだけれど、A子は元々A父親があまり好きではなくて、私にした変態行為からはいよいよもって気持ち悪くて仕方なくなり、吐きそうになりながらA母親に相談したんだそうだ。
そしたら程なくしてA子はA母親の実家に預けられて(夏休み開始直後)学校のプールもそっちから通いつつ一月過ごして家に帰ったら父親がいなくなってたんだと。(夏休み終了直前)
どうもA父親は自宅にも変なものを大量に隠し持ってたらしい。
『変なもの』が何なのかは怖くて聞けなかったけど、さほど時間もかからず離婚を成立させてA父親を追い出せるような負のパワーアイテムだったんだろう。
以後、A父親を見かけることは一度もなかった。
まあそれらの事柄とは関係なくA子とは高校で進学先が別れて段々と疎遠になってたんだけど。近所でもなかったし。
ここまでが長い前提。