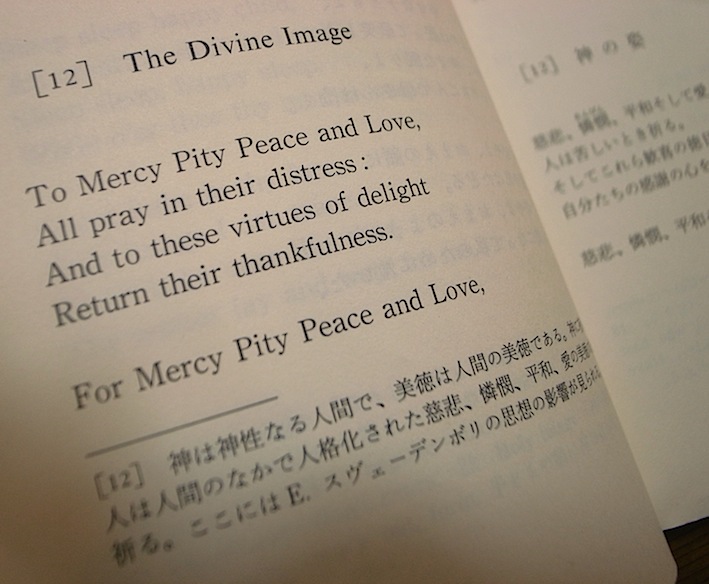510: 名無しの心子知らず 2008/06/21(土) 12:32:58 ID:FoFau0+r
学校で姪の友達のAちゃんが男子のBにいじめられていたらしい。
Aちゃんはちょっと家庭に事情があってそれをネタに馬鹿にされていたとか。
で、ある日それを見ていたC君が怒ってBを殴り飛ばして怪我をさせてしまった。
Bの親がちょっとモンペア的な人達で、結構大事になりBとその両親、C君と父親
そしてその場にいた姪とAちゃんが校長室で事情聴取を受けることになった。
姪はAちゃんがいじめられていたことを一生懸命訴えたらしいが、Bの両親の
キレ具合に押されて結局C君が一方的に悪いという雰囲気に。どうも先生は
Aちゃんがイジメられていたの事実を認めたくないため、歯切れが悪かったみたい。
一通りの事情を聞き終わったC君の父親は息子に「本当にお前が殴ったんだな」と
確認後、フルスイングでC君を平手打ち!C君は口から血を出してぶっ倒れる。
で、B親子に「申し訳ありませんでした」と謝罪。その父親のあまりの迫力に
B親子はしどろもどろになり「まあ今回は…ムニャムニャ…」って感じで終了。
校長室を出た後、どうしても納得できない姪はC君の父親を捕まえて
「C君は悪くないのに叩くなんてひどいです!」と詰め寄ったらしい。
すると父親はC君に向かって「お前、俺に叩かれると分かっていたらどうした?」
それに対してC君は「あれは絶対許せない。やっぱりBを殴ったと思う。それが
理由で自分が殴られるのは仕方ない。」と即答したとか。それを聞いた父親は
「それでこそ俺の子だ。」と心底嬉しそうに言うと姪に軽く会釈をして去ったとか。
その後、BはAちゃんをいじめるのをやめたらしい。感動とかとはちょっと違うけど
世の中捨てたもんじゃないと思った一件。
C君、漢だねぇ。
担任や校長の(校長は話に出てこないが)事なかれ主義的な態度が気に掛かる。
ともあれC君、男を上げたぜ。
よっニッポン男児!
そうですね。学校がイジメを認めないというニュースは良く見ますが本当に対応してくれないみたいです。
どうしても「うるさい親の意見」が優先になるみたい。うちの娘も行く予定の学校なのでちょっと心配。
あと姪は「C君の父親はひどいよね」という感じだったのでまだ父親の気持ちはわからないようでした。
なにはともあれ姪にとってC君が「気になる男の子」になったのは確かなようです。
C君やべぇ。
まじで悟りの境地。
惚れた。。
なんとなくだけどAちゃんの家庭の事情ってのはお母さんに関する内容で
C君側はお父さんしか来なかったことから考えてAちゃんとよく似た境遇だったのかもしれない。
まあ想像の域を出ないけど、もしそうなら絶対許せないとブチ切れたのも納得かな。
いや単純にC君はAちゃんを好きだったんでしょ。
姪っ子涙目wwww
もともとBのやり方が気に入らなかったのかもよ。
昔、ちょっと障害のある女の子がいたのね。障害自体は軽いもので日常生活にはほとんど支障がなかったし
その子の担任が「差別・イジメは絶対許さない」ってタイプだったのでクラスでは楽しくやってたの。
ところが些細な理由から他のクラスの男子にイジメられるようになっちゃったのね。身体のことをネタに…
で、ある日同じクラスの男の子がそれを見つけてイジメていた3人相手に大喧嘩。1人に怪我をさせちゃった。
元々あまり素行の良くない子だったので、退学か?ってくらいまで問題になったんだけど、その担任が理由を聞いて
男の子を無茶苦茶擁護して、結局イジメていた連中は女の子に謝罪、男の子は停学一週間で済んだの。
停学中、担任は毎日男の子に家に行っていたんだけど停学最後の日に男の子に向かって
「怪我させたのは悪いし停学も自慢にはならないが、お前がイジメを見過ごすような奴じゃなくて本当に嬉しかった。
立場上『よくやった』とは言えないが許してくれ」って言ったんだって。
その男の子は「堂々と学校サボれたんだからラッキーだったよw」って笑ってたらしいけどね。
私と旦那の昔話でした。チラ裏スマソ。
「…ノロケかよ!!!」
と思ってしまうと、なんかモヤッとするよなぁorz いや、いい話なんだけど。
夫の父親は昔気質の職人で典型的な口より手が先に出るタイプ。昔、夫がクラスの女の子をいじめたことがあって
そのことが父親にばれた時それこそ顔の形が変わるくらいに殴られたらしい。夫曰く
「なにが辛かったかって殴られたことよりも、いつもなら必ず途中で仲裁してくれた母がそのときばかりは俺が
どれだけ殴られても最後まで助けてくれなかったことだな。あーこりゃマズイことをしたと心底反省したよ。」
それから夫には「女の子には優しく」がインプットされたみたいです。>>510 のBや>>524の3人組ももしかしたら
その事件後は女の子に対する態度が変わったんじゃないかなとちょっと期待してます。





 2017年03月30日 01:06
2017年03月30日 01:06 


 誠二郎がついに公開!
誠二郎がついに公開!