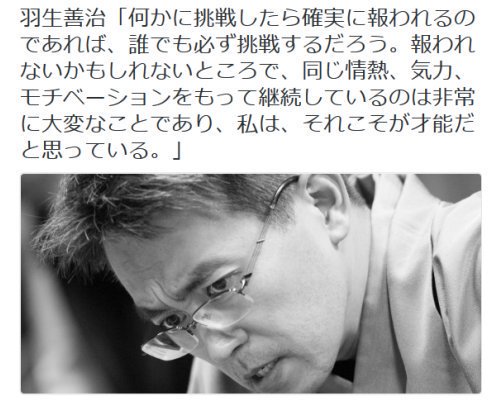ある仏教書を読んでいると、次のような章・節タイトルに出会った。
「生命を生かしているもの」
「だれに生かされているのか」
仏教の本を読んでいて、このタイトル。
誰がどう考えてもこの章には、「宗教」じみた、「説教」くさい話が書かれているのだろうと考える。
ところがこの著者は、「神さまでしょうか、なにか外部の存在でしょうか」と問いかけながら、次のように書くので、笑ってしまう。
わたしたちを生かしているものは、「不満」なのです。不満が、わたしたちを生かしているのです。/不満が「ああしなさい、こうしなさい」と命令して、わたしたちの生きるパターンを形づくっているのです。不満は、エンジンのようなものです。ジェット機が動くためには、エンジンが必要でしょう。いくら大きな両翼がついていても、エンジンがなければ一ミリたりとも動きません。(A・スマナサーラ『わたしたち不満族』国書刊行会p.44-45、強調は原文)
さすが仏教書!
無神論としての、そして精神コントロールの宗教としての、面目躍如である。

- 作者: アルボムッレスマナサーラ,Ven Alubomulle Sumanasara
- 出版社/メーカー: 国書刊行会
- 発売日: 2007/03/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
その上、「スリランカ初期仏教長老」の肩書を持つこの著者は、「満足は『死』を意味する」として、
「生きることに満足した」なら、生きることができなくなり、生きることが終了します。人生に満足したということは、人生が終わったということです。やることもないし、がんばれなくなります。/これは冗談ではなく、ほんとうに停止するのです。つまり「死」なのです。すべての機能がストップするのです。(スマナサーラ同書p.38)
「満足すること」と「生きること」は敵同士です。(同p.42)
と説く。
ちなみに、最も原初的な欲望、例えば食べてもまた食べたくなる、セックスしてもまたセックスしたくなる、というのは、動物として生き残った人間(ホモ・サピエンス)というものの自然選択の結果であり、バグではなく仕様なのだ、というのはロバート・ライト『なぜ今、仏教なのか』(早川書房)で読んだ(以下の引用に出てくる「章」は同書の章)。
人間は目標を達成することで、長続きする満足が得られると期待しすぎる傾向がある。この錯覚とそこから生じるあくなき欲望という心の傾向は、自然選択の産物と考えると納得がいくが(1章を参照)、かならずしも生涯にわたる幸せの秘訣ではない。(ライト同書p.329)
ドゥッカは、普通に生きていれば容赦なくくり返しやってくる人生の一部だ。ドゥッカを従来どおり純然たる「苦しみ」と訳すだけではそれを実感しにくいが、「不満足」という大きな要素を含めて訳すとよくわかる。人間をはじめ生物は、自然選択によって、ものごとが(自然選択の観点から)「よりよく」なるような方法で環境に反応するように設計されている。つまり、生物はほとんどいつも、楽しくないこと、快適でないこと、満足できないことを探して地平を見渡しているようなものだ。そして満たされないことは必然的に苦しみをともなうため、ドゥッカに不満足が含まれると考えることは、結局、苦しみという意味でのドゥッカが人生に浸透しているという思想の信憑性を高めることになる(1章、3章を参照)。(ライト同前)
四聖諦で明らかにされるドゥッカの原因――タンハー(「渇き」「渇愛」「欲望」などと訳される)――は、進化を背景にすると納得がいく。タンハーは、どんなものに対する満足も長くつづかないように自然選択が生物に植えつけたものといえる(1章を参照)。(ライト同前)