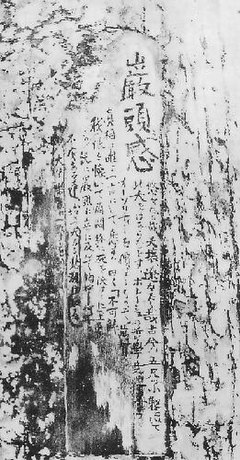アメリカにおける自由と統制
アメリカの話をしようと思う。自由を論じるときにどうしてアメリカの話をするのかと言うと、私たち日本人には「自由は取り扱いのむずかしいものだ」という実感に乏しいように思われるからである。私たちは独立戦争や市民革命を経由して市民的自由を獲得したという歴史的経験を持っていない。自由を求めて戦い、多くの犠牲を払って自由を手に入れ、そのあとに、自由がきわめて扱いにくいものであること、うっかりすると得た以上に多くのものを失うかも知れないことに気づいて慄然とするという経験を私たちは集団的にはしたことがない。「自由」はfreedom/Liberté/Freiheitの訳語として、パッケージ済みの概念として近代日本に輸入された。やまとことばのうちには「自由」に相当するものはない。ということは、自由は土着の観念ではないということである。
私たちはややもすると私たちは「自由というのはすばらしいものである」「全力を尽くして守らなければならないものである」ということを不可疑の前提にして、そこから議論を出発させる。けれども、そうすると、自由に制限を加えようとする政治的立場が理解できなくなる。自由を恐れるという発想が理解できなくなる。自由を制限しようとする者はただひたすらに「邪悪な権力者」にしか見えない。だから、市民が語る自由論は「どうやって権力者の干渉を排して、自由を奪還するか」という戦術論に居着いてしまう。私たちの社会で自由についての思索が深まらないのはこの固定的なスキームから出ることができないせいではないか。
J・S・ミルの『自由論』(1855年)はアメリカ合衆国建国の歴史的実験を間近に観察した上でなされた考察である。私たちがまず驚くのは、ミルの最初の主題が「社会が個人に対して当然行使してよい権力の性質と限界」(J.S.ミル、『自由論』、早坂忠訳、『世界の名著33』、中央公論社、1967年、215頁) だということである。どこまで市民的自由を制限することが許されるのか。ミルはそう問題を立てているのである。
私たちの国では、そういう問いから自由について語り始めるという習慣はない。私たちの社会では、市民は「個人が行使できる自由の拡大」について語り、統治者は「政府が行使できる権力の拡大」について語る。話はまったく交差しない。
統治機構はどこまで市民的自由を制限できるのか、制限すべきなのか、それがミルの自由論の一つの論点である。こういう問いは市民革命を経験し、政府を倒し、統治機構を手作りした経験のある市民にしか立てることができない。
市民革命以前の人民にとって、支配者は「民衆とつねに利害が相反」する存在であった。だから、人民は支配者の権力の制限についてだけ考えていればよかった。しかし、民主制を市民が打ち立てた後、理論上は人民の代表が社会を支配することになった。支配者の利害と意志は、国民の意志と利害と一致するという話になった。政府の権力は「集中化され行使しやすい形にされた国民自身の権力にほかならないのだ」(同書、217頁) ということになった。
民主制以前だったら、空想的にならそう語ることもできただろう。けれども、実際に市民革命を行って、民主制を実現してしまったら、話はそれほど簡単ではないことがわかった。「権力を行使する『民衆』は、権力を行使される民衆と必ずしも同一ではない」(218頁) からである。
代議制民主制のふたを開いてみたら、そこで「民衆の意志」と呼ばれているものは「実際には、民衆の中でもっとも活動的な部分の意志、すなわち多数者あるいは自分たちを多数者として認めさせることに成功する人々の意志」(218頁) だったからである。「民衆がその成員の一部を圧迫しようとすることがありうるのである。」 (218頁)
これは市民革命をした経験のある者にしか語れない知見だと思う。
支配者対人民という二項対立で話が済むうちは簡単だった。だが、近代民主制のアポリアはその先にあった。市民革命を通じて民主制を実現してみたら、予想もしていなかったことが起きた。最も活動的な民衆の一部がそれほど活動的でない他の民衆の自由を制約しようとし始めたのである。「民衆による民衆の支配」という予想していなかったことが起きた。
さて、どのようにして民主制の名においてそのような事態を制御することができるのか? 社会が個人に対して行使してよい権力の性質と限界はいかなるものか?
これが170年ほど前にミルによって定式化され、いまに至るまで決定的な解を見出すことができずにいる自由をめぐる最大の論件である。
繰り返すが、私たちの国では、そのような問いが優先的に気づかわれるまでに市民社会が成熟していない。現に、「多数者の専制」が「社会が警戒することが必要な害悪の一つ」(219頁) であるという認識は日本国民の間では常識としては登録されていない。だから、「選挙に勝ったということは、民意の負託を受けたということだ」「選挙に勝って、禊が済んだ」というような言葉を政治家たちが不用意に口にし、メディアがそのまま無批判に垂れ流すということが起きる。ミルはそういう考え方が民主制に致命傷を与えるということをつとに170年前に指摘していたのである。
ミルの書物は明治初年に日本に翻訳されて、ずいぶん広く読まれたはずである。しかし、読まれたということと血肉化したということはまったく別の話だ。私たちはトクヴィルやハミルトンやミルが生きた18~19世紀の欧米市民社会よりもはるかに民主制の成熟度の低い社会にいまも暮らしているのである。そのことをまず認めよう。
自由は端的に自由として、あたかも自然物のようにそこにあるわけではない。それは近代市民社会においては、「どの程度までなら制限してよいものか」という問いを通じて、欠性的にその輪郭を示してゆく。市民的自由と社会的統制はどこかで衝突する。私的自由と公共の福祉はどこかで衝突する。自由と平等はどこかで衝突する。そのときに、どのあたりが適切な「落としどころ」になるかは原理的には決することができない。汎通的な「ものさし」は存在しない。「適度」なところを皮膚感覚や嗅覚で探り当てなければならない。そして、そういう精密な操作ができるためには、どうしても一度は自分の手で「なまものとしての自由」を取り扱ってみなければならない。そして、私たちにはその経験がない。
私が本稿で建国期のアメリカの事例を検討するのは、その時代のアメリカ人はまことに誠実に「統制と自由」の問題で悩んだと思うからである。ある問題に取り組むときに生産的な知見をもたらすのは、多くの場合、その問題を解決した(と思っている)人よりも、現にその問題で苦しんでいる人である。
独立宣言(1776年)から合衆国憲法の制定(1787年)までには11年間のタイムラグがある。それは新しく創り出す国のかたちについての国民の合意形成が困難だったということを意味している。一方に連邦政府にできるだけ大きな権限を委ねようとする「中央集権派(フェデラリスト)」がおり、他方に単一政府の下に統轄されることを嫌い、州政府の独立性を重く見る「地方分権派」がいた(Stateを「州」と訳すことが適切なのかどうか私にはわからない。以下に引く『ザ・フェデラリスト』の訳文では「州」と「邦」が混用されている)。
中央政府に必要な権限を付与するために人民はみずからの自然権の一部を譲渡しなければならない。これはホッブズ、ロック以来の近代市民社会論の常識である。この原理に異を唱える市民は近代市民社会にはいないはずである。だから、問題は、どの機関に、どの程度の私権を譲渡するかなのである。ことは原理の問題ではなく、程度の問題なのである。原理の問題なら正否の決着がつくということがあるが、程度の問題に「最終的解決」はない。それは必ずオープン・クエスチョンとして残される。アメリカ合衆国がその後世界最強国になったのは、彼らが統治の根本原理を採択するとき、統制か自由かのいずれを優先させるかをついに決しかねたことの手柄だと私は思っている。人間は葛藤のうちに成熟する。国も同じである。解決のつかない、根源的難問を抱え込んでいる国は、単一の無矛盾的な統治原理に統制された社会よりも生き延びる力が強い。
『ザ・フェデラリスト』は合衆国憲法制定直前に、世論を連邦派に導くためにジョン・ジェイ、ジェイムズ・マディソン、アレグザンダー・ハミルトンの三人によって書かれた。直接の理由はジェイの記すところによれば、「一つの連邦の中にわれわれの安全と幸福を求めるかわりに、各邦をいくつかの連合に、あるいはいくつかの国家に分割することにこそ、われわれの安全と幸福を求めるべきであると主張する政治屋たちが現われだした」 からである。(『ザ・フェデラリスト』、斎藤真訳、『世界の名著33』、317頁)
アメリカは一体でなければならない。「この国土を、非友好的で嫉妬反目するいくつかの独立国に分割すべきではない」(同書、318頁) というのがフェデラリストたちの立場であった。
さて、このとき連邦に統合されることに反対した人々が掲げたのが「自由」の原理だったのである。連邦政府に強大な権限を付与することは、州政府の自由を損ない、さらには市民の自由を損なうことだ、と。だから、まことにわかりにくい話になるが、このとき「自由」の対立概念は「連邦」だったのである。明らかなカテゴリーミステイクのように思われるが、「自由」と「連邦」はゼロサムの関係にあるという考え方がその時点ではリアリティを持っていたのである。そのことは次のジェイの文章から知れる。
「同じ祖先より生まれ、同じ言葉を語り、同じ宗教を信じ、同じ政治原理を奉じ、(...)一体となって協議し、武装し、努力し、長期にわたる血なまぐさい戦争を肩を並べて戦い抜」いたアメリカ人は独立戦争のあと「13州連合(the Confederation)」を形成した。しかし、この政体は戦火の下で急ごしらえされたものであったので、「大きな欠陥」があった。
「自由を熱愛すると同様、また連邦にも愛着をもちつづけていた彼らは、直接には連邦(ユニオン)を、間接には自由を危殆ならしめるような危険性があることを認めたのである。そして、連邦と自由とを二つながら十分に保障するものとしては、もっとも賢明に構成された全国的(ナショナル)政府(ガバメント)しかないことを悟り(...)憲法会議を召集したのである。」(318-9頁)
よく注意して読まないと読み飛ばしそうなところだが、ここでジェイは連邦と自由を両立させるのは簡単な仕事ではないということを認めているのである。自由だけを追求すれば、連邦は存立できない。連邦が存立できなければ、自由は失われる。だから、自由と連邦を「二つながら十分に保障する」工夫が必要なのだ。そのとき、連邦がなければ自由が危機に瀕することの論拠にジェイが選んだのは、「侵略者があったときに誰が戦争をするのか?」という仮定だった。
独立直後の合衆国は英国、スペイン、フランス、さらには国内のネイティヴ・アメリカンとの軍事的衝突のリスクを抱えていた。仮にある邦がこれらの国と戦闘状態に入ったときに、戦闘の主体は誰になるのか? 邦政府が軍事的独立を望むのなら、邦政府はとりあえずは単独で外敵に対処しなければならない。
「もし、一政府が攻撃された場合、他の政府はその救援に馳せ参じ、その防衛のためにみずからの血を流しみずからの金を投ずるであろうか?」(329頁)。
ずいぶんと生々しい話である。私たちはいまのアメリカしか知らないから、例えばヴァージニア州が外国軍に攻撃されたときにコネチカット州が「隣邦の地位が低下するのをむしろよしとして」傍観するというような事態を想像することができない。あるいは「アメリカが三ないし四の独立した、おそらくは相互に対立する共和国ないし連合体に分裂し、一つはイギリスに、他はフランスに、第三のものはスペインに傾くということになり」(330頁)、大陸で代理戦争が始まったらどうするというようなことを想像することができない。しかし、ものごとを根源的に考えるというのは、その生成状態にまで立ち戻って考えるということである。いまのようなアメリカになる前の、これから先何が起きるかまだ見通せないでいる時点に立ち戻って、そこで自由と連邦の歴史的意味を吟味しなければならない。
外敵の侵略リスクを想定して、その場合に自由を守るためには、邦政府に軍事的フリーハンドを与えるべきか、それとも連邦政府に軍事を委ねるべきか、いずれが適切なのか。それがジェイの提示した問いであった。
連邦政府に軍事を委ねるというのは常備軍を置くということである。だが、地方分権派は常備軍というアイディアそのものにはげしいアレルギーを示した。世界最大の軍事力を持ついまのアメリカを知っている私たちにはにわかには信じにくいことだが、合衆国憲法をめぐる最大の論争は実は「常備軍を置くか、置かないか」をめぐるものだったのである。
地方分権派が常備軍にはげしいアレルギーを示したのは、常備軍は簡単に権力者の私兵となって市民に銃口を向けるという歴史的経験があったからである。これは独立戦争を戦った人々にとっては、恐怖と苦痛をともなって回想されるトラウマ的記憶であった。たしかに英国軍は国王の意を体して、植民地人民に銃を向けた。それに対して、自らの意志で銃を執って立ち上がった「武装した市民(militia)」たちが最終的に独立戦争を勝利に導いた。だから、戦争をするのは職業軍人ではなく、武装した市民でなければならない。これはアメリカ建国の正統性と神話性を維持し続けるためには譲ることのできない要件だった。現に、独立宣言にははっきりとこう明記してあった。
「われわれは万人は平等に創造され、創造主によっていくつかの譲渡不能の権利、すなわち生命、自由、幸福追求の権利を付与されていることを自明の真理とみなす。(...)いかなる形態の政府であろうと、この目的を害するときには、これを改変あるいは廃絶し、新しい政府を創建することは人民の権利である(it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government)」
独立宣言は人民の武装権・抵抗権・革命権を認めている。独立戦争を正当化するためにはそれを認めることが論理的に必須だったからである。だから、独立戦争直後に制定されたペンシルヴェニアとノース・カロライナの邦憲法には「平時における常備軍は、自由にとって危険であるので、維持されるべきではない」と明記されている。ニュー・ハンプシャー、マサチューセッツ、デラウェア、メリーランドの邦憲法はいくぶん控えめに「常備軍は自由にとって危険であるので、議会の承認なしに募集され、あるいは維持されるべきではない」としている。
「常備軍は自由にとって危険である」というのは建国時のアメリカ市民の「気分」ではなく、「成文法」だったのである。そのことを忘れてはならない。
それに対して、フェデラリストたちは外敵の侵入リスクをより重く見た。ことは「国家存亡の危機」にかかわるのである。ハミルトンは「国防軍の創設、統帥、意地に必要ないっさいのことがらに関しては、制約があってはならない」 と主張した。(346頁)
強大な国防軍を創設すべきか、常備軍は最低限のもの、暫定的なものにとどめておくべきか。この原理的な対立は結局、憲法制定までには解決を見なかった。合衆国憲法は常備軍反対論に配慮して、常備軍の保持は憲法違反であると読めるような条項を持つことになったからである。連邦議会の権限を定めた憲法8条12項にはこうある。
「連邦議会は陸軍を召集し、支援する権限を有する。ただし、このための歳出は二年を越えてはならない。」
常備軍はどの国でもふつう行政府に属する。しかし、合衆国憲法は陸軍の召集と維持を立法府に委ねた。さらも二年以上にわたって軍隊の維持費として継続的な支出をすることを禁じた。「これは、よくみると、明らかな必要性がないかぎり軍隊を維持することに反対する重要にして現実的な保障とも思われる配慮なのである」 とハミルトンは8条12項について書いている。(351頁)
アメリカが常備軍を禁じた憲法を持っていることを知っている日本人は少ない。改憲派は、憲法第九条二項と自衛隊の「矛盾」を指摘して、「憲法と現実の間に齟齬があるときは、現実に合わせて改憲すべきである」と主張するが、彼らが常備軍規定について合衆国憲法と現実の間には深刻な齟齬があるので改憲すべきであると米国政府に献策したという話を私は寡聞にして知らない。私はむしろ憲法条項と現実の間に齟齬があることがアメリカの民主制に活力と豊穣性を吹き込んでいると理解している。アメリカ市民は憲法8条12項を読むたびに、「建国者たちは何のためにこのような条項を書き入れたのか?」という建国時における統治理念の根源的な対立について思量することを余儀なくされるからである。正解のない問いにまっすぐ向き合うことは、教えられた単一の正解を暗誦してみせるよりは、市民の政治的成熟にとってはるかに有用である。
常備軍についての原理的対立は憲法修正第二条の武装権をめぐる対立において再演される。1789年、憲法制定の二年後に採択された憲法修正第二条にはこう書かれている。
「よく訓練されたミリシアは自由な邦の安全のために必要であるので、人民が武器を保持し携行する権利は侵されてはならない。」
修正第二条の文言を確定するときにどのような議論があったのかはつまびらかにしないが、これが邦の手元に軍事力を残したい地方分権派と軍事力を連邦政府の統制下に置きたい中央集権派の妥協の産物であったことはわかる。というのも、憲法制定時点でフェデラリストたちが最も懸念していたのは、外敵の侵攻と並んで邦政府と連邦政府との軍事的対立だったからである。ハミルトンははっきりと「内戦」のリスクに言及している。
「各州政府が、権力欲にもとづいて、連邦政府と競争関係に立つことはきわめて当然の傾向であり、連邦政府と州政府が何らかのかたちで争うとなると、人々は(...)州政府に必ず加担する傾向があると考えてしかるべきであることは、すでに述べた。各州政府が(...)独立の軍隊を所有することによって、その野心を増長せしめられることにでもなれば、その軍事力は、各州政府にとって、憲法の認める連邦の権威に対して、あえて挑戦し、ついにはこれをくつがえそうという、あまりにも強力な誘惑となり、あまりにも大きな便宜を与えるものになろう。」(356頁)
ミリシアを邦が自己裁量で運用できる軍事力として手元にとどめたい地方分権派と、できるだけ軍事力を連邦政府で独占したいフェデラリストとのきびしい緊張関係のなかで憲法は起草され、憲法修正が書き加えられた。原則として常備軍を持たないとしたこと、軍隊の召集・維持の権限を立法府に与えたこと、市民の武装権を認めたこと、これらは連邦派の側からすれば不本意な譲歩だっただろう。連邦派の抵抗の跡はかろうじて「よく訓練された(well regulated)」と「自由な邦の安全のため(the security of a free state)」という二重の条件に残されている。
ミリシアはのちにNational Guard に改称された。日本語では「州兵」と訳されるが、これは独立戦争の英雄だったラファイエット将軍が母国でフランス革命の時に率いたGarde Nationaleに敬意を表して改称されたのであって、原義は「国民警備兵」である。一方で武装した市民たち自身はいまも「ミリシア」を名乗り続けている。2021年1月20日のバイデン大統領の就任式では、「武装したトランプ支持者」の乱入に備えて「州兵」15000人が配備されたと日本のメディアは報じたけれど、彼らは「暴徒と兵士」でも「デモ隊と警官」でもなく、いずれも主観的には「ミリシア」だったのである。
アメリカの政治文化では、原理主義的な首尾一貫性よりも、そのつどの状況にすみやかに最適化する復元力(resilience)が高く評価される。鶏さ先か卵が先かわからないが、この政治文化の形成に、アメリカが建国時点から二種の統治原理に引き裂かれていたという歴史的事実が与っていると私は思う。
トランプ以後、アメリカの国民的分断を嘆く人が多いが、実際にはアメリカは建国時点から、統一国家なのか連邦なのか、どちらにも落ち着かない両義的性格を持ち続けてきた。その意味では二つの統治原理の間でつねに引き裂かれてきたのである。分断は今に始まった話ではない。
両院から成る立法府の構成も二つの原理の妥協の産物である。下院定員は人口比で決まるので、下院議員は「その権限をアメリカ国民から直接ひき出している」 と言ってよいが、上院議員は各州2名が割り当てられているので、邦を代表している。日本人には理解しにくい大統領選挙人制度も、大統領を選挙するのはあくまで邦であって、国民ではないということを示している。アメリカは「統一国家的性格と同様に、多くの連邦的性格をもった一種の混合的な性格」 を具えた国家なのである。
そこからアメリカにおける自由の特殊な含意が導かれる。絶対自由主義者は「リバタリアン(libertarian)」を名乗る。彼らは公権力が私権・私有財産に介入することを認めない。だから、徴兵に応じない(自分の命をどう使うかは自分が決める)、納税もしない(自分の資産をどう使うかは自分が決める)。ドナルド・トランプはリバタリアンだったので、四度にわたって徴兵を逃れ、大統領選のときも税金を納めていないことを公言してはばからなかった。そういう人物が大統領になって、公権力のトップに君臨することができるのは、公権力が市民的自由に介入することへの強い拒否がアメリカの政治文化の一つの伝統だからである。
トランプ統治下のアメリカでCOVID-19の感染拡大が止まらず、世界最高レベルの医療技術を持った国であるにもかかわらず、感染者数でも死者数でも世界最多を記録したのは、医療についても、公権力の介入を嫌う人がそれだけ多かったからである。
『トランピストはマスクをしない』というのは町山智浩のアメリカ観察記のタイトルだが、このタイトルは疾病のリスクをどう評価し、どう予防し、どう治療するかという、本来なら科学的に決定されるはずのことがらが「自由か統制か」という政治理念の選択問題にずれこんでしまうアメリカの特異な風土を言い当てている。
感染症は、全住民が等しく良質な医療を受ける医療システムを構築しないかぎり終息させることができない。だが、そのためには公権力が患者の治療やワクチン接種といった医療サービスを無償で提供する必要がある。医療を商品と考え、金がある者は医療が受けられるが,金がない者は受けられないという市場原理を信じる人たちの眼には、これは医療資源を公権力が恣意的に再分配する社会主義的「統制」に映る。
だから、自由と平等は実は両立させることがきわめて難しい政治理念なのである。私たちはフランス革命の標語に慣れ親しんでいるせいで、「自由・平等・博愛」がワンセットのものだと考えているけれど、それは違う。平等は、公権力が強力な介入を行って、富める者の私財の一部を奪い、力ある者の私権の一部を制限して、それを貧しい者、弱い者に再分配することなしには、絶対に成就しないからである。平等を実現しようとすれば、必ずある人たちの自由は損なわれる。それも、その集団において相対的に豊かで、力があって、より活動的な人たちの自由が損なわれる。
ミルの論点を思い出そう。平等は「民衆の中でもっとも活動的な部分」の私権を制限し、私財を没収することによってしか実現されない。そして、この「活動的な部分」はミルによればまさに「自分たちを多数者として認めさせることに成功」したがゆえに「活動的」たりえた人々なのである。平等は「多数の市民」の自由を公権力が制約するという図式においてしか実現しない。そして、当然ながらそのことに「多数の市民」は反対するのである。
いま、世界の最も富裕な8人の資産は、最も貧しい36億人が保有する資産と同額である。それくらいに富は偏在しているわけだけれども、その貧しい36億人のうちにおいてさえ、ジェフ・ベソスやビル・ゲイツとともに自分は「多数者」の側にいると信じて、公権力が私権を統制し、私財を公共財に付け替えることに反対する人たちが大勢いる。それは富豪であるトランプの支持基盤が「ホワイト・トラッシュ」と呼ばれる白人貧困層であったことに通じている。彼らは平等よりも自由の方を重く見る政治的伝統を継承しているのである。
その「自由主義」思想は「独立宣言」に源流を持っている。「独立宣言」の先ほど引いた「抵抗権」を保障した箇所の直前にはこう書いてあるからだ。
「われわれは、以下の真理を自明のものと信じる。すなわち、すべての人間は平等なものとして創造され、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている、と。(We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness)」
すべての人間は平等なものとして、創造主によって創造されたのである。ここでは、平等はすべての人間の初期条件であって、未来において達成すべきものとしては観念されていない。政府は生命、自由、幸福追求の権利を確保するために創建されたものであって、平等の実現は政府の仕事にはカウントされていない。平等はすでに創造主によって実現している。だから、政府が配慮すべきは人民の生命と自由と幸福追求に限定されるのである。「すべての人間は平等なものとして創造されている」と宣言されてから奴隷制が廃絶されるまでに86年かかり、公民権法が成立するまでにさらに101年かかり、それから半世紀以上経って、いまだにBlack Lives Matter が黒人に白人と平等の人権を求めなければならないのは、平等の実現はアメリカの建国時でのアジェンダに含まれていなかったからである。そして、その政治文化はいまも生き続けている。
長くなり過ぎたので、もう話を終える。市民的自由と社会的統制の間の葛藤に「最終的解決」はない。私たちに必要なのは「適度」を探り当てる経験知の蓄積である。自由を扱う技術の習得にはそれなりの時間と手間を覚悟しなければならないのである。
(2022-02-22 11:47)