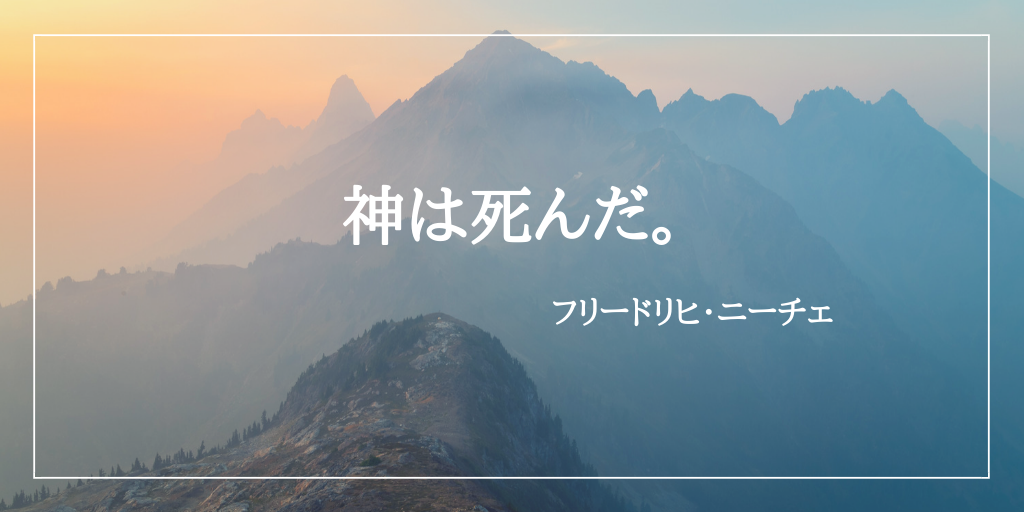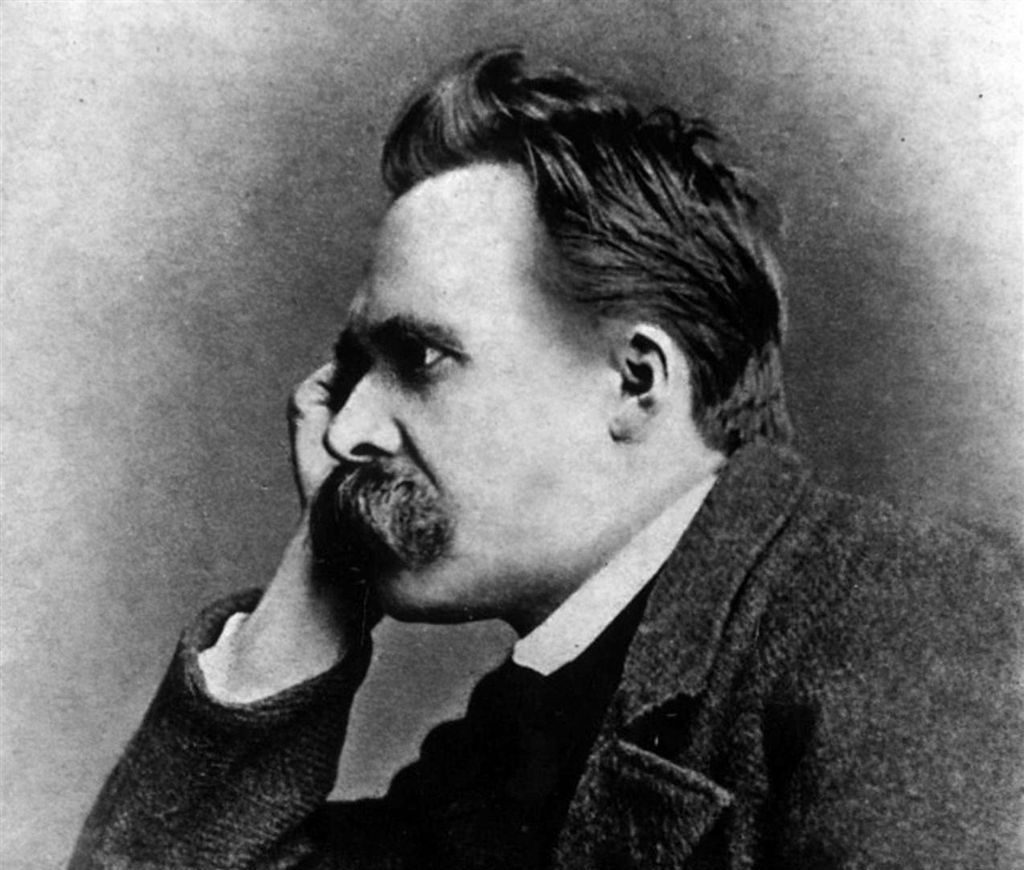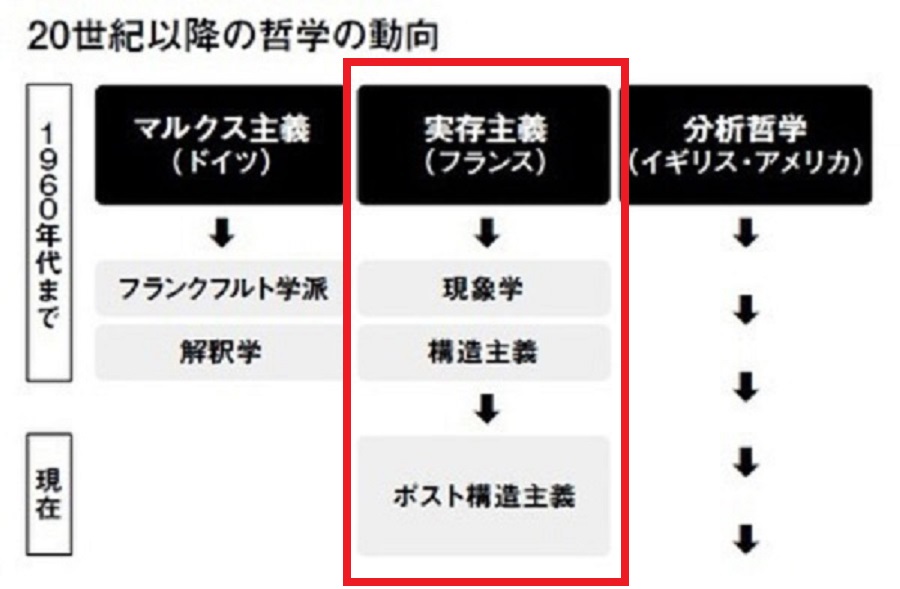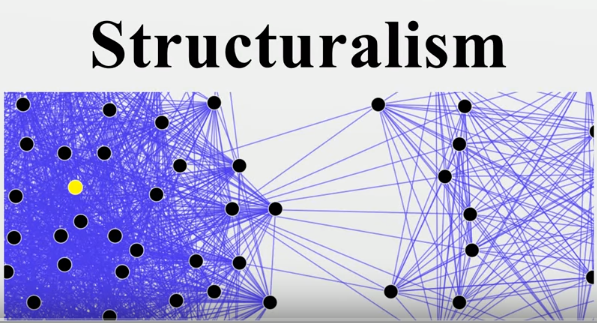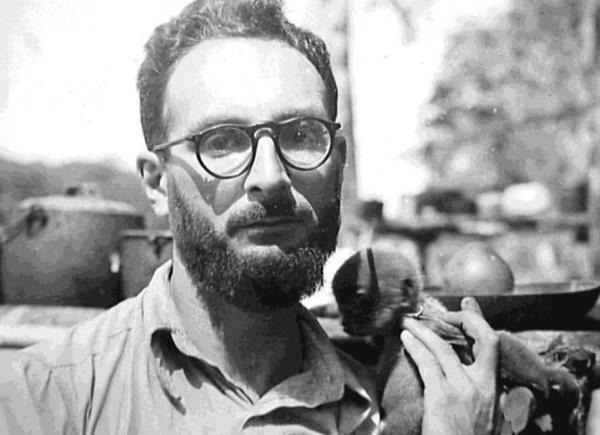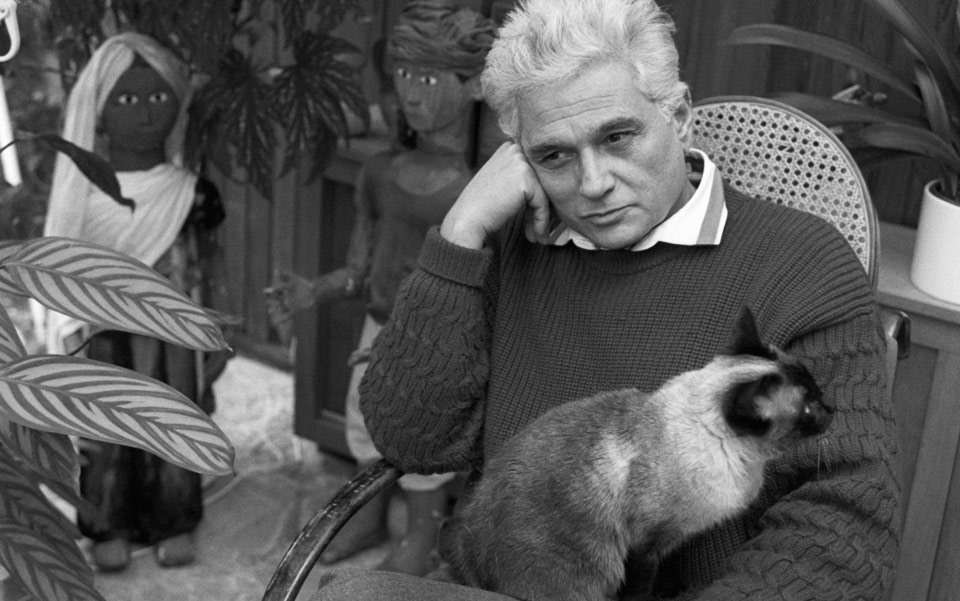考察の対象が思いつかないので、アリストテレスの思想の一部をウィキペディアから転載しておく。その自然科学についての思想は現代では考察に値しないだろう。
哲学とは煎じ詰めれば「AはBである」という命題(真偽の判断が可能な文)になると思うが、その述語を分類したのが面白い。
すなわち「実体」「性質」「量」「関係」「能動」「受動」「場所」「時間」「姿勢」「所有」まあ、この分類で妥当かどうか、他の要素もあるとは思うが、かなり思考のガイドラインにはなる分類だと思う。
つまり、何かを考えるとき、その対象の
1:実体は何か
2:性質は何か
3:量はどうか
4:他者との関係はどうか
5:能動的か
6:受動的か
7:時間とどう関係するか
8:姿勢はどうか
を考えるわけだ。まあ、これは私が下の記述から今適当に考えたものである。創造や創作や研究を試みる際のいい手引きになるのではないか。たとえば、小説でキャラを作る場合だと「量」とは体型や体格や体重になるだろうし、内面的な「器量」「包容力」でもあるわけだ。また、たとえばシャーロック・ホームズの「本質(実体)」とは何かと言えば「思考機械で、かつ冒険家」だろう。
(以下引用)
形而上学(第一哲学)
原因について
アリストテレスの師プラトンは、感覚界を超越したイデアが個物から離れて実在するというイデア論を唱えたが、アリストテレスはイデア論を批判して、個物に内在するエイドス(形相)とヒュレー(質料)の概念を提唱した。
また、アリストテレスは、世界に生起する現象の原因には「質料因」と「形相因」があるとし、後者をさらに「動力因(作用因)」、「形相因」、「目的因」の3つに分けて、都合4つの原因(アイティア aitia)があるとした(四原因説)(『形而上学』A巻『自然学』第2巻第3章等)。
事物が何でできているかが「質料因」、そのものの実体であり本質であるのが「形相因」、運動や変化を引き起こす始源(アルケー・キネーセオース)は「動力因」(ト・ディア・ティ)、そして、それが目指している終局(ト・テロス)が「目的因」(ト・フー・ヘネカ)である。存在者を動態的に見たとき、潜在的には可能であるものが、素材としての可能態(デュナミス)であり、それと、すでに生成したもので思考が具体化した現実態(エネルゲイア)とを区別した。
万物が可能態から現実態への生成のうちにあり、質料をもたない純粋形相として最高の現実性を備えたものは、「神」(不動の動者)と呼ばれる。イブン・スィーナーら中世のイスラム哲学者・神学者や、トマス・アクィナス等の中世のキリスト教神学者は、この「神」概念に影響を受け、彼らの宗教(キリスト教・イスラム教)の神(ヤハウェ・アッラーフ)と同一視した。
範疇論
アリストテレスは、述語(AはBであるというときのBにあたる)の種類を、範疇として下記のように区分する。すなわち「実体」「性質」「量」「関係」「能動」「受動」「場所」「時間」「姿勢」「所有」(『カテゴリー論』第4章)。ここでいう「実体」は普遍者であって、種や類をあらわし、述語としても用いられる(第二実体)。これに対して、述語としては用いられない基体としての第一実体があり、形相と質料の両者からなる個物がこれに対応する。
倫理学
アリストテレスは、倫理学を創始した。 一定の住み処で人々が暮らすためには慣習や道徳、規範が生まれる。古代ギリシャではそれぞれのポリスがその母体であったのだが、アリストテレスは、エートス(住み処)の基底となるものが何かを問い、人間存在にとって求めるに値するもの(善)が数ある中で、それらを統括する究極の善(最高善)を明らかにし、基礎付ける哲学を実践哲学として確立した。
アリストテレスによると、人間の営為にはすべて目的(善)があり、それらの目的の最上位には、それ自身が目的である「最高善」があるとした。人間にとって最高善とは、幸福、それも卓越性(アレテー)における活動のもたらす満足のことである。幸福とは、たんに快楽を得ることだけではなく、政治を実践し、または、人間の霊魂が、固有の形相である理性を発展させることが人間の幸福であると説いた(幸福主義)。
また、理性的に生きるためには、中庸を守ることが重要であるとも説いた。中庸に当たるのは、
- 恐怖と平然に関しては勇敢、
- 快楽と苦痛に関しては節制、
- 財貨に関しては寛厚と豪華(豪気)、
- 名誉に関しては矜持、
- 怒りに関しては温和、
- 交際に関しては親愛と真実と機知
である。ただし、羞恥は情念であっても徳ではなく、羞恥は仮言的にだけよきものであり、徳においては醜い行為そのものが許されないとした。
また、各々にふさわしい分け前を配分する配分的正義(幾何学的比例)と、損なわれた均衡を回復するための裁判官的な矯正的正義(算術的比例)、これに加えて〈等価〉交換的正義とを区別した。
アリストテレスの倫理学は、ダンテ・アリギエーリにも大きな影響を与えた。ダンテは『帝政論』において『ニコマコス倫理学』を継承しており、『神曲』地獄篇における地獄の階層構造も、この『倫理学』の分類に拠っている。 なお、彼の著作である『ニコマコス倫理学』の「ニコマコス」とは、アリストテレスの父の名前であり、子の名前でもあるニコマスから命名された。
政治学
アリストテレスは『政治学』を著したが、政治学を倫理学の延長線上に考えた。「人間は政治的生物である」とかれは定義する。自足して、共同の必要のないものは神であり、共同できないものは野獣である。両者とは異なって、人間はあくまでも社会的存在である。国家のあり方は王制、貴族制、ポリティア、その逸脱としての僭主制、寡頭制、民主制に区分される。王制は、父と息子、貴族制は夫と妻、ポリティアは兄と弟の関係にその原型をもつと言われる(ニコマコス倫理学)。
アリストテレス自身は、ひと目で見渡せる小規模のポリスを理想としたが、アレクサンドロス大王の登場と退場の舞台となったこの時代、情勢は世界国家の形成へ向かっており、古代ギリシアの伝統的都市国家体制は過去のものとなりつつあった。
*夢人注:「ポリティア」について舛添要一は「混合政体」としている。特に根拠は無いが、政治意識のある中産階級を「市民」として、「市民政治」と訳しても良さそうだ。それは「民主政治」とは違って、或る程度の知性と教養を政治参加の必要条件とするわけである。ポリス(都市)の運営が政治(ポリティクス)の起源だろう。奴隷には政治を考える心理的余地は無い。市民に政治参加の資格はある。現代では奴隷としての頭脳しかない人間に選挙権が与えられている。それが民主主義を崩壊させている。
2018/02/28 — そこで、アリストテレスも、現実に可能な最善の制度として、中産階級の人々が中心として運営するポリティア(混合政体)をあげたのである。
文学
アリストテレスによれば、芸術創作活動の基本的原理は模倣(ミメーシス)である。文学は言語を使用しての模倣であり、理想像の模倣が悲劇の成立には必要不可欠である。作品受容の目的は心情の浄化としてのカタルシスであり、悲劇の効果は急転(ペリペテイア)と、人物再認(アナグノーリシス)との巧拙によるという。古典的作劇術の三一致の法則は、かれの『詩学』にその根拠を求めている。