任意団体であれば、何をやっていても問題ない
PTAをめぐる記事とコメントを読んで、問題の整理のために書く。
#PTAやめたの私だ 「入会しません」 ひとりの主婦の静かなる抵抗 
PTA批判について思うこと - 感想文 
PTA批判について思うこと その2 - 感想文 
ぼくが言いたいことは、かんたんに言えば「PTAは必要かどうか」という問題と、「PTAは任意か強制か」という問題を分けて議論せよ、ということ。それだけ。
PTAが任意のボランティアであるという原則を承認するなら、それがどんなにくだらないことをやっている団体であっても、「廃止せよ」などという主張には、まったく道理はない。
「任意のボランティア団体」を「廃止せよ」というのはイコール「禁止せよ」と同じことである。結社の自由をふみにじる行為だ。
そして、PTAの活動が役に立ったという実感を持っている人たちの感情を逆なでするだけで、それこそ何の役にも立たない。
他方で、PTAがどんなに必要な団体であっても、「任意のボランティア」であることを認めるなら、そこには一切参加の義務や強制はありえない。
極端なことを言うけど、例えば子どもが受ける授業に、PTAの役員・委員・会員が講師となるしくみがあったとする。その場合当然、PTAが人を出さなければ、授業はなりたたない。子どもの教育は成り立たない。
しかしそうであっても、PTAが任意のボランティアであるというルールを持っているなら、講師としての労働を強制することができない。学校教育が成り立たないほどの必要性を仮にPTAが抱えていたとしても、参加は強制できないのである。
まあ、ここまで極端なものはないけども、運動会のお手伝いがないと運動会が成り立たないにせよ、子どもたちの臨海学校にいく付き添いがなければ成り立たないにせよ、PTAが任意であることを踏まえれば、義務や強制はあり得ないのである。
「PTA批判について思うこと」を書いた「ねむれないさかな」と言うブロガーの記事には、例えばこうある。
PTAのお手伝いがなければ、わたしのいた学校は、授業参観さえ人手不足で行えないのです。
授業中、職員室はからっぽになります。
事務員さんは数人しかいません。
それでどうして、門を開けっぱなしにした学校の安全が守れるでしょうか。
受付での名札チェックは、子供たちの安全を守るための大切な業務でした。
それはPTAの役割でした。
人手がない学校が悪い、制度が悪い、学校がやれって文句をいうのは簡単です。
でもそれを自分たちでお手伝いすれば、授業参観を開催してもらえる。
だったらやればいいじゃないですか。
http://nemurenai-same.hatenadiary.jp/entry/2017/01/30/174304
そのあとに、わざと「だから参加を強制してもいいんです。」という一文をいれてみる。
PTAのお手伝いがなければ、わたしのいた学校は、授業参観さえ人手不足で行えないのです。
授業中、職員室はからっぽになります。
事務員さんは数人しかいません。
それでどうして、門を開けっぱなしにした学校の安全が守れるでしょうか。
受付での名札チェックは、子供たちの安全を守るための大切な業務でした。
それはPTAの役割でした。
人手がない学校が悪い、制度が悪い、学校がやれって文句をいうのは簡単です。
でもそれを自分たちでお手伝いすれば、授業参観を開催してもらえる。
だったらやればいいじゃないですか。
だから参加を強制してもいいんです。
(赤字の強調は、引用者が恣意的に挿入したもの)
うわー。
こういう主張にしてしまうと違和感ありまくりだな。
世の中では、こういう論だてで、参加が強制されている。
もちろん、この「ねむれないさかな」はそういう主張はしていない。このブロガーによれば、この人がPTA役員をやっていたPTAでは任意加入を明確にする制度改革を行い、さらにできない仕事は断れるようにもなっていたという。
それならば、何の問題もない。
ホント。
任意の団体で自由に断れるようになったそうなのだから、必要だろうが不要だろうが、好きなことをやればいい。どんなにしんどいことを提起したって、任意であれば志願したい人が志願するだけなのだ。
PTAの議論が出た時に、「役に立たない」「不要」というタイプの議論をする人は、気づいていないかもしれないが、裏返せば「役に立てば・必要な団体であれば強制してもいい」というロジックを備えてしまっている危険がある。
任意のボランティア(志願)でやっているものを「廃止しろ」などと誰が言えるだろうか。
俳句のサークルは「役に立たないから禁止しろ」とまったく同じロジックである。
問題の大もとの部分はこれで終わりである。
以下は、単なる付け加え。
読みたい人だけが読めばいい。
現実問題として考えてみると
はい、ではこれから、読みたい人だけが読む部分が始まります。主張の主要な部分はもう終わっているので、ここから先を勝手に読んで「長い」とか言うなよ。別に言ってもいいけど。
現場では、明確に強制じゃなくて、なんとなく義務にされ、いわば「半強制」にされている。断れない雰囲気があるし、やらないと差別されるんだよ、と。
うむ。
そうでもない事例は多く知っているが、他方でそう言う事例も確かにある。
その場合は、必要かどうかという問題ではなく、加入・脱退自由という原則をより明確にして、厳しくそこを徹底することが問題になる。
「こんな団体はいらないからやめちまえ」とはならない。その事業(仕事)を必要だと思う人がいるんだから。その人たちが好き勝手にやる自由を奪うことはできない。
さらにふみこめば、「いや、例えばPTAの協力がなければ運動会サポートや登下校見守りは成り立たないんだから、義務としてやるべきだし、強制していいんだよ」という主張を本気でする人は、かなりの割合でいる(念のためくり返しておくが、先ほど紹介した「ねむれないさかな」というブロガーはこうした主張は一切していない)。
まず原則を言っておく。
くり返すけど、強制はできない。
任意なんだから。
どんなに必要でも、参加は強制できない。
必要性を説くことはできるけどもね。
次に現実問題として。
運動会の場合は、ボランティアをそのつど呼びかければいい。「それを呼びかけるのは誰なんですか? PTAですよ」とか言う人がいるけど、そうですね、としか言いようがない。ボランティアであるPTAが、運動会の時だけのボランティアを呼びかけたらよいではないか。
ボランティア原則を徹底してしまったPTAが呼びかけたボランティアが、例えば10人しか集まらなかったら? そうしたら、教員+10人のボランティアでできる規模の運動会をやるしかない。その結果、親子三世代がテント持ち込んで観戦するような運動会はできなくなるかもしれない。あるいは全ての保護者が締め出されるかもしれない。しかし、仕方ないんじゃないか。
根本的には学校設置者が予算をつけて人員を確保すべきだが、予算が確保できずにその間をしのぐボランティア労働力が集まらなければ断念せざるを得ない。実際、夏休みのプール開放や休みの校庭開放がそれでダメになったケースはある。
登下校の見守りはどうか。
これもボランティアで10人しか集まらなかったとする。
これまで半強制で、保護者全員が輪番で朝立っていたのに。
どうするのか。
うむ。
10人でやるしかないのでは。
子どもが車にハネられる確率が上がるかもしれない。
しかし、だからと言って、PTAが登下校の安全に責任を持っているわけではない。あくまでPTAがやっているような登下校の見守りというのは、任意のボランティアとして、「自分にできることをやって、少しでも悪いことを減らす」という程度のものでしかないのだ。
逆に言えば、今登下校の見守りで立っているポイントは限られているはずである。通学路すべてに立って見守ることはできない。だとすれば、今保護者が立っていないポイントはそのままにしてもいいのだろうか? もっと一つの家庭が見守り当番に立つ頻度を上げるべきではないのだろうか? さらに言えば、登校時は見守りをしているけども、下校時はしていないという地域もあろう。下校時は見守りをしなくていいのだろうか?
つまり、絶対に果たさねばならない責任の水準がPTAには課せられているわけではないのである。あくまでプラスアルファだというわきまえが必要だ。
ベルマークはどうか。
集めなければ、自分の学校の備品はより多く買えないだけでなく、へき地への支援がその分なくなる……。それはその通りなんだけど、それはベルマークを集めない人が非難されるのではなく、予算をつけない行政が責められるべき問題である。
「予算をつけろと行政を責めるのは非生産的だ」とまで言い出すと、もはや本末転倒。学校教育法第5条で「学校の設置者は…その学校の経費を負担する」とある通り、経費を負担する責任は「設置者」、たいていは市町村である。
それでもどうしてもPTAが強制でやらないとダメな問題があるとしたら、法律で加入を義務づけるしかないではないか。そのための法制定を提起するのが、筋というものだ。




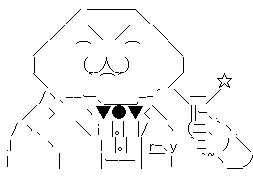
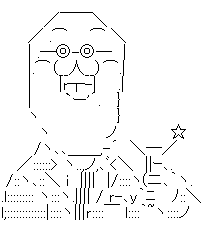
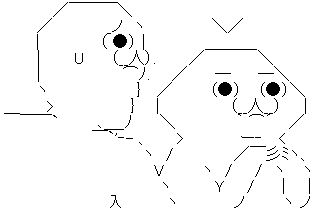






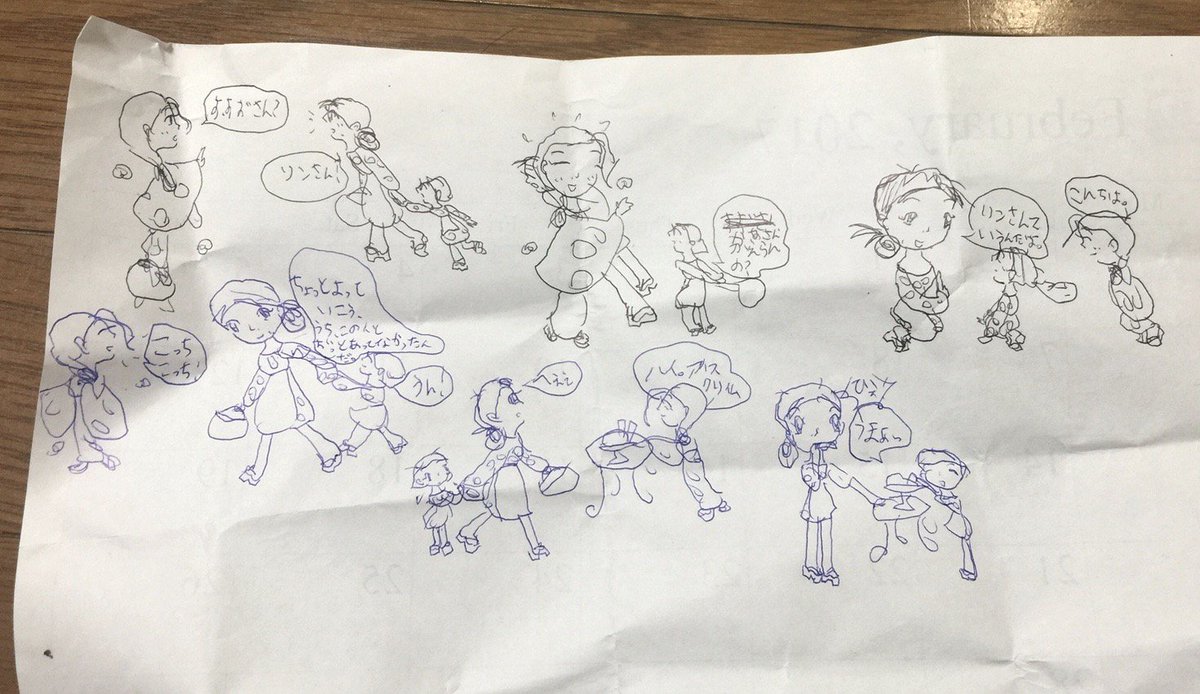

人材活用と簡単にいうが、普通に働ける人間を育てるのは非常に時間もコストもかかるのです。それは知能・性格とも何の問題もない優秀な人間でさえ、仕事でものの役に立つまでは多少の期間辛抱が必要なわけです。
ところが、学校段階でついていけなくなったような人間、しかもやんちゃだとか遊び癖ではなく、(不本意ではあっても)怠け癖のついた人間を普通に働けるようにするのはなかなか大変な大事業です。
昔はそういうのも辛抱強く面倒見てくれる工場や職人の親方が居たりしたものだが、そんな非効率な業種は日本の生産性を下げると言っていまや風前の灯火です。非効率部門ではなくセーフティーネットだったんですがね。
まあどうしても活用したいのならば、効率的という言葉は忘れて、まずは簡単な軽労働をたくさん作ってやるしかないでしょう。
子供にお手伝いをさせる手順ですね。最初は簡単なことからさせてやがては家事全般、中学生になればできるようになります。
社会全体がもう一度辛抱強く教育する体制にならなければ復帰はかなわないでしょう。
効率主義なら殺処分が最善の手段ですが、それでは人間社会の存在意義がなくなる、自分が病気になったらすぐに殺してくれといえる人間だけがそれを言えるということですね。