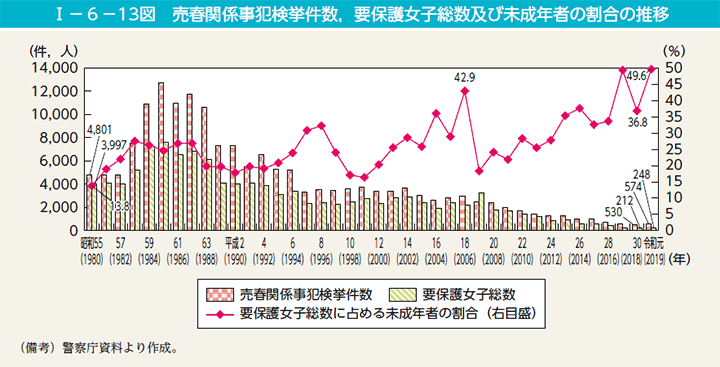[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
酔生夢人のブログ
気の赴くままにつれづれと。
[PR]
×
論理思考と直観思考
小林秀雄の或る文章に引用されていたパスカルの言葉から判断すると、パスカルはデカルトをまったく評価していなかったようだ。私はパスカルの「パンセ」を若いころに読みかけて、ほんの数ページで挫折した人間なので、それが事実かどうかは知らないし、別にパスカルという人間を思想家として評価しているわけでもない、むしろ、「分析と総合」という、思考の大原則を自分に教えてくれたデカルトをはるかに評価している。だが、パスカルは神を「無前提的に信じる」ことを採用した人間である以上、デカルト的な「論理による真偽判定」手法の否定者となったのは当然だろう。ユダヤ・キリスト教的な神の存在は論理的には否定されて当然だからだ。これはドストエフスキーがその著作の中で何度も「2+2は4」という思考を下らない、と書いている理由である。
では、仏教ではどうか。私は仏教の本質は宗教ではなく、「現世をより良く生きるための哲学」だと思っており、来世の有無とか神仏の存在とかは本来のブッダの教えとはまったく無関係だと思っている。つまり、ほとんどの日本仏教はブッダの教えとは無関係なのではないか、と思っているわけだ。葬式仏教など特にそうである。捨身飼虎の説話など、葬式仏教の対極だろう。
で、仏教の本質は何かと言えば、それは「この世界をいかに理解するか」という問題に答えたことで、その答えは「色即是空 空即是色」である。そこには、なぜそう言えるのかという論理は無い。ただ、直観的な答えを提出しただけだ。それを信じるかどうかというところにだけ仏教の宗教性はある、とも言えるだろう。で、色即是空・空即是色を信じることで、無用な迷いや悩みから解放されるというご利益がそこにあるから、その意味では宗教だとも言える。
では、仏教ではどうか。私は仏教の本質は宗教ではなく、「現世をより良く生きるための哲学」だと思っており、来世の有無とか神仏の存在とかは本来のブッダの教えとはまったく無関係だと思っている。つまり、ほとんどの日本仏教はブッダの教えとは無関係なのではないか、と思っているわけだ。葬式仏教など特にそうである。捨身飼虎の説話など、葬式仏教の対極だろう。
で、仏教の本質は何かと言えば、それは「この世界をいかに理解するか」という問題に答えたことで、その答えは「色即是空 空即是色」である。そこには、なぜそう言えるのかという論理は無い。ただ、直観的な答えを提出しただけだ。それを信じるかどうかというところにだけ仏教の宗教性はある、とも言えるだろう。で、色即是空・空即是色を信じることで、無用な迷いや悩みから解放されるというご利益がそこにあるから、その意味では宗教だとも言える。
PR
対立原理と包摂原理
サマセット・モームは「世界の十大小説」の中で、バルザックが「人間喜劇」(バルザックが自分の小説群に与えた総称)の中で描き出そうとした主題(人類の原理)を
「人間は善でもなければ悪でもなく、本能と性癖を生まれながらに持っている。社会はこの人間を、ルソーの主張とは違って、腐敗堕落させるどころか、完全にし、進歩向上させる。だが、その一方、利己心は人間の持つ悪しき傾向を極度にまで発達させる」
という思想だとしている。
バルザック自身がそれに類したことを発言しているかどうかは別として、私もこの思想に賛同する。ただし、ルソーが言うように、文明や文化が人間を腐敗堕落させる面もあると思う。
要点は人間の悪を極度にまで発達させるのが「利己心」だということだ。
では、利己心に対して、東海アマ氏のように「利他心」を「正しい人類原理」だとするのは正しいか。それは大間違いだ、というのが私の考えだ。
東海アマ氏の考え方は「形式論理」であり、おそらく氏が称揚するヘーゲルの「弁証法」がその思考法の土台にあると思う。
なぜ、その考えが間違いかと言うと、「利他心」は「利己心」の完全な対立物であり、そのふたつを「正→反→合」とアウフヘーベン(何と日本語訳していたか失念。「止揚」か?)する作業が行われていないからだ。利己心に対して利他心を提出しただけでは、何も発展しないのである。
そもそも、「利他心」の中には「自分」という存在が捨象されている。つまり、完全な利他心は「自己犠牲」しか無いのであり、どこの世界にも、平気で自己犠牲をする人間は実に希少なのである。そんなものを人類原理にできるはずがない。
では、利己心と利他心をアウフヘーベンするのは何か。それは「人間愛」だというのが私の答えだ。人間愛なら、他人を愛するのも自分を愛するのも含まれることになる。
それほど大袈裟な話ではなく、「(汝自身と同様に)汝の隣人を愛せよ」というだけのことだが、これが実は難しいのである。汝の隣人は(だいたいは利害関係のため)しばしば汝の敵なのだから。
しかし、自分と利害関係の無い隣人まで憎悪するようになれば、それはまさに「人類の敵」であり、それが最近しばしば起きる大量無差別殺人事件の犯行者の心に起こっている現象だろう。つまり、社会から満足を得ていない人間が社会や他の人間全体を憎悪するようになるわけだ。
さらには、自分と何の関係も無い他の国やその国民を憎悪するようになると、これはまさに社会的精神病である。
議論はここまでとしておく。とりあえず、「人間愛」が人間の正しい原理であり、そして人類を幸福にする原理だとだけ言っておく。そしてその理解や実行には必ずしも宗教を必要とせず、自分の理性に問うだけで「これが正解だ」と分かるはずである。ただし、実行が容易だとは言わない。たとえば、誰か異性を愛した時に生じるのは人間愛ではなく激情と情欲と独占欲だろう。それはしばしば極度の利己心なのである。
「人間は善でもなければ悪でもなく、本能と性癖を生まれながらに持っている。社会はこの人間を、ルソーの主張とは違って、腐敗堕落させるどころか、完全にし、進歩向上させる。だが、その一方、利己心は人間の持つ悪しき傾向を極度にまで発達させる」
という思想だとしている。
バルザック自身がそれに類したことを発言しているかどうかは別として、私もこの思想に賛同する。ただし、ルソーが言うように、文明や文化が人間を腐敗堕落させる面もあると思う。
要点は人間の悪を極度にまで発達させるのが「利己心」だということだ。
では、利己心に対して、東海アマ氏のように「利他心」を「正しい人類原理」だとするのは正しいか。それは大間違いだ、というのが私の考えだ。
東海アマ氏の考え方は「形式論理」であり、おそらく氏が称揚するヘーゲルの「弁証法」がその思考法の土台にあると思う。
なぜ、その考えが間違いかと言うと、「利他心」は「利己心」の完全な対立物であり、そのふたつを「正→反→合」とアウフヘーベン(何と日本語訳していたか失念。「止揚」か?)する作業が行われていないからだ。利己心に対して利他心を提出しただけでは、何も発展しないのである。
そもそも、「利他心」の中には「自分」という存在が捨象されている。つまり、完全な利他心は「自己犠牲」しか無いのであり、どこの世界にも、平気で自己犠牲をする人間は実に希少なのである。そんなものを人類原理にできるはずがない。
では、利己心と利他心をアウフヘーベンするのは何か。それは「人間愛」だというのが私の答えだ。人間愛なら、他人を愛するのも自分を愛するのも含まれることになる。
それほど大袈裟な話ではなく、「(汝自身と同様に)汝の隣人を愛せよ」というだけのことだが、これが実は難しいのである。汝の隣人は(だいたいは利害関係のため)しばしば汝の敵なのだから。
しかし、自分と利害関係の無い隣人まで憎悪するようになれば、それはまさに「人類の敵」であり、それが最近しばしば起きる大量無差別殺人事件の犯行者の心に起こっている現象だろう。つまり、社会から満足を得ていない人間が社会や他の人間全体を憎悪するようになるわけだ。
さらには、自分と何の関係も無い他の国やその国民を憎悪するようになると、これはまさに社会的精神病である。
議論はここまでとしておく。とりあえず、「人間愛」が人間の正しい原理であり、そして人類を幸福にする原理だとだけ言っておく。そしてその理解や実行には必ずしも宗教を必要とせず、自分の理性に問うだけで「これが正解だ」と分かるはずである。ただし、実行が容易だとは言わない。たとえば、誰か異性を愛した時に生じるのは人間愛ではなく激情と情欲と独占欲だろう。それはしばしば極度の利己心なのである。
エロチシズム論
別ブログに書いた小論だが、わりと満足できる内容なので、こちらにも載せておく。
(以下自己引用)
(以下自己引用)
エロチシズム論
三島由紀夫の文学論「ジョルジュ・バタイユ『エロチシズム』」の冒頭部分だけ読んだのだが、そこに書いてあるバタイユとやらのエロチシズム論が不可解なので、考察ネタにしてみる。
とりあえず、「エロチシズム」という、言葉だけはよく聞くが定義の曖昧な言葉の私流の定義からしておく。それは「性的欲望を喚起する物象や言語表現によって喚起され高揚した、性欲を含む複合的感情」としておく。つまり、基本は性欲だが、性欲だけではなく、或る種の神秘感や美感がそこには存在する、と言えるのではないか。たとえば、自分の母親や姉妹の全裸を見た時に、相手を犯したいという性欲を感じる人もいるだろうが、普通の性欲とは言えない或る強烈な感情を生じる人もいるだろう。それは、近親相姦というタブーによって、より激烈化しつつ隠れた性欲であり、葛藤であり、苦悩なのではないか。しかも、そこには或る種の美感すらあるかもしれない。
まあ、分かったような、偉そうなことを書いているが、私は男の性欲など射精すれば終わりという思想であり、恋愛と性欲はまったく別だと考えている。そして、エロチシズムというものもよく分かっていない。だが、それを「性欲と同じ」とするのは違う気がする。まあ、美的概念のひとつでもあるだろうが、裸=エロではない。勃起した男を見て女性が美的と思うとは思えない。あんな無様な姿はない。映画やアニメのラブシーンでも男の勃起したペニスは見せないし描かないものである。
ここで、三島由紀夫が紹介しているバタイユの「エロチシズム論」の概要を書いておく。
三島の文章をさらに私が簡略化しておく。
1:生の本質は非連続性にある。
2:個体分裂によって個々の非連続性が始まる。
3:個々の個体において生殖の瞬間にのみ連続性の幻影が垣間見られる。
4:しかし、存在の連続性とは死である。
5:ゆえにエロチシズムと死は固く相結んでいる。
6:エロチシズムとは、われわれの生の、非連続的形態の解体である。
7:それはまた、「われわれ限定された個人の非連続性の秩序を確立する規則的生活、社会生活の形態の解体」である。
8:ここに性愛と犠牲の近似点があり、犠牲が裸にされることがこうした解体の第一歩であり、殺されることがその完成である。
9:なぜなら、犠牲の死によって、人々は存在の連続性の明証を見るからであり、それがすなわち神聖感の根拠である。
10:エロチシズムには三つの形態があり、「肉体のエロチシズム」「心のエロチシズム」「神聖なエロチシズム」である。
さて、理解できただろうか? もちろん、私には理解できないのだが、理解に努めてみよう。
1はそのままだと極論だが、「個人の生の本質は、両親から切り離された存在であるという非連続性にある」とでも言えば納得できるだろうか。そこに人間の生の孤独の出発点もある。
2は、私が上の説明で言ったことと同じだろう。
3も、「生殖」とは祖先から子孫に続く、「血(遺伝子)の連続性」を確立する手段だから、そこには「連続性」が幻想されるわけだ。もちろん、それが「避妊」という壁をはさんでいても、性交という行為自体によって、連続性の幻想は生じるのである。
4が一番難解であり、論理性が無いように思える。そこにどういう論理を持ってきたらいいのだろうか。1で見たように、生の本質は非連続性である、というのは良しとしよう。としたら、形式論理としては、生の反対物である死の本質は連続性である、となるわけだろうか。しかし、死の本質が連続性だ、と聞いて頷く人はほとんどいないと思う。死とはまさに生の断絶であり、究極の非連続性だと誰でも思うだろうからだ。まあ、とりあえず、個人の死ではなく、種としての死を問題とするなら、個体の死は生殖の前提条件であり、個体に死がなければ生殖の必要性も無いわけである。つまり、(個体の)死は種としての連続性の前提条件となる。これを乱暴にかつ断定的に言ったのが「存在の連続性とは死である」という言葉だ、と解釈しておく。
5は、4が同意できたら即座に了解されるだろう。
6も、5と同様に4への同意で了解されるだろう。
7も、同様に4への同意で了解されるかと思うが、わかりやすく言えば、セックスをしている時に会社や仕事のことを考える馬鹿はいない、ということだ。
8は、まあ、どうでもいい話だと思う。犠牲がどうこうという人類学的問題に関心が無い人間には意味を持たないことだ。性愛と犠牲が近似している、というのは「それはあなたの意見ですよね」と言っておく。だからどうなの、という話だ。
9は、4への同意から了解されるだろう。要するに、「存在の連続性とは死である」という、奇抜な逆説への同意があるかないかで、4以降の論への同意・不同意が決まる。
10もどうでもいい話で、だから何なの、である。エロチシズムを御大層なものとするために「神聖なエロチシズム」をくっつけただけで、エロチシズムに心のエロチシズムと肉体のエロチシズムがあるのは馬鹿でも分かる。むしろ、エロチシズムとは肉体ではなく心の問題だ、とするのが私は正解だと思う。
とりあえず、「エロチシズム」という、言葉だけはよく聞くが定義の曖昧な言葉の私流の定義からしておく。それは「性的欲望を喚起する物象や言語表現によって喚起され高揚した、性欲を含む複合的感情」としておく。つまり、基本は性欲だが、性欲だけではなく、或る種の神秘感や美感がそこには存在する、と言えるのではないか。たとえば、自分の母親や姉妹の全裸を見た時に、相手を犯したいという性欲を感じる人もいるだろうが、普通の性欲とは言えない或る強烈な感情を生じる人もいるだろう。それは、近親相姦というタブーによって、より激烈化しつつ隠れた性欲であり、葛藤であり、苦悩なのではないか。しかも、そこには或る種の美感すらあるかもしれない。
まあ、分かったような、偉そうなことを書いているが、私は男の性欲など射精すれば終わりという思想であり、恋愛と性欲はまったく別だと考えている。そして、エロチシズムというものもよく分かっていない。だが、それを「性欲と同じ」とするのは違う気がする。まあ、美的概念のひとつでもあるだろうが、裸=エロではない。勃起した男を見て女性が美的と思うとは思えない。あんな無様な姿はない。映画やアニメのラブシーンでも男の勃起したペニスは見せないし描かないものである。
ここで、三島由紀夫が紹介しているバタイユの「エロチシズム論」の概要を書いておく。
三島の文章をさらに私が簡略化しておく。
1:生の本質は非連続性にある。
2:個体分裂によって個々の非連続性が始まる。
3:個々の個体において生殖の瞬間にのみ連続性の幻影が垣間見られる。
4:しかし、存在の連続性とは死である。
5:ゆえにエロチシズムと死は固く相結んでいる。
6:エロチシズムとは、われわれの生の、非連続的形態の解体である。
7:それはまた、「われわれ限定された個人の非連続性の秩序を確立する規則的生活、社会生活の形態の解体」である。
8:ここに性愛と犠牲の近似点があり、犠牲が裸にされることがこうした解体の第一歩であり、殺されることがその完成である。
9:なぜなら、犠牲の死によって、人々は存在の連続性の明証を見るからであり、それがすなわち神聖感の根拠である。
10:エロチシズムには三つの形態があり、「肉体のエロチシズム」「心のエロチシズム」「神聖なエロチシズム」である。
さて、理解できただろうか? もちろん、私には理解できないのだが、理解に努めてみよう。
1はそのままだと極論だが、「個人の生の本質は、両親から切り離された存在であるという非連続性にある」とでも言えば納得できるだろうか。そこに人間の生の孤独の出発点もある。
2は、私が上の説明で言ったことと同じだろう。
3も、「生殖」とは祖先から子孫に続く、「血(遺伝子)の連続性」を確立する手段だから、そこには「連続性」が幻想されるわけだ。もちろん、それが「避妊」という壁をはさんでいても、性交という行為自体によって、連続性の幻想は生じるのである。
4が一番難解であり、論理性が無いように思える。そこにどういう論理を持ってきたらいいのだろうか。1で見たように、生の本質は非連続性である、というのは良しとしよう。としたら、形式論理としては、生の反対物である死の本質は連続性である、となるわけだろうか。しかし、死の本質が連続性だ、と聞いて頷く人はほとんどいないと思う。死とはまさに生の断絶であり、究極の非連続性だと誰でも思うだろうからだ。まあ、とりあえず、個人の死ではなく、種としての死を問題とするなら、個体の死は生殖の前提条件であり、個体に死がなければ生殖の必要性も無いわけである。つまり、(個体の)死は種としての連続性の前提条件となる。これを乱暴にかつ断定的に言ったのが「存在の連続性とは死である」という言葉だ、と解釈しておく。
5は、4が同意できたら即座に了解されるだろう。
6も、5と同様に4への同意で了解されるだろう。
7も、同様に4への同意で了解されるかと思うが、わかりやすく言えば、セックスをしている時に会社や仕事のことを考える馬鹿はいない、ということだ。
8は、まあ、どうでもいい話だと思う。犠牲がどうこうという人類学的問題に関心が無い人間には意味を持たないことだ。性愛と犠牲が近似している、というのは「それはあなたの意見ですよね」と言っておく。だからどうなの、という話だ。
9は、4への同意から了解されるだろう。要するに、「存在の連続性とは死である」という、奇抜な逆説への同意があるかないかで、4以降の論への同意・不同意が決まる。
10もどうでもいい話で、だから何なの、である。エロチシズムを御大層なものとするために「神聖なエロチシズム」をくっつけただけで、エロチシズムに心のエロチシズムと肉体のエロチシズムがあるのは馬鹿でも分かる。むしろ、エロチシズムとは肉体ではなく心の問題だ、とするのが私は正解だと思う。
「性の解放」論と売春肯定論
男である私にはあまり関心が持てない話題だし、論じる資格も無いのだが、考える手がかりとしてここに保存しておく。
宮台真司が「売春肯定論者」であるということは前に読んだことがあるが、女性の性の解放と売春の肯定の間には深い裂け目があると思う。つまり、売春はその行為自体が危険性を持っているということだが、もちろんそれは不特定多数との性交渉にはすべて付き物でもある。妊娠や性病や暴力団が怖くてセックスができるか、という勇敢な女性も多いだろう。
まあ、ここで詳しく論じるだけの知識が私には無いのは前に書いたとおりである。売春という人類最古の仕事が否定されるべきものかどうか、また現在の日本社会の貧困状態の中で売春しか生きる手段の無い女性のこともあり、議論の余地は大きいだろう。言えることはただひとつ、女性が売春をしなくても済む社会をまず作ることである。買う側の男の話や男の売春や娯楽としてのセックスの話はそれからだ。正直、男の性のことなどどうでもいいww
(以下引用)

宮台真司が「売春肯定論者」であるということは前に読んだことがあるが、女性の性の解放と売春の肯定の間には深い裂け目があると思う。つまり、売春はその行為自体が危険性を持っているということだが、もちろんそれは不特定多数との性交渉にはすべて付き物でもある。妊娠や性病や暴力団が怖くてセックスができるか、という勇敢な女性も多いだろう。
まあ、ここで詳しく論じるだけの知識が私には無いのは前に書いたとおりである。売春という人類最古の仕事が否定されるべきものかどうか、また現在の日本社会の貧困状態の中で売春しか生きる手段の無い女性のこともあり、議論の余地は大きいだろう。言えることはただひとつ、女性が売春をしなくても済む社会をまず作ることである。買う側の男の話や男の売春や娯楽としてのセックスの話はそれからだ。正直、男の性のことなどどうでもいいww
(以下引用)

なぜ仁藤夢乃さんは萌え絵やAVを攻撃せねばならなかったのか
2022年12月21日 18:00
与えられた前提情報で思考することの危うさ
あまり真面目な記事ばかり書いているとつまらないので、別ブログに書いた記事をこちらにも載せておく。まあ、こういうのを面白いと思うのは私だけかもしれないが、書いた以上は無駄にしないでおく。
(以下自己引用)
谷川流の涼宮ハルヒシリーズは、アニメを見たのが1,2年前で、原作小説を古本屋で買って読み始めて1年くらいかと思うが、もちろん全作品は揃っていない。それどころか、同じ作品を何度も買っているのは、その作品タイトルが記憶できないためである。まあ「消失」だけは記憶できるが、それ以外は無理だ。従って、作品内容もほとんど覚えていない。ひどい場合は、同じ作品を半分くらい読んでから「あっ、これは前に読んだやつだ」と気づいたりする。
(以下自己引用)
ミステリーの根本技法 2022/12/17 (Sat)
谷川流の涼宮ハルヒシリーズは、アニメを見たのが1,2年前で、原作小説を古本屋で買って読み始めて1年くらいかと思うが、もちろん全作品は揃っていない。それどころか、同じ作品を何度も買っているのは、その作品タイトルが記憶できないためである。まあ「消失」だけは記憶できるが、それ以外は無理だ。従って、作品内容もほとんど覚えていない。ひどい場合は、同じ作品を半分くらい読んでから「あっ、これは前に読んだやつだ」と気づいたりする。
まあ、同じ作品を何度も楽しめるとも言えるから、ボケも悪いばかりではない。
で、「憤慨」の中に出て来る、キョンの書いた「恋愛小説」には、2度目も騙されてしまったのである。つまり、最初に読んだ時もあまり真面目に読んでいなかったので、これがいかにトリッキーな推理小説であるかが分からなかったわけだ。「恋愛小説」だという前提で読んだので、そうとしか思えず、その「推理小説」性を忘れていたので、二度も騙されたのである。
要するに、我々は「与えられた前提で思考する」ことが完全に習慣化しているために、実に騙されやすい存在になっているということだ。この場合は「恋愛小説」として提出されたら、そういう目でしかその作品を読まなくなるのである。これは人間性への鋭い問題提起だろう。
ちなみに、このキョンの小説のトリックは、日本の推理小説の傑作のひとつとされている(かどうかは知らないが、その年度の代表作だと思う。)「葉桜の季節に君を想うこと」と同じである。あの作品は、作中の事件自体よりも、作中で最後まで隠された「ある事実」によって読者をあっと言わせたのだが、キョンのこの「恋愛小説」がまさにそれと同じであり、ある意味では、これが推理小説の基本かもしれないと思う。つまり、「作者が『肝心の事実』を隠して話を進めれば、ミステリーになる」ということだ。
これを「叙述トリック」と分類してもいいが、推理小説全体がそうだと言ってもいいと思う。
マルキ・ド・サドの「道徳観」
次に引用する文章はマルキ・ド・サドの「末期の対話」の1節で、サド自身の信条だったと思われる。ある意味では、私がいつも言う「社会主義的精神」の根本がここにあると思われるので引用する。で、これはすべての道徳の根本でもあり、道徳を成立させるには神も仏も不要で、理性だけで十分だ、ということ、そして他者に害を為す行為は愚者の行為にすぎない、という思想である。
さて、「われらの同胞に害を及ぼすものはけっしてわれわれを幸福にすることができない」という言葉の前に恥じないでいられる為政者や上級国民がどれだけいるだろうか。
(以下引用)
理性のみがーーそうです、神父さんーー実に理性のみが、われわれに教えてくれるはずです。われらの同胞に害を及ぼすものはけっしてわれらを幸福にすることができない、自然がこの地上においてわれらに許した最大の配与は、われらが同朋の幸福に貢献することであると、人類の全道徳は、次の一語に含まれております、すなわち、「みずから幸福たらんとせば、これを他にも施すべし」そして他より害を受けたくなければ、けっして他にも害を及ぼすな、です。
(澁澤龍彦訳「恋の罪」河出文庫より)
さて、「われらの同胞に害を及ぼすものはけっしてわれわれを幸福にすることができない」という言葉の前に恥じないでいられる為政者や上級国民がどれだけいるだろうか。
(以下引用)
理性のみがーーそうです、神父さんーー実に理性のみが、われわれに教えてくれるはずです。われらの同胞に害を及ぼすものはけっしてわれらを幸福にすることができない、自然がこの地上においてわれらに許した最大の配与は、われらが同朋の幸福に貢献することであると、人類の全道徳は、次の一語に含まれております、すなわち、「みずから幸福たらんとせば、これを他にも施すべし」そして他より害を受けたくなければ、けっして他にも害を及ぼすな、です。
(澁澤龍彦訳「恋の罪」河出文庫より)
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新CM
最新記事
(06/09)
(06/09)
(06/08)
(06/08)
(06/08)
(06/07)
(06/07)
プロフィール
HN:
酔生夢人
性別:
男性
職業:
仙人
趣味:
考えること
自己紹介:
空を眺め、雲が往くのを眺め、風が吹くのを感じれば、
それだけで人生は生きるに値します。
それだけで人生は生きるに値します。
ブログ内検索
アーカイブ
カウンター
アクセス解析