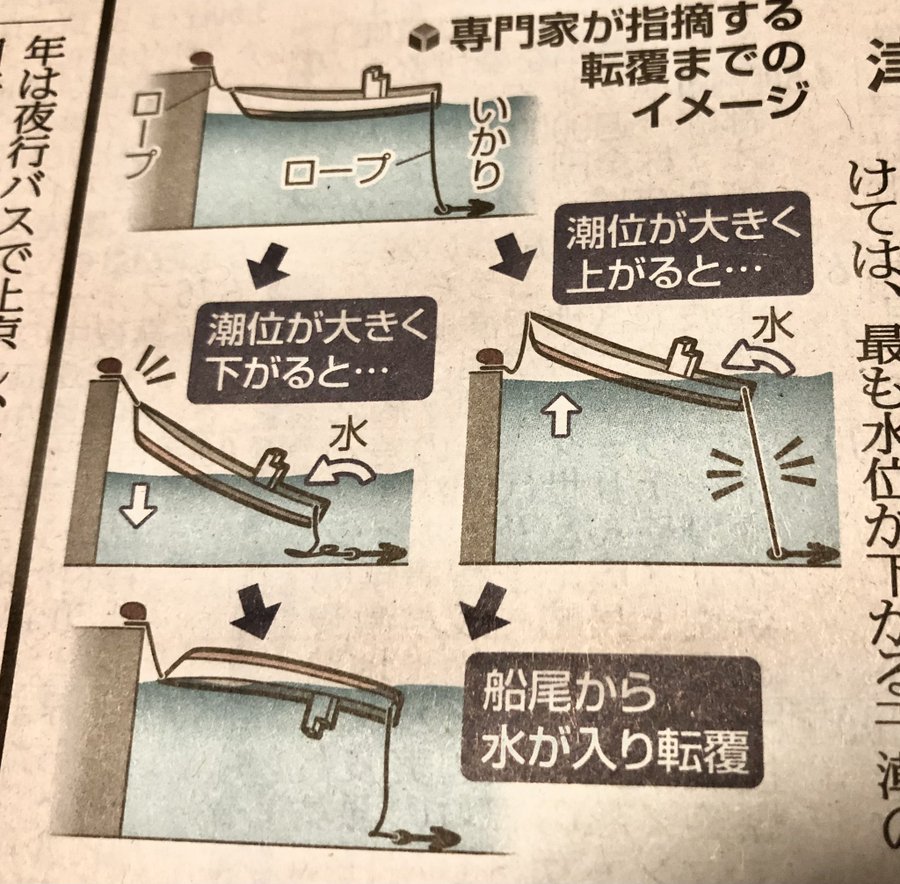問題は、その夢をいつまで見続けるかだ。(シュバイツァー)
なんか、急にね、娘が、
「平穏無事に、生活できていて、家族も仲がいいのは、本当に、ありがたいことだと思うんだけど・・・でも、私の夢がまだ、かなわない。
こんなこと、不満に思うなんて、あの、お金持ちの娘が、水たまりを通るときに、貧乏人には手に入らない「白いパン」を、投げ込んで、そのパンを踏んで、靴を汚さずに渡ろうとしたら・・・
白いパンもろとも、底なしの地獄に落ちた…おとぎ話みたいに、地獄に落ちそうだけど」
と、いってきました。
まだ、40代なのに。
私からみたら、時間もたっぷりあるのに。
「大丈夫よ。いつか、かなうって。今は、そのために必要な準備期間だって。
願い続ければ願いはかなう。」
「ほかの人が、成功しているのを見ると、うらやましくてたまらないの」
「ま、そりゃあそうだろうけど。
私なんかね、いまだに、夢がかなっていない。まだ、やり遂げたいことが、残っている。」
「だから、ママは元気なのか?」
「うん、まだ、やり遂げられないことを思うと、悔しい。悔しいから、頑張る。だから、元気」
話ながら、考えてみたら、私は、多くのことを手掛け、多くのことをともかくやり遂げたけど、「夢」は、近づくたびに遠のいて、いまだ、かなわない。
それどころか、時代の変化が急激で、昭和時代に描いた夢は、すでに、現実味がない。
一人ではできないから、だれか私より若い世代を協力者に育てないと、だめだわ。
最近、以前、伝統文化の教室でお世話していた子が、中学生になって不登校だと知った。
しめた、不登校なら、暇だろうから、この子たちを、呼び込もう!!
いい考えだ!と、思ったけど、
ま、そうは問屋がおろさないわね、
学校にいけないか、行かないには、深い大きな問題があるはずで、健康な普通のくらしの子に「スーパーボールすくいの世話係をやって」というみたいに、簡単なはずない。
そこまで到達するまでに、なにか、深い溝を飛び越えないとだめだよね。
一緒に、飛び越えたいけどね、私は。
前に弟子にしようとした「不登校の男の子」は、めでたく学校に復帰できて、高校生になった今では、クラブ活動をかけもちするモテモテ男子になってしまった。
めでたい話だが、私のそばから飛び立った。
いいよ、今度出会う子たちも、飛んで行ってもいい。でも、家にこもっているのなら、私と一緒に、ちょっと、跳ねてほしい。
人生は、長い、学校だけが生活じゃない。学歴だけが重大じゃない。
夢は、むしろかなわないところに値打ちがあるかも。
追い続けるのが、楽しいのかも。