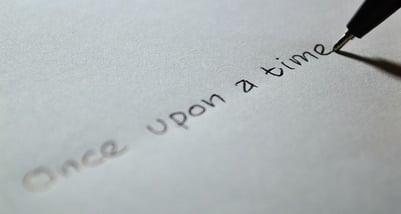
雑誌が定期的に文学作品の最高の冒頭文のリストをまとめるのには理由があります。本の冒頭は読者に大きな印象を与えるからです。本の始まり方は、その本が作り出す世界を理解するのに役立ちます。
まず、語り手と、これから私たちが出会うであろう語りのタイプについての最初のイメージが与えられます。息を切らした一人称の告白でしょうか?それとも、冷静で客観的な三人称の観察でしょうか?
第二に、舞台設定を紹介し、物語がいつどこで起こるのかを知らせます。これは読者の期待を調節するのに非常に重要です。ビクトリア朝時代のイギリスで2人のキスについて私たちが考えることは、現代のカナダで同じカップルについて私たちが考えることとはまったく異なります。
では、 『グレート・ギャツビー』の冒頭では何が語られているのでしょうか? この作品の序文、冒頭の文章、冒頭の段落の意味について読み進めてください。
記事のロードマップ
- 『グレート・ギャツビー』のエピグラフを分析する
- 『グレート・ギャツビー』の最初の一行の意味を探る
- 『グレート・ギャツビー』の最初の段落からニックを語り手として理解する
引用に関する簡単なメモ
このガイドの引用形式は (章.段落) です。Gatsby には多くの版があるため、このシステムを使用しています。そのため、ページ番号の使用は、このガイドで紹介している本を持っている学生にのみ有効です。章と段落で引用されている引用を本で探すには、目視 (段落 1-50: 章の始め、50-100: 章の途中、100 以降: 章の終わり) するか、テキストのオンライン版または eReader 版を使用している場合は検索機能を使用します。
『グレート・ギャツビー』のエピグラフ詩
この小説の序文には次の4行の詩が書かれている。
それで彼女の心を動かすなら、金の帽子をかぶって。
高く跳べるなら、彼女のためにも跳んで。
彼女が「恋人よ、金の帽子をかぶって高く跳べる恋人よ、
私はあなたを手に入れなくちゃ!」と叫ぶまで。
—トーマス・パーク・ダンビリエ
まず、この詩を分析し、それからこのダンヴィリエという人物が誰なのかについて話しましょう。
「金の帽子をかぶって」
最も基本的な意味では、この詩はアドバイスです。最初の単語「それから着なさい」が、会話の途中を聞いているように聞こえるので、私たちはそのことがわかります。ある人が特定の「彼女」との恋愛問題について不満を漏らしており、詩の語り手は、どうすればよいかについてのヒントでそれに答えています。
この詩のアドバイスは、あなたの富や地位(「金の帽子」)とあなたの勇敢な行為(「高く跳ねる」)で彼女に感銘を与えるために全力を尽くすことです。彼女の気を引くためにできることは何でも、最終的に彼女を虜にできればそれだけの価値があります。なぜなら、そのとき彼女は飽きることなく欲しがるからです(「私はあなたを手に入れなければなりません」)。もちろん、この「金の帽子をかぶり、高く跳ねる恋人」のイメージは、よく言っても道化的で、悪く言えばまったく馬鹿げています。
この詩は小説の筋書きと登場人物を反映している。
- ギャツビーがデイジーを口説き落とす方法は、まさに金の帽子をかぶって元気いっぱいの恋人のやり方で、彼女が来てくれるかもしれないという漠然とした希望を抱いて隣に巨大な邸宅を購入したり、毎週パーティーを開いたりと、何でも試そうと必死になっている。
- 自分のイメージを磨く方法として帽子をかぶるという考えは、まさにギャツビーが「オックスフォードの男」というペルソナを採用する際に行ったことであり、彼が俳優やペテン師として描写されることもあることと関係しています。(ニックはギャツビーを「あらゆる毛穴からおがくずが漏れているターバンを巻いた「人物」」(4.31) と呼び、一方、第 3 章では、フクロウのメガネをかけたパーティーのゲストがギャツビーを有名な劇場プロデューサーのデイビッド・ベラスコと比較しています。)
- 同時に、この恋人のイメージをあからさまに嘲笑していることは、ギャツビーの執着心の狂気と、デイジーの心を奪おうとする偏執狂的な探求の不条理さを示唆している。この詩が推奨するアプローチには尊厳がなく、ギャツビーのアプローチにも尊厳はない。この考えは、フィッツジェラルドが当初この小説にもっと風刺的な味わいを持たせたかったことを考えると、さらに強固なものになる(詳細については、グレート・ギャツビーのタイトルに関する記事を参照)。
- この詩は、デイジーの代わりを務める「彼女」というキャラクターを通じて小説ともつながっています。この詩の「彼女」は、感銘を与えて心を掴むべき人物であり、何かを学ぶべき人物ではないことに注意することが重要です。小説のデイジーと同じように、この詩の「彼女」は人物ではなく、賞品や目標です。
トーマス・パーク・ダンヴィリエ
なんと、ダンビリエのような詩人は存在しないのです。フィッツジェラルドがダンビリエを創作し、この詩も創作したのです。
実際、ダンビリエは、プリンストンを題材にしたフィッツジェラルドの初期の小説『楽園のこちら側』では脇役として登場する。その本では、主人公は才能ある詩人であるダンビリエと親しくなるが、彼の詩は現実の問題や不快な側面を無視する傾向がある。
ここで、この詩人の偽名と創作されたペルソナもギャツビーの旅と結びつき、アイデンティティの可変性という小説の主要テーマに関係しています。ジェームズ・ギャツは魅力的なジェイ・ギャツビーに変身し、この詩人はフィッツジェラルドの偽のアイデンティティです。
 それで、ダンビリエはフィッツジェラルドの友人である詩人のジョン・ピール・ビショップをモデルにしているわけですね。実在の人物がフィッツジェラルドの碑文となるような何かを書いたのではないですか?
それで、ダンビリエはフィッツジェラルドの友人である詩人のジョン・ピール・ビショップをモデルにしているわけですね。実在の人物がフィッツジェラルドの碑文となるような何かを書いたのではないですか?



