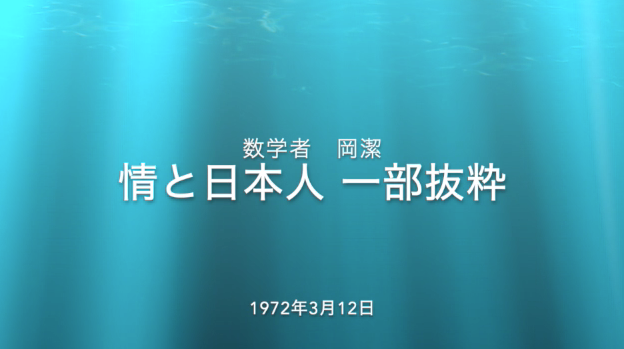1: 名無し 2023/01/14(土) 15:28:01.99 ID:4X7YLc0Wd
今のところ悪くない
2: 名無し 2023/01/14(土) 15:28:37.66 ID:U6oJRqYSM
テスラ?
5: 名無し 2023/01/14(土) 15:29:24.19 ID:4X7YLc0Wd
>>2
リーフや
リーフや
3: 名無し 2023/01/14(土) 15:28:57.64 ID:4X7YLc0Wd
あと気になるのはバッテリーがどんな感じで劣化するかや
4: 名無し 2023/01/14(土) 15:29:04.11 ID:D2rm0coup
1回の充電時間と走行距離教えて
7: 名無し 2023/01/14(土) 15:30:49.33 ID:4X7YLc0Wd
>>4
週2で30分の急速+自宅で100V充電
週2で30分の急速+自宅で100V充電
10: 名無し 2023/01/14(土) 15:31:32.08 ID:1P+JCKiX0
>>7
時間聞いとんやろがボケ
頭ん中までスカスカなんかハゲ
しばきまわすぞ
時間聞いとんやろがボケ
頭ん中までスカスカなんかハゲ
しばきまわすぞ
14: 名無し 2023/01/14(土) 15:33:40.33 ID:4X7YLc0Wd
>>10
30分の急速を週に2回や
自宅のは家にいる間ずっとやから6~8時間ってところ
30分の急速を週に2回や
自宅のは家にいる間ずっとやから6~8時間ってところ
17: 名無し 2023/01/14(土) 15:34:56.95 ID:s7BfF6Nc0
>>14
え?睡眠時間プラスαで8時間ってどんな生活してるん?
え?睡眠時間プラスαで8時間ってどんな生活してるん?
24: 名無し 2023/01/14(土) 15:36:30.30 ID:4X7YLc0Wd
>>17
変か?
21:00帰って5:00出発とかやから
変か?
21:00帰って5:00出発とかやから
9: 名無し 2023/01/14(土) 15:31:30.58 ID:4X7YLc0Wd
>>4
距離書き忘れた
4600kmってところやいまのところ
距離書き忘れた
4600kmってところやいまのところ
11: 名無し 2023/01/14(土) 15:32:33.25 ID:D2rm0coup
>>9
違う
1回の充電での走行距離や
違う
1回の充電での走行距離や
15: 名無し 2023/01/14(土) 15:33:57.28 ID:4X7YLc0Wd
>>11
260km
260km
19: 名無し 2023/01/14(土) 15:35:02.34 ID:4X7YLc0Wd
>>11
あーうそや
1回の充電なら16kWhくらい充電されるから100km弱やな
あーうそや
1回の充電なら16kWhくらい充電されるから100km弱やな
6: 名無し 2023/01/14(土) 15:29:48.31 ID:U6oJRqYSM
アメリカではテスラ値下げでプリウスと同じ価格で買えるようになったで
8: 名無し 2023/01/14(土) 15:30:50.32 ID:PS+3l0UT0
近場の移動限定なら最高だな
都市間移動は最悪
次もEV買うかEV購入者にアンケートしたら
6割以上が買わんと答えてるな
都市間移動は最悪
次もEV買うかEV購入者にアンケートしたら
6割以上が買わんと答えてるな
13: 名無し 2023/01/14(土) 15:33:29.88 ID:s7BfF6Nc0
>>8
混雑時は高速道路の充電コーナーが順番待ちになるらしいな
混雑時は高速道路の充電コーナーが順番待ちになるらしいな
12: 名無し 2023/01/14(土) 15:32:36.92 ID:RcJ9Mv6ZM
街なかにある充電ステーションっていくらなの?
16: 名無し 2023/01/14(土) 15:34:46.55 ID:ckgmpN660
遠出とかせんの?
27: 名無し 2023/01/14(土) 15:38:16.03 ID:4X7YLc0Wd
>>16
しないわ
隣県に移動するくらいや
しないわ
隣県に移動するくらいや
28: 名無し 2023/01/14(土) 15:39:01.52 ID:s7BfF6Nc0
>>27
しないのではなく出来ないのでは?ってのを知りたい
しないのではなく出来ないのでは?ってのを知りたい
32: 名無し 2023/01/14(土) 15:41:44.50 ID:4X7YLc0Wd
>>28
できないしこれで東京⇔大阪移動とかしようとも思わんな
できないしこれで東京⇔大阪移動とかしようとも思わんな
18: 名無し 2023/01/14(土) 15:34:59.92 ID:WBhzl0Nvd
移動中の充電とエアコン使った時の燃費がね
21: 名無し 2023/01/14(土) 15:35:57.44 ID:D2rm0coup
ハイブリッドなら1回の給油で700~800キロ走るだろ?
ガソリン代6000円として
充電だと時間かかるけどそれなりに走るなら考えるんや
今乗ってるプリウスも10万キロ超えたし
ガソリン代6000円として
充電だと時間かかるけどそれなりに走るなら考えるんや
今乗ってるプリウスも10万キロ超えたし
23: 名無し 2023/01/14(土) 15:36:16.35 ID:zbqqeDANM
1年で1万キロ行かんやつの意見なんか意味ないやろ
33: 名無し 2023/01/14(土) 15:44:25.22 ID:4X7YLc0Wd
>>23
言うてそんな走らんくなったから電気自動車でもええかってなった身やし
言うてそんな走らんくなったから電気自動車でもええかってなった身やし
29: 名無し 2023/01/14(土) 15:39:10.06 ID:9pK9U5o/p
本当に持ってるなら写真撮ってや
36: 名無し 2023/01/14(土) 15:46:53.59 ID:4X7YLc0Wd
>>29
これで勘弁したって
これで勘弁したって
34: 名無し 2023/01/14(土) 15:45:22.39 ID:XXzi/kluM
PHVには魅力かんじるんだがな
如何せん高くてなー
燃料コストでペイできそうも無いしな
如何せん高くてなー
燃料コストでペイできそうも無いしな
35: 名無し 2023/01/14(土) 15:46:46.78 ID:Mkln53ue0
>>34
EVモードが便利すぎてそっちばかり使ってるとガソリン腐るからな
アウトランダーとかわざわざ強制消費モードあるし
EVモードが便利すぎてそっちばかり使ってるとガソリン腐るからな
アウトランダーとかわざわざ強制消費モードあるし
37: 名無し 2023/01/14(土) 15:48:37.50 ID:4X7YLc0Wd
>>35
ガソリンって腐るんか
ガソリンって腐るんか
38: 名無し 2023/01/14(土) 15:51:50.85 ID:ftPBNiOO0
家で充電うるさくね?
隣の家にリーフおるけどいつまでもピコピコ糞うるさい
隣の家にリーフおるけどいつまでもピコピコ糞うるさい
42: 名無し 2023/01/14(土) 15:59:55.44 ID:4X7YLc0Wd
>>38
うるさくはないなあ
コントローラーからも音しない
うるさくはないなあ
コントローラーからも音しない
40: 名無し 2023/01/14(土) 15:55:10.27 ID:AzHpHtLsM
リーフやけど登り坂でキロ4.5倍航続距離減ってビビるわ
43: 名無し 2023/01/14(土) 16:00:44.92 ID:4X7YLc0Wd
>>40
ZE0ってやつ?
坂道登るとメーター減るって言われてたな
ZE0ってやつ?
坂道登るとメーター減るって言われてたな
52: 名無し 2023/01/14(土) 16:05:56.80 ID:ckgmpN660
もともと行動範囲狭いやつ向けだよな
41: 名無し 2023/01/14(土) 15:57:41.02 ID:OeUPr2BN0
生活は事足りるよな。旅行行くなら昼から酒飲みたいし
46: 名無し 2023/01/14(土) 16:01:43.42 ID:4X7YLc0Wd
>>41
足りる
ってか前はムラーノ乗ってたけどガス食い虫すぎてマジで車乗らなくなった
足りる
ってか前はムラーノ乗ってたけどガス食い虫すぎてマジで車乗らなくなった
49: 名無し 2023/01/14(土) 16:04:17.46 ID:s7BfF6Nc0
>>46
クルマ乗らんでなんに乗ってたん?
クルマ乗らんでなんに乗ってたん?
53: 名無し 2023/01/14(土) 16:09:22.41 ID:4X7YLc0Wd
>>49
きょくりょく歩きにしてた
きょくりょく歩きにしてた
45: 名無し 2023/01/14(土) 16:01:22.58 ID:1yucg8wO0
中国のEVバイクみたいに出先で電池交換できればいいんだろうけど
充電時間や容量にもっと革命が起きないと無理
充電時間や容量にもっと革命が起きないと無理
49: 名無し 2023/01/14(土) 16:04:17.46 ID:s7BfF6Nc0
>>45
ぐぅわかる
ぐぅわかる
48: 名無し 2023/01/14(土) 16:03:37.93 ID:4X7YLc0Wd
>>45
全個体?とかいうのでも劇的に充電時間は短くならんやろなあ
劣化には強くなるんやろうけど
全個体?とかいうのでも劇的に充電時間は短くならんやろなあ
劣化には強くなるんやろうけど
47: 名無し 2023/01/14(土) 16:03:27.49 ID:TqHJFRwUM
彼女と遠出するときどうすんの?
ワイの三重から白浜まで片道300kmとかあったけど
ワイの三重から白浜まで片道300kmとかあったけど
50: 名無し 2023/01/14(土) 16:05:25.19 ID:4X7YLc0Wd
>>47
現在いないので問題なし
野郎相手なら上手いことサービスエリア休憩でなんとかなった
現在いないので問題なし
野郎相手なら上手いことサービスエリア休憩でなんとかなった