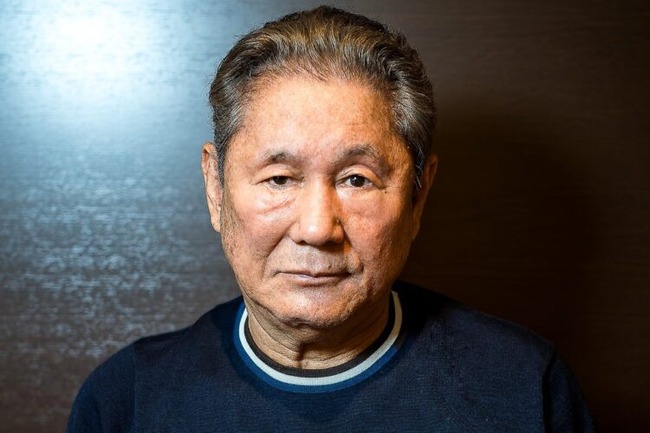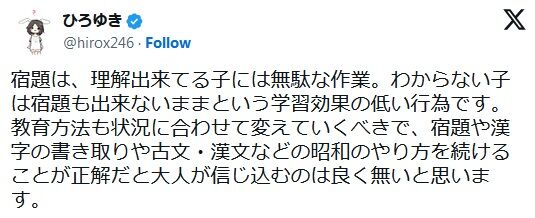「福音の史的展開」というサイトから転載。
パウロ(サウロ)が「ガザで盲(めし)いた」状況である。
で、私は、これはパウロの作り話で、パウロは自らキリスト教の内部に入って、それを変質させようとした「思想スパイ」だったと思っている。
その後のパウロが土台を作ったカソリック教会の「キリスト教」が本来のイエスの教えとはかけ離れた、「人民支配の道具」になっていくのは誰でも知っているだろう。
さて、ガザはカソリックにとって聖地だと思うのだが、今のガザでの「ユダヤによる他民族虐殺」について、ローマ法王やカソリック関係者、あるいはキリスト教関係者は何か発言しているだろうか。
(以下引用)
第二節 パウロの回心とアンティオキア共同体の成立
はじめに
前節で、エルサレムに成立したユダヤ人たちのキリスト信仰の共同体が、使用言語の違いからアラム語系ユダヤ人の共同体とギリシア語系ユダヤ人の共同体に別れたことを見ました。エルサレム共同体はもともと、ガリラヤでイエスの弟子であった「十二人」の使徒たちの福音告知によって成立した共同体であり、「十二人」が代表するアラム語を用いるパレスチナ・ユダヤ人の信仰共同体でした。その共同体にエルサレム在住のギリシア語系ユダヤ人が加わったことによって、エルサレム共同体の福音活動に重大な変化が生じます。ギリシア語系ユダヤ人のグループは、「十二人」の承認の下に「七人」の代表者を立て、周囲のギリシア語系ユダヤ人の間で活発な福音告知の活動を始めます。そのとき、彼らのディアスポラ・ユダヤ人としての体質から、神殿での祭儀や伝統的な律法順守に対して批判的な言動がなされ、それに反発する周囲の律法熱心なギリシア語系ユダヤ人との間に激しい論争が起こり、彼らの代表者であるステファノが石打で殺されるという事件が起こります。今回は、この事件から引き起こされた結果をたどることになります。
Ⅰ パウロの回心
迫害者サウロ
ギリシア語系ユダヤ人の間に起こった激しい論争で、ステファノグループを迫害する側の先頭に立ったのは、同じくギリシア語系ユダヤ人の会堂で指導的な立場にいた年若い新進気鋭のファリサイ派律法学者サウロでした。サウロは、ステファノが会堂の衆議所に引き立てられたとき、彼の石打の処刑に賛成し(八・一)、石打が行われたときには、最初に石を投げる証人の上着を預かるなど立会人を務め、積極的にステファノの石打に参加しています(七・五八)。それだけでなく、彼はその後もイエスをメシアと言い表す信者を探索し、見つけ出せば会堂の衆議所に送り、審問にかけるという活動を続けます。ルカは彼の弾圧活動を、「サウロは家から家へと押し入って《エクレーシア》を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた」と記述しています(八・三)。
この迫害の急先鋒となったサウロこそ、後にイエスの僕となり、イエスをキリストとして世界の諸民族に告げ知らせる偉大な使徒となったパウロに他なりません。どうしてこのようなことが起こったのか、それは何を意味するのかを理解するために、ここで迫害者として現れたサウロとはどういう人物であったのかを見ておきましょう。
サウロは、キリキア州の州都タルソス出身のディアスポラ・ユダヤ人です。サウロの両親は、タルソス在住の敬虔なユダヤ教徒であり、サウロが生まれたとき、八日目に割礼を施し、自分たちが所属するベニヤミン族の英雄サウル王にちなんで「サウロ」と名付けました(フィリピ三・五)。ヘレニズム都市に住むディアスポラ・ユダヤ人の通例として、「サウロ」というユダヤ名の他に、「パウロ」というギリシア語の名前も用いていました。このように二つの名前を持ち、ギリシア文化の中でギリシア語を母語として育ちながら、ユダヤ教の伝統に従って教育を受けるという二重性が、後のパウロを形成することになります。
サウロの父親は、キリキア特産の天幕布織りを職業としていました。父親はサウロをラビ(ユダヤ教の教師、律法学者)にしようと願ったのでしょう、幼いときからその職業を教え込みました。当時ラビは、無報酬で教えることができるために手仕事を習得することが求められていました。後にこの技術がパウロの独立伝道活動を支えることになります(一八・三)。
サウロが生まれ育ったタルソスは、当時のヘレニズム世界で有数の文化都市であり、ギリシア文化の学芸が盛んな都市でした。ギリシア語を母語として育ち、ギリシア語を用いる初等の学校で教育を受けたサウロは、当時のギリシア思想文化を深く身に染みこませていたと考えられます。しかし、厳格なユダヤ教徒の家庭に育ったからでしょうか、ギリシア哲学とか文学・演劇などに深入りした形跡はないようです。
サウロは青年期にエルサレムに行って、そこで律法を学びます。何歳の時にエルサレムに渡ったのかは確認できません。パウロは後に自分がファリサイ派であることを明言していますが(フィリピ三・五)、当時のエルサレムで指導的なファリサイ派のラビはガマリエルでしたから、自分はガマリエルの門下で律法の研鑽に励んだという、ルカが伝えるパウロの証言(二二・三)は十分信頼できます。七〇年以前のユダヤ教で、ファリサイ派ラビの律法教育がエルサレム以外の地で行われることはありませんでした。ガマリエルはヒレルの弟子で、二〇年から五〇年の頃活躍したファリサイ派を代表するラビです。従って、三三年頃に舞台に登場するサウロが、それまでガマリエル門下で学んでいたことは十分ありうることです。
ガマリエルの下で律法(ユダヤ教)の研鑽に励み、その実践に精進した時代のことを、後にパウロは「わたしは先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました」と語っています(ガラテヤ一・一四)。このガマリエル門下での律法の研鑽によって、聖書の言語であるヘブライ語を十分に習得し、また、長年のエルサレム在住によりその日常語であるアラム語も使えるようになっていたことは、十分に推察できます。
しかし、ギリシア語を母語とするギリシア語系ユダヤ人として、ギリシア語系ユダヤ人の会堂に所属し、そこで律法(聖書)の教師として働き、聖都に巡礼したり在住するようになったディアスポラ・ユダヤ人に聖書を教え、また、ユダヤ教にひかれて聖書を学ぼうとする異邦人に律法(ユダヤ教)を講じ、彼らが割礼を受けてユダヤ教に改宗するように導く働きをしたと考えられます。後にパウロはこの活動を「割礼を宣べ伝える」と表現しています(ガラテヤ五・一一)。
このようにギリシア語系ユダヤ人会堂で責任ある立場にいたサウロは、イエスをメシアと言い表すギリシア語系ユダヤ人たちが、モーセ律法や神殿祭儀に批判的な言動をするのを見過ごすことはできませんでした。サウロは、イエスと同時代のエルサレム在住のユダヤ人として、イエスがエルサレムの最高法院で裁判を受け、ローマ総督に引き渡されて十字架刑により処刑された事実はよく知っていたはずです。それを目撃したり、その過程にかかわった可能性も十分あります。その後、数人のガリラヤ人によりイエスをメシアと宣べ伝える運動が始まったとき、それがユダヤ教の枠内で行われている限りは、師のガマリエルと同じく、ことの成り行きに委ねることができました。しかし、一部のギリシア語系ユダヤ人がその信仰のゆえに律法(ユダヤ教)そのものをないがしろにするような言動を示したとき、黙って見過ごすことはできませんでした。先にステファノの殉教のところで見たように、サウロは迫害者として舞台に登場します。
- 迫害者として舞台に登場するまでのサウロと彼の迫害活動について詳しくは、拙著『パウロによるキリストの福音Ⅰ』43頁以下の「ユダヤ教時代のパウロ」と「迫害者パウロ」の両節を参照してください。なお、そこでステファノの殉教を「リンチ事件」としていることは訂正しなければなりません。先に見たように、ステファノの石打は、民衆の激高によるリンチ事件としての様相も見せていますが、やはり(最高法院ではありませんが)会堂の衆議所の審問と判決を経た処刑と見なければなりません。
復活者イエスとの遭遇
さらにルカは、「さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸会堂あての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった」と報告しています(九・一~二)。サウロは、エルサレムだけでなくダマスコの諸会堂にも探索の手を伸ばします。ダマスコにも「この道に従う者」、すなわちイエスをメシアと言い表すユダヤ教徒がいることが報告されてきたからです。この時ダマスコにいたエスを信じる者たちとは、エルサレムでの迫害を逃れてダマスコに行った人たちを指すのか、その時までにダマスコにも信じる者たちの共同体が成立していたのか、確認は困難です。しかし、サウロを迎え入れた後のアナニアを中心とする彼らの活動を見ますと、この時までにかなりの規模の信者の共同体が存在していたと見る方が順当でしょう。
そうすると、ダマスコの共同体《エクレーシア》はどのような経過で成立したのかが問題になります。まだエルサレムのギリシア語系ユダヤ人の福音活動はダマスコには及んでいません。エルサレムの会堂との密接な交流によって、メシア・イエスの信仰が伝えられたのか、地理的に近いガリラヤからの伝道活動で信じる者の共同体が形成されたのか、詳しいことは分かりません。ガリラヤからの影響の可能性が高いと考えられますが、ガリラヤでの信仰運動の実態が分からないので、確定的なことは言えません。
とにかく、ダマスコの諸会堂がこの新しい信仰によって動揺することを恐れたエルサレムのギリシア語系の諸会堂は、迫害の先鋒を担うサウロをダマスコに派遣します。サウロは大祭司のところへ行き、ダマスコの諸会堂あての添書を求めます。他の地域の諸会堂で逮捕連行のような検察官の任務を行うのですから、ユダヤ教の最高機関の承認と任命によることを示す必要があります。おそらく、逮捕連行するための神殿警察隊も同行したと考えられます。ルカは、サウロの迫害行為が大祭司や祭司長たちの承認による行動であることを、繰り返し強調しています(九・一四、二二・五、二六・一〇と一二)。こうして、エルサレムのギリシア語系ユダヤ人の会堂で始まった迫害は、最高法院の権限による広い地域での迫害に拡大します。
「ところが、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然、天からの光が彼の周りを照らし」ます(九・三)。それは真昼ごろであり、その昼の光よりも強い光が天から一行を照らします(二二・六参照)。この光は神の栄光の光であり、真昼の太陽の光をもしのぐ強烈な明るさで一行を(照らすというより)打ちます。
「サウロは地に倒れ、『サウル、サウル、なぜ、わたしを迫害するのか』と呼びかける声を聞」きます(九・四)。その光は自然の光ではなく、人格から発する光であることが、その光がサウロの名を呼んで語りかけることから分かります。この語りかけは、「サウロ」というヘブライ名を使っていることから、ヘブライ語(またはアラム語)でなされたことが分かります(二六・一四参照)。
- 新共同訳はこの呼びかけを「サウル」としています。これはギリシア語で、《サウロス》(日本語表記ではサウロ)という人に呼びかけるときの形(呼格)が《サウル》だからです。呼格がない日本語への訳では、「サウロ」のままでよいのではないかと考えられます。
サウロはこの光に打たれて地に倒れたとき、自分の前に一人の人格が迫っていることを感じます。しかし、それが誰であるか分かりません。サウロに強烈な光として現れた人格は、「なぜ、わたしを迫害するのか」と迫り、サウロがまさに迫害してきた相手であることを告げます。サウロは思わず、「主よ、あなたはどなたですか」と訊ねます。すると答えが来ます、「わたしは、あなたが迫害しているイエスである」。(九・五)
この強烈な光として現れた人格は、復活されたイエスだったのです。復活者イエスが、神の栄光の強烈な輝きをまとってサウロに現れたのです。復活されたイエスが弟子たちに現れるとき、生前のイエスをよく知っている弟子たちでも、それが誰であるか分からないのが普通です。現れた人格が、地上の人間の容相とは違うからです。現れた方が言葉をかけることによってはじめて、それがイエスであることが分かります。この場合も、復活者イエスが顕現されるときの典型的な様相を示しています。
サウロの場合この体験は、探し求めていた方についにめぐり会ったとか、たまたま出会ったというような性質のものではありません。突然敵将に遭遇したのです。今の今まで敵対し攻撃していた敵軍の将が、突如思いもかけないときに、その強烈な力をもってサウロの前に現れたのです。サウロはその力と威厳に圧倒されて、地に倒れ伏します。
「主よ、あなたはどなたですか」と訊ねたサウロに、「わたしは、あなたが迫害しているイエスである」という答えが響きます。サウロは地上のイエスを知りません。直接イエスを迫害したことはありません。サウロが迫害したのは、イエスを信じるユダヤ人です。しかし、実は彼らの中にいますイエスを迫害していたのです。復活者イエスは、イエスを信じる者とご自分を一体として、彼らを迫害することは自分を迫害することだとされるのです。
このようにご自身が誰であるかを示された後、「起きて町に入れ。そうすれば、あなたのなすべきことが知らされる」と、降参して倒れ伏しているサウロに、これからなすべきことを指示されます(九・六)。
「同行していた人たち」とは、ダマスコのイエスの信者を逮捕してエルサレムに連行するために、サウロに同行していた神殿警察の一隊でしょう。彼らも光に照らされ、サウロが発する声は聞こえたのですが、だれの姿も見えないので、あまりの驚きにものも言えず立ちつくしていました。「あなたはどなたですか」という問いに対する答えは、サウロの内面だけに響いた言葉であり、ここで復活者イエスを見たのはサウロだけで、同行者はだれも見ず、イエスの言葉も聞かなかったと考えられます(九・七)。
「サウロは地面から起き上がって、目を開けたが、何も見えなかった」。サウロの目は、あまりにも強烈な光を見たために、見えなくなっていました。それで、「(同行の)人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行」きます(九・八)。