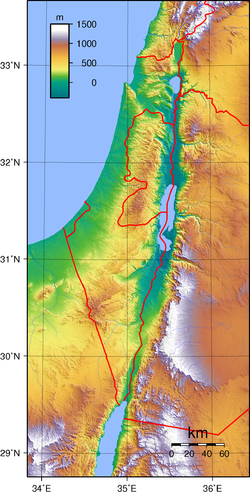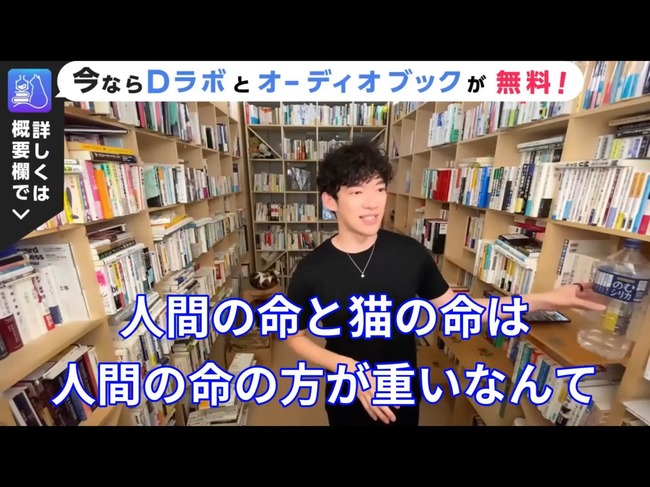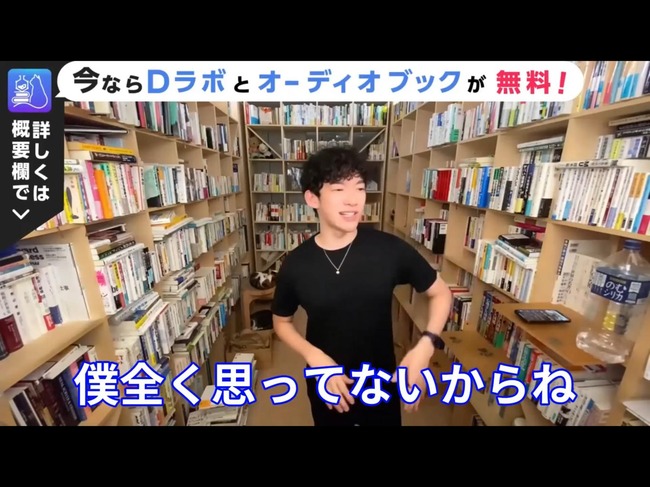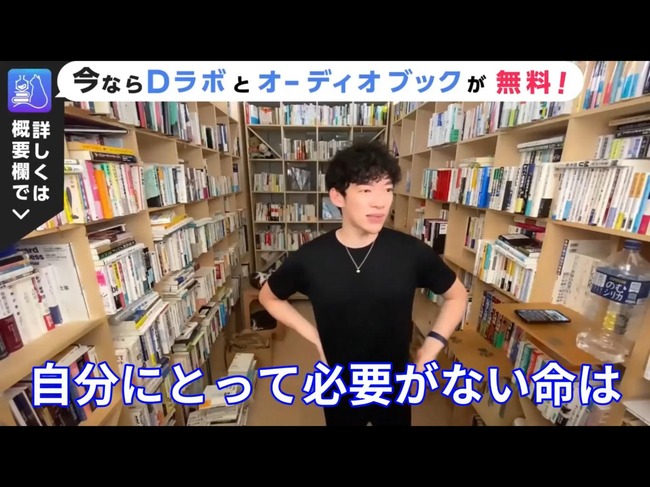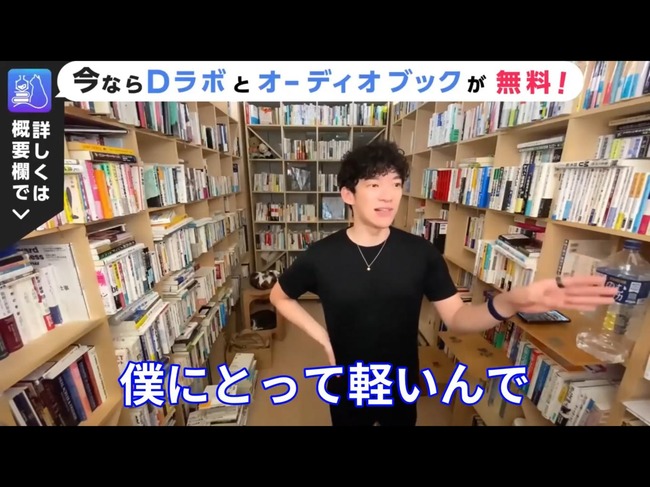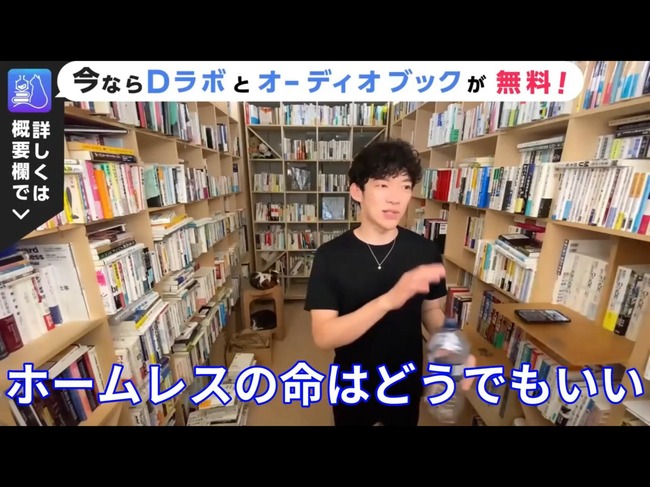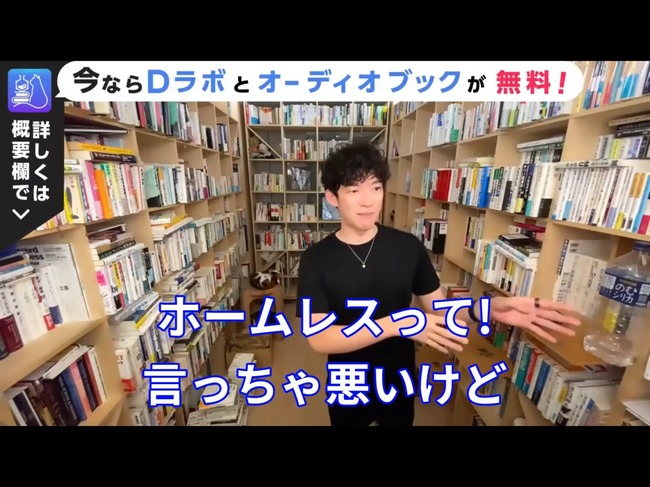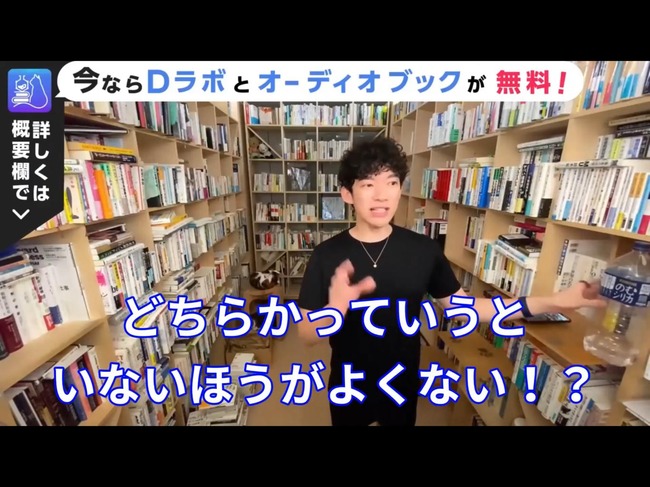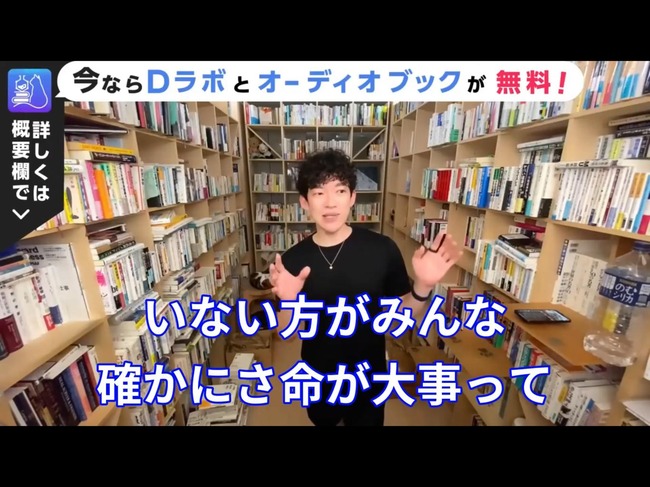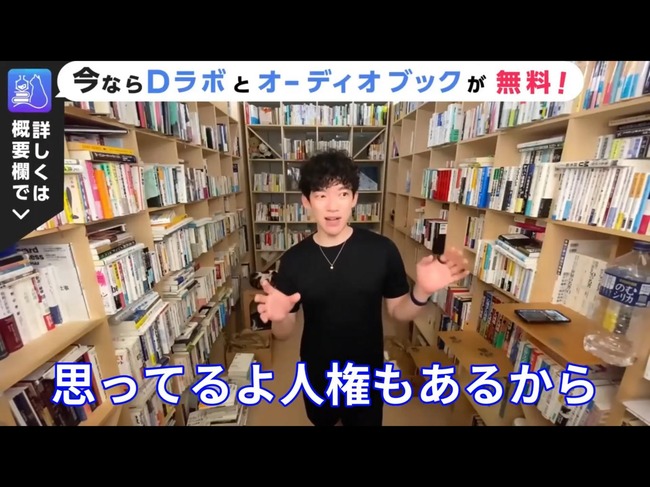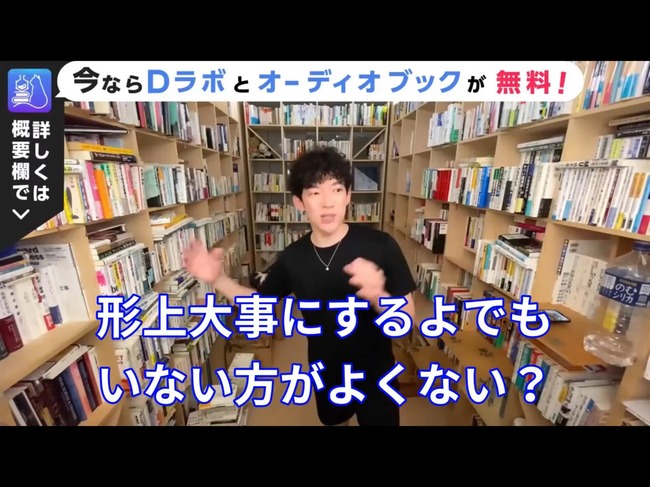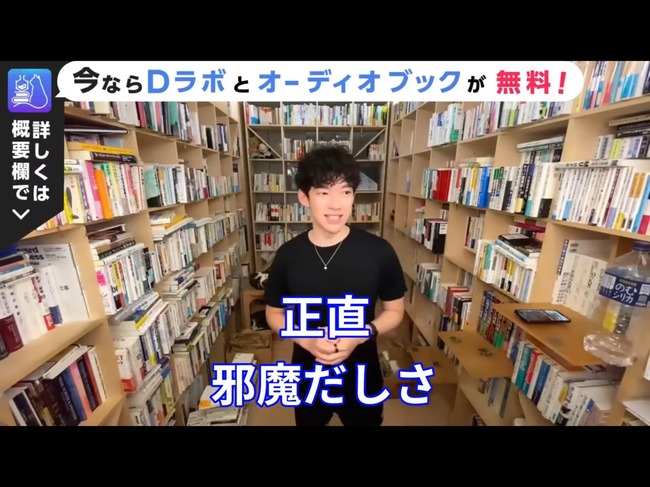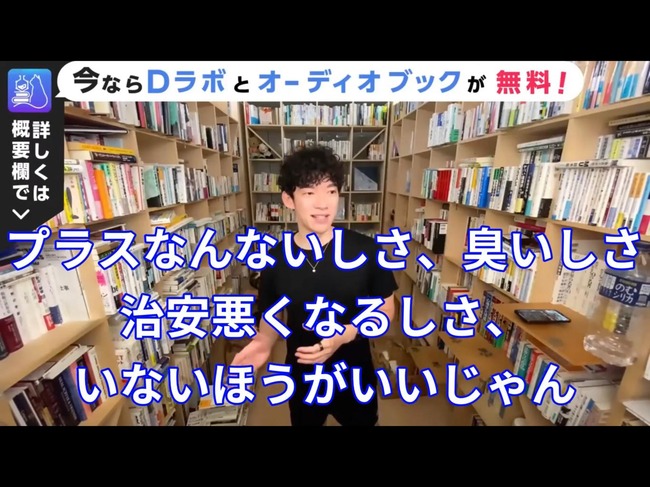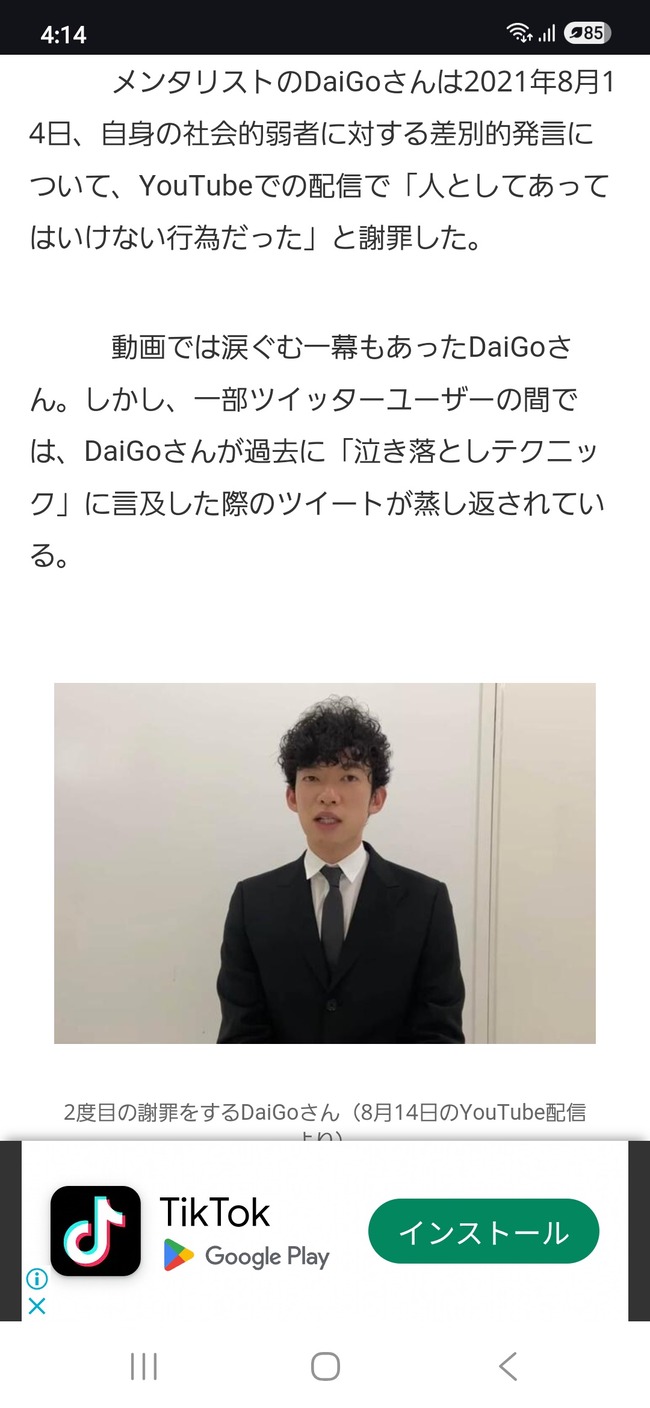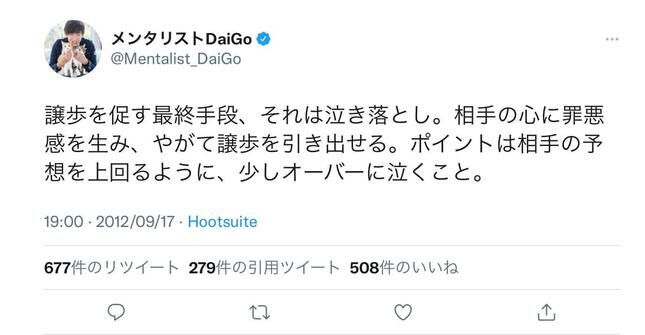1: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:31:16.59 ID:YEw13nVJ0
4: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:33:31.54 ID:plD/awz50
ミャクミャクの眷属だから受け入れろ
羽虫を差別するな
5: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:34:13.22 ID:QKhX4Nl90
>>4
ゴチゾウかよ
6: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:34:36.51 ID:7d5pFGU/0
ユスリカも来場者に含めたら15万人いくやろ
8: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:36:35.31 ID:SHZxKpniM
蚊と違って刺さないから無害だし!とか言って擁護してる場合ちゃうよなこれ
ランプでおびき寄せて電撃で殺す装置つけるとか
開園前に発生源に薬剤撒いて根こそぎ殺すとかなんとかせーや
109: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 07:05:53.69 ID:JsM3iVk+0
>>8
バチバチやるか
9: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:37:39.74 ID:GKDPwT6f0
アース製薬がなんとかしてくれるから大丈夫や
10: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:39:55.31 ID:GKDPwT6f0
てか害虫駆除業者じゃなくて殺虫メーカーに協力依頼するところがほんまお笑いよな
メーカー協賛ってことにして金掛けたくないのがみえみえ
12: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:40:20.49 ID:I5CLgEyq0
彼岸島かな
13: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:42:01.84 ID:T6IiCGlI0
大量駆除で命の輝きを見よう!
14: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:42:14.45 ID:frsnVTtJ0
最初に襲ってきたのは人の方だからな
元々は彼らの土地だぞ
295: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 09:02:06.93 ID:exChTM7z0
>>14
元は海ちゃうんか
15: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:42:18.31 ID:wJEgNKiq0
虫を壊滅させることで技術をアピールする演出や
18: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:43:15.56 ID:0DejE5s80
夏とかどうすんの
20: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:44:45.57 ID:ol0cH0GH0
アンチが生み出した幻想虫だろ
21: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:46:06.80 ID:QKhX4Nl90
キンチョーが記事書いてたで
ユスリカ ~大量発生のひみつ
https://note.com/kincho_jp/n/n9c53051ca48eただし、環境に大きな変化が起こった場所や、人為的に作って間もない環境では、生物の種類が豊富ではないため、
ユスリカに限らず特定の生物の大量発生が起こりがちです。
これは生態系の遷移の過程に起こる自然の現象の一つでもあります。
また、大発生には必ずピークがあり、いつまでも同じ生き物の天下が続くわけではありません。大発生には「終わり」があります。
48: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:03:42.54 ID:tmAzcEDe0
>>21
それを食べる別の生き物が大量発生するってことでは…
76: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:27:41.19 ID:hN9vbR4Gd
>>48
トンボさんは飛行性能鬼やから大体回避してくれるし接触するときも優しく止まるからええやんけ
24: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:48:01.86 ID:I1STKNu+0
死骸が粉末化して周囲に舞うって話だけど飲食店大丈夫なのか
25: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:48:13.66 ID:hqbD+10o0
アフリカ人「うおおお!ごちそうだーー!!」
26: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:48:29.23 ID:CX/Y55Ng0
フィフィが虫くらいで騒ぐな、害はないって言うてた
39: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:55:35.48 ID:ZpXBxtNH0
こんなもん報道しやがって、、、許さんぞ
41: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:57:11.08 ID:kXVOPVym0
夏に入場予定の奴ら絶望で草
ワイはニンテンドーミュージアム行くから
93: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:50:34.84 ID:aBFIqDFX0
>>41
暑い方が減るやろ
46: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 05:59:50.80 ID:CBl4z9d/0
なんだかんだでみんな笑顔で振り払ったり逃げたりして楽しそうだな
47: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:00:43.33 ID:dESiKVUn0
楽しそうでええやん
53: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:11:06.73 ID:BUXCAdb40
貴重な来場者(関係者)やぞ
54: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:11:12.89 ID:NUer9sCv0
歩きながら喋ってたら口の中に入るやろこれ
58: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:12:24.26 ID:BUXCAdb40
動画見たら思ったより湧いてて草も生えない
65: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:16:11.78 ID:5jAiFj4d0
こいつってきっしょい俗称あるんだけど流石に自重されてるな
75: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:26:10.57 ID:paw20hcS0
>>65草

78: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:29:22.26 ID:zQ+mVfvw0
何が笑えないって死骸が粉状になって体内に入ることらしいな
死骸を吸い込んで肺を炎症させる

80: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:32:01.06 ID:hN9vbR4Gd
>>78
普通にアレルゲンで草
91: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 06:49:55.00 ID:AfBDx93L0
>>78
うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
これはやばい!拡散しろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
153: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 07:25:12.84 ID:aeUYCu5h0
ユスリカたこ焼きにユスリカ串焼きなんでもあるで~
寄ってってや~
175: 名無しのアニゲーさん 2025/05/24(土) 07:40:12.90 ID:yS+T8mCd0
Q.こんなユスリカ大量発生してるけど対策は?
A.殺虫剤撒く
小 学生かな?