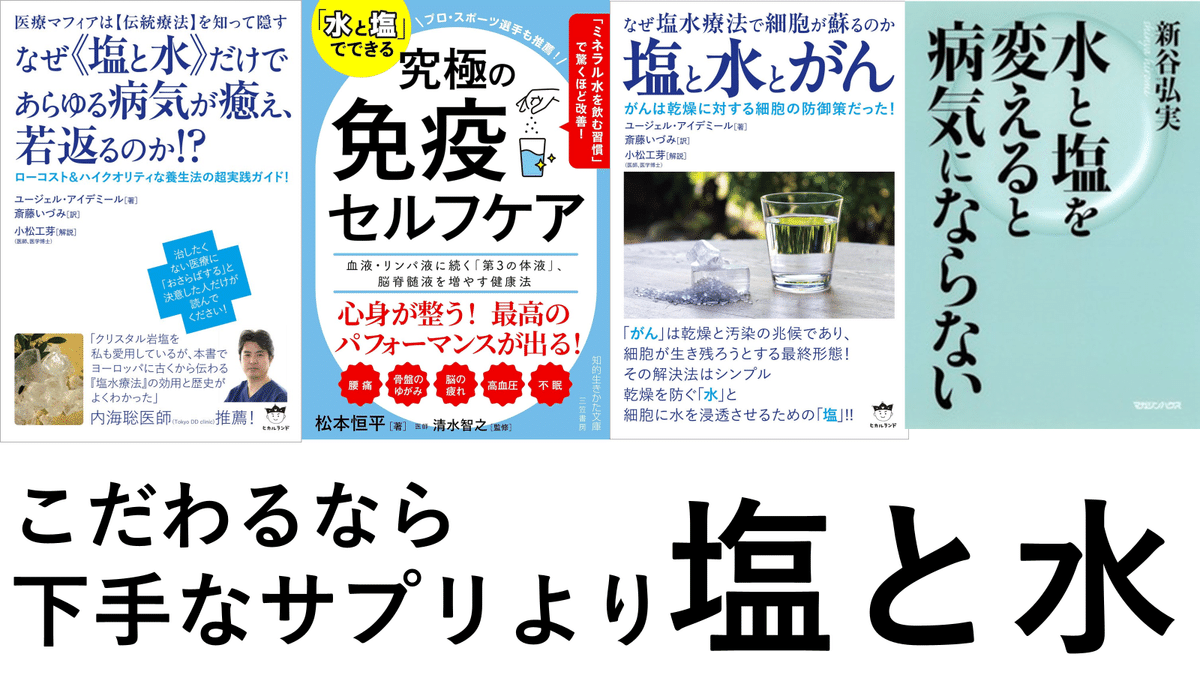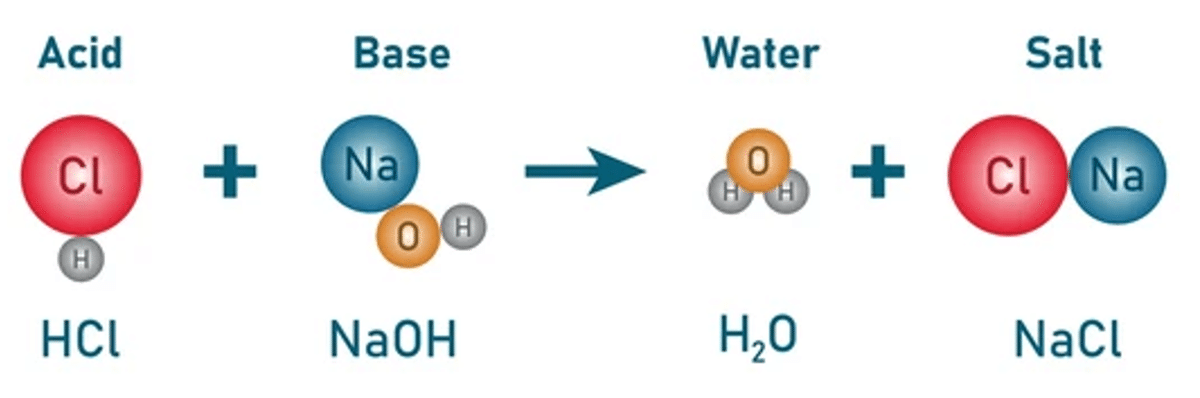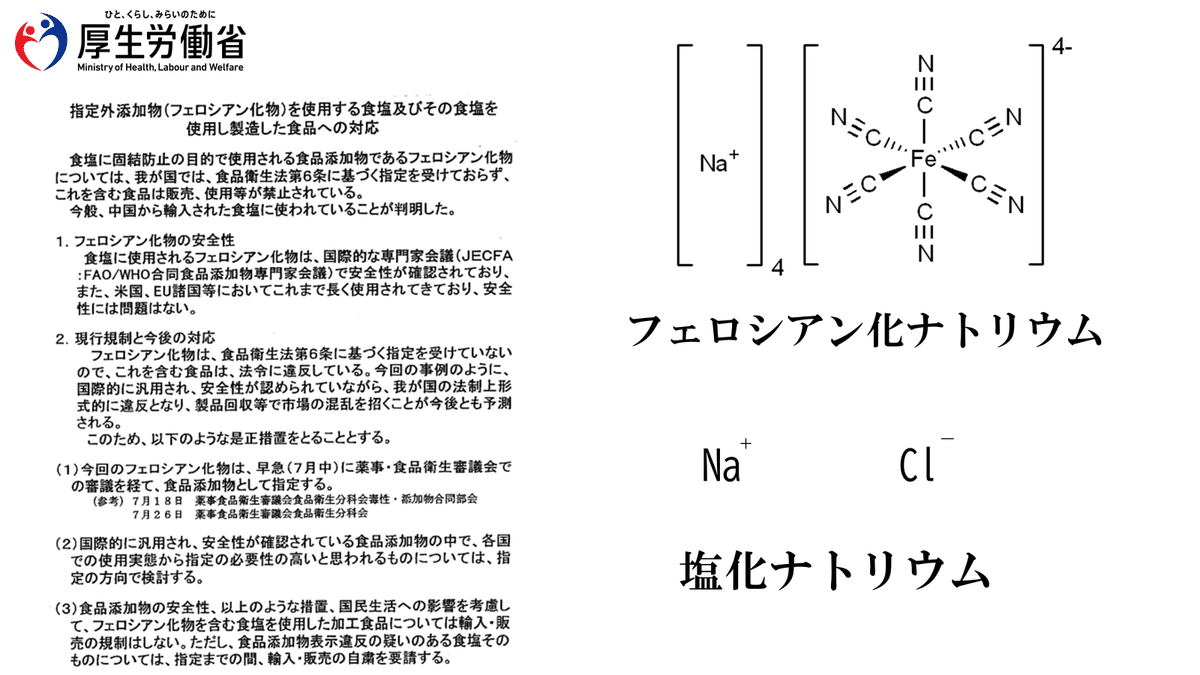https://earthreview.net/exercise-has-nothing-to-do-with-lifespan/
<転載開始>
cure.ae
運動と寿命の関係
運動は健康にいい、という概念は、もうずっと以前から常識的な概念となっています。
もちろん、曖昧な意味では健康にはいいんでしょうが、それと共に、
「運動をすることが長寿につながる」
ということについても、何となく常識的に定着しています。
しかし、最近、フィンランドのユヴァスキュラ大学の研究者たちが、
「運動をよくした人たちと、していなかった人たちの間に寿命の長さに有意な差を見つけることができなかった」
という結論に達した論文が発表されていました。
これは、1958年以前に生まれたフィンランドの双子 2万2750人が含まれているという研究で、実に 30年に渡って追跡調査が続けられたという、運動と長寿の関係についての世界最大の研究のひとつだと思われます。
その結果として、
「差はない」
となったのでした。
ただし、「短期間」での寿命に関しては、運動をしている人たちの死亡率のほうが低かったということも示されています。つまり、若いうちは、運動をしている人たちのほうが亡くなりにくいと。
しかし「長期間」となると、ほとんど同じだったようです。
長期間ということは、つまり「寿命」ということと関係するものですが、これに関しては、運動はほぼ関係しないようです。
まあ…漠然とした概念で恐縮ですが、「長生き」という観念で考えますと、スポーツマンなどの職業の人たちよりも、画家とか作家とか美術家などの「ずっと座っているような人たち」のほうが長生きしているようなイメージ(あくまでイメージですが)はあります。
このフィンランドの研究で面白かったのは、「最も運動をしない人たちと、最も運動をしていた人たちが、共に最も死亡率が高かった」ということです。
全然運動をしない人と、激しく運動をし続けていた人たちが、寿命の最短グループだったようです。
結局、寿命というのは、遺伝の関わりが最大で、そして、それに続くのがストレス(特に持続するストレス)などの外的な要因なのだとは思います。
もちろん、適度な運動が悪いわけはないですので、歩いたり何なり程度の身体活動をすることはいいことなのだとは思います。私は今はほとんどしていないですが。
フィンランドの研究に関しての医学メディアの記事です。
運動は本当に寿命を延ばすのか? 双子研究が新たな知見をもたらす
Does exercise really extend life? Twin study offers new insights
medicalxpress.com 2025/03/13

片方の双子が運動ガイドラインを満たし(右)、もう片方(左)は満たしていない一卵性双生児ペアの記録。
身体活動は人間の寿命を延ばす方法と考えられているが、フィンランドの双子研究によると、身体活動が長寿にもたらす利点はこれまで考えられていたほど単純ではない可能性があることが判明した。
フィンランドのユヴァスキュラ大学の研究者たちは、長期にわたる余暇時間の身体活動と死亡率の関係、また身体活動が遺伝的疾患素因による死亡リスク増加を軽減できるかどうかを調査した。
さらに、身体活動とその後の生物学的老化との関係も調べた。
この研究には、1958年以前に生まれたフィンランドの双子 2万2750人が含まれており、1975年、1981年、1990年に余暇時間の身体活動が評価された。
死亡率の追跡調査は 2020年末まで続けられた。
結果は、医学誌『Medicine & Science in Sports & Exercise』および『European Journal of Epidemiology』に掲載された。
15年間の追跡期間中の余暇時間の身体活動に基づくデータから、
・座位中心 (座っていることが多い)
・中程度に活動的
・活動的
・高度に活動的
という 4つの明確なサブグループが特定された。
30年間の追跡期間でグループ間の死亡率の違いを調べたところ、座位中心と中程度に活動的なグループの間で、死亡リスクが 7% 低下するという最大のメリットが得られたことがわかった。 (※) ほとんど座って生活している人たちと、少し運動している人たちの死亡リスクが同じで、最も死亡率が低かったということです。
身体活動レベルが高くなっても、追加のメリットはなかった。
死亡率を短期と長期に分けて調べたところ、短期的には明らかな関連性が見つかった。身体活動レベルが高いほど、死亡リスクは低くなっていた。
しかし、長期的には、非常に活動的な人と運動不足の人との死亡率に差はなかった。
「運動不足自体が原因ではなく、病気の前段階の状態が身体活動を制限し、最終的には死に至る可能性があります」とスポーツ・健康科学部のエリーナ・シランパー准教授は言う。
「これにより、短期的には身体活動と死亡率の関連性に偏りが生じる可能性があるのです」
WHOの身体活動ガイドラインを満たしても死亡リスクが低くなるとは限らない
研究者たちは、世界保健機関の身体活動ガイドラインに従うことにより死亡率や遺伝病リスクに影響を及ぼすかどうかも調査した。
WHO ガイドラインでは、中程度の運動を毎週 150~ 300分、または激しい運動を毎週 75~ 150分行うことが推奨されている。
この研究では、これらのガイドラインを満たしても死亡リスクが低下したり、遺伝病リスクが変化したりすることはなかった。
15年間にわたって身体活動の推奨レベルを満たした双子でも、活動量の少ない双子ペアと比較して死亡率に統計的に有意な差は見られなかった。
「身体活動と死亡率の間に広く見られる好ましい関係は、さまざまな情報源からの偏りが生じやすい観察研究に基づいています」と、スポーツ・健康科学部の博士研究員であるローラ・ヨエンスー氏は言う。
「私たちの研究では、さまざまな偏りの原因を考慮することを目指しましたが、追跡期間が長かったため、身体活動ガイドラインを順守することで遺伝性の心血管疾患のリスクが軽減されるか、死亡率が低下するかは確認できませんでした」
身体活動と生物学的老化の関係はU字型
双子のサブサンプルについては、エピジェネティック・クロック (DNAのメチル化のレベルによって予測される年齢の時計)を使用して血液サンプルから生物学的老化を判定した。
エピジェネティック・クロックにより、遺伝子発現を制御し、老化プロセスに関連するメチル基に基づいて、人の生物学的老化速度を推定できる。
「余暇時間の身体活動と生物学的老化の関係は U 字型であることがわかりました。つまり、運動量が最も少ない人と最も多い人では生物学的老化が加速していたのです」とシランパー准教授は言う。
喫煙やアルコール摂取などの他のライフスタイルは、身体活動と生物学的老化との好ましい関連性を主に説明した。
この研究では、4,897組の双子の遺伝子データを入手できた。
冠動脈疾患、収縮期血圧、拡張期血圧に対する双子の遺伝的感受性は、ゲノム全体の罹患感受性を合計した新しい多遺伝子リスク・スコアを使用して評価された。
さらに、180組の一卵性双生児の全死因死亡率と心血管疾患死亡率が追跡された。1,153組の双子の生物学的老化率は血液サンプルから評価された。
この研究は、ユヴァスキュラ大学のスポーツ・健康科学部および人間科学方法論センター、ヘルシンキ大学のフィンランド分子医学研究所と協力し実施された。