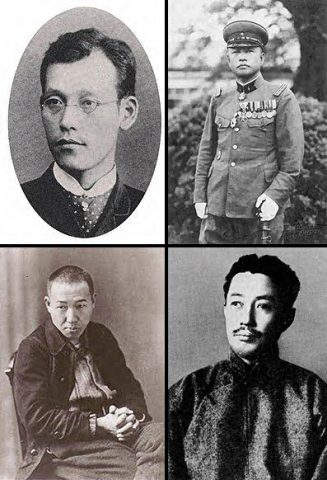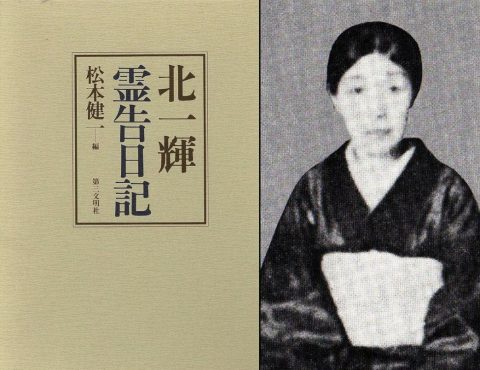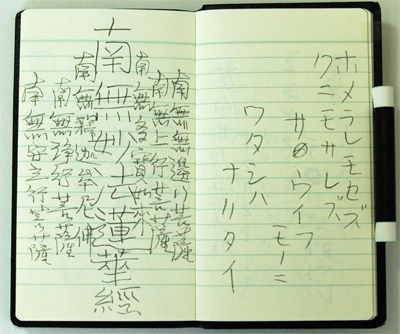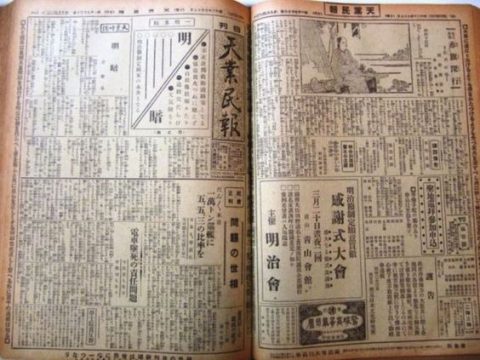酒(アルコール)に関しては、まあ、「人間やめますか、酒やめますか」という選択であり、命を伸ばすために酒をやめる勇気はないし、それで長生きする意味も私にはない。ただ、健康に悪いのは確かだろう。「健康を増進させる美味くて安い酒」を誰か発明してくれないか。
写真拡大
医学や栄養学の進歩で、これまで「体にいい」「体に悪い」と考えられていた食べ物の位置づけが、180度変わってしまうことが頻出している。五良会クリニック白金高輪・五藤良将医師が語る。
「長年続けてきた食習慣を変えることは難しいですし、急に食べ始めたりやめたりするのではなく、できる範囲で取り入れていくことが大切です」
昔、聞きかじった知識が、健康の機会を遠ざけているのかも。ネットの誤情報や、時代遅れの知識に振り回されることなく、美味しく健康な人生を送るための30の「食の常識」を紹介する!
――食材編――
1【ピーナッツ】高カロリーで太る → 糖尿病リスクが低下
「高脂肪、高カロリーですが、じつは糖質が少なく、腹持ちがいい間食に適した食品。インスリンの感受性を改善し、血糖の急上昇を防ぐ効果もあります。糖尿病予備軍や内臓脂肪が多い人に適していますが、一日30粒までが適量です」(五藤医師、以下同)
2【アボカド】高カロリーで太る → ダイエットに効果的
「こちらも高脂肪で高カロリーですが、脂肪の主成分は悪玉コレステロールを下げるオレイン酸。腹持ちがよく食物繊維が豊富なため、便通が改善しておなかもスッキリするはずです。食物繊維+脂肪の組み合わせで、食後血糖値の急上昇を防ぐ効果も」
3【ウナギと梅干】食べ合わせが悪い → 疲労回復の相乗効果
「脂の多いウナギと、胃酸分泌を促す梅干し。胃に負担が大きいとされてきましたが、高価なものを食べすぎることへの戒めの意味があったようですね。ウナギのビタミンB1と梅のクエン酸は、いずれも疲労回復に効果があり、相乗効果があるといえます」
4【ジャンクフード】避けるべき → 食べ方次第
「不健康と思われがちなジャンクフードですが、たとえばフライドポテトの原料であるじゃがいもには、余分な塩分を排出する働きをもつカリウムや、水溶性ビタミンが含まれています。もちろん毎日食べるのではなく、量と頻度をコントロールすることが大切です。完全に避けるよりも、うまく取り入れて栄養価を底上げしよう、と発想を転換してみてはいかがでしょう」
5【マーガリン】トランス脂肪酸が多い → じつはバターよりも少ない
「マーガリンには、心臓病の原因となるトランス脂肪酸が含まれており、避けている人も多いでしょう。しかし、加工技術が進歩した近年では、マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、バターよりも少ないことがわかっています。比較すると、一般的なバター10gに約0.2g含まれるのに対し、マーガリンは0.1gを切るほど。朝食のパンには、安心して塗っていい量です」
6【肉】体に悪い → 長寿の味方
「かつては『肉=脂っこい=体に悪い』、若い人の食べ物だという価値観がありました。ですが、筋肉量が減る高齢者こそ良質のたんぱく質が必要です。最近の研究では、必須アミノ酸や亜鉛、ビタミンB12がバランスよく含まれる赤身肉を適度に摂取することが、健康長寿やフレイル予防に寄与するとされています。もちろん、加工肉や脂身の多い肉の過剰摂取は別問題です」
7【卵】一日1個 → 2、3個でもOK
「かつて、卵はコレステロール値を上げるため『一日1個まで』といわれてきました。しかし今は、食事から摂取するコレステロールは、血中コレステロール値に与える影響が限定的であることがわかってきました。卵は、筋肉や免疫力の維持に非常に優れています。糖尿病や脂質異常がある方は別ですが、健康な中高年なら一日2、3個の卵は、メリットのほうが大きいといえます」
8【オリーブオイル】ドバドバかけてもOK → 高カロリー! 使いすぎに注意
「オリーブオイルはアボカド同様、オレイン酸が豊富で体にいいのは間違いありません。ポリフェノールやビタミンEは、動脈硬化や老化の予防に効果的です。ただ、料理番組でたっぷりと料理にかけるシーンを見たことがある方も多いと思いますが、ドレッシング感覚でかけるべきではありません。大さじ一杯で110kcalもあり、それくらいが限度。それ以上は脂質過多です」
9【白湯】目覚めの一杯 → 歯磨き後に
「目覚めの一杯に、白湯を飲んで体を温める習慣が広がっています。しかし、起床直後の口腔内には、数千億個の細菌が繁殖しているとされます。歯磨き前に白湯や水を飲むことは、そのまま口腔内細菌を胃に流し込んでしまうことになるのです。白湯自体は胃腸を優しく温め、自律神経を整えるメリットがありますが、必ず歯磨き後に飲むことを習慣にしてください」
10【コーヒー】膵臓がんの原因 → 抗がん作用がある
「コーヒーは、1980年代に膵臓がんのリスクを増加させるという研究結果が発表されました。しかしその後の研究で、同様の結果は得られていません。むしろ今は、肝臓がんや子宮体がんなどを予防する可能性があるとされています。また、動脈硬化・糖尿病・認知症の予防や、一日3~4杯飲めば脳卒中や心疾患による死亡率を下げるという研究もあります」
11【オーガニック野菜】健康にいい → 栄養価はほとんど変わらない
「農薬や化学肥料を使わず、自然に近い方法で育てたオーガニック野菜は健康によく、栄養価が高いというイメージを持たれがちです。しかし、通常の野菜と比べて栄養価が高いとは断言できず、ほとんど変わらないという研究があります。また農薬が使われている通常の野菜も、厳格な基準のもとに栽培されていますから、健康被害は科学的に考えられません」
12【青汁】野菜不足を解消 → 腎機能が低い人は×
「野菜不足の解消のために飲んでいる方も多いでしょうが、腎機能が低下していると、豊富なカリウムが不整脈や心停止を引き起こす原因になります。糖尿病・高血圧を長年患っている方は、命取りになりえます」
13【酒】百薬の長 → 少量でもリスクに
「『酒は適量なら健康にいい』といわれていました。しかし近年は、『少量でもがんや高血圧、脳卒中(女性)などの健康リスクが増加する』とする研究結果が増えています。飲ん兵衛には、残念なニュースですね」
14【コラーゲン】食べても意味がない → 意味があるかも
「『食べても肌がピチピチにはならない』ことは知られてきましたね。しかし近年、摂取した一部が『コラーゲンペプチド』となり、骨や関節の材料になるということがわかってきました。研究はこれからですが……」
15【カルシウム不足】イライラの原因 → イライラとは関係ない
「『イライラするのはカルシウム不足のせい』というのは俗説です。たしかに、カルシウムには脳神経の興奮を抑える機能があります。しかし、不足しても骨から溶け出し、血中の量は一定に保たれるのです。牛乳やサプリを飲んだからといってイライラは収まりません。もちろん、骨から溶け出すほど不足させないようにすべきですよ」
16【和食】塩分が多く避けるべき → 健康食として高評価
「和食は塩分が多く、高血圧や腎臓病に繋がるとたびたび警告されてきました。しかし、魚、大豆、野菜、発酵食品を中心とした和食は、本来は長寿を支える食事。和食が悪いわけではなく、調味料の使い方に問題があるのです。かつおや昆布のだしのうま味で減塩した和食は、近年『健康食』として世界的に高評価を受けています」
17【チョコレート】鼻血が出る → 血管を守る
「チョコレートを食べすぎると鼻血が…というのは、僕も子供のころに言われましたね(笑)。少量のカフェインで興奮することがあるかもしれませんが、迷信に近い話です。むしろ、カカオ70%以上のダークチョコレートのポリフェノールの一種が、血管の柔軟性を保ち、老化を防ぐ作用に注目が集まっています。高血圧や心筋梗塞、脳卒中のリスクを減らす効果が期待されます」
18【ひじき】鉄分の王様 → 鉄分は「9分の1」に
「かつて、ひじきは “鉄分の王様” と呼ばれていました。鉄鍋で茹でられていたためで、鍋の成分を吸収していたんですね。しかし、2015年の『日本食品標準成分表』では、ステンレス鍋で茹でた場合が併記されました。鉄鍋だと100gあたり58.2mgあったのが、ステンレスだと6.2mgに激減。なんと9分の1以下になってしまいました」
19【うまみ調味料】多用は避けるべき → 減塩に繋がると積極活用
「グルタミン酸ナトリウムは、『食べ慣れると、味を感じにくくなる』といった風評が長年ありました。しかし、適量で使用するぶんには健康になんの問題もなく、活用すれば、塩分を30%カットしても味の好ましさが変わらないという調査があります。現在では、病院や高齢者施設でも、うま味調味料が積極的に使われています」
20【黒糖や岩塩】白砂糖や精製塩より栄養がある → 栄養はほぼ変わらない
「『白砂糖や精製塩は体に悪い』『黒糖や岩塩は体にいい』と思っている人は多いのではないでしょうか。しかし、砂糖や塩が真っ白なのは不純物が取り除かれているためで、ネット上で散見される『漂白されているから』というのは事実ではありません。一方、黒糖や岩塩に含まれるミネラルはごくわずか。美味しさを感じるかもしれませんが、体にいいとまではいえません」
――食・生活習慣編――
21【朝食】しっかり摂るべき → 抜くと代謝向上にも
「『朝食は一日の活力源』といわれてきましたが、近年は、無理なく食べない時間をつくることによる健康効果も注目されています。特に人気の『16時間断食』は、体内のオートファジー(細胞の自己浄化作用)を促進し、老化抑制や代謝改善に役立つとされています。血糖値の安定や、脂肪の燃焼効率が高まるという研究報告もあります」
22【夜食】眠りが浅くなる → 睡眠の質がアップ
「深夜にラーメンやお菓子を食べると血糖値が急上昇し、睡眠中の成長ホルモン分泌が妨げられます。一方、たんぱく質は筋肉の合成や修復を促し、睡眠中の体のメンテナンスを助けます。茹で卵、ギリシャヨーグルト、ナッツなどは、朝の疲労感軽減にも効果が期待できます。寝る1時間前までに、100~150kcal程度にとどめましょう」
23【一日1食健康法】アスリートやビジネスマンに人気 → 筋肉が分解し代謝も低下
「近年、『一日1食』健康法が注目されています。それで体調を保つには、魚、豆類、卵、緑黄色野菜などを組み合わせ、かつ運動や生活リズムが整っていることが前提です。空腹時間が長すぎると筋肉分解や代謝の低下、低血糖による集中力低下、情緒不安定に繋がります。特に高齢者や基礎疾患のある人は、慎重に判断すべきです」
24【ジュースクレンズ(ジュースだけ生活)】セレブに人気 → 腸内環境が “壊れる” 恐れが
「野菜や果物のジュースだけで数日間過ごすデトックスとして、セレブたちに人気ですね。しかし、果物や野菜を搾ってジュースにすると、食物繊維のほとんどが失われてしまいます。腸内細菌のエサとなる繊維が減り、善玉菌が減少し、悪玉菌が優位になる腸内バランスの崩壊が起こります。果糖による血糖値の上昇や、たんぱく質不足による筋肉の減少も気がかりですね」
25【食後すぐ横になる】牛になる → 胃にいい
「『食べてすぐ横になると牛になる』、つまり行儀が悪く、太るといわれてきました。実際は、体の左側を下にして横になれば、胃の出口(幽門)が下に向き、食べ物を腸へ移動させる動きの助けになります。胃もたれしやすい人は、ゆっくりと横になることで胃内圧を下げ、負担を軽減することができます。逆に右を下にすると、胃酸が食道へ逆流しやすくなるので要注意です」
26【ベジタリアン】病気を防ぎ、健康に → 栄養不足になる可能性が
「野菜や豆類、全粒穀物を中心にすれば、高血圧や、大腸がんなど一部のがんのリスクは低下するでしょう。倫理的な選択としても尊重されるべきです。しかし、たとえばビタミンB12は植物性食品からは摂取が難しく、欠乏すると貧血や神経障害・認知機能低下が起こります。鉄や亜鉛、オメガ3系脂肪酸も不足しがちですので、栄養補助食品や強化食品での補填が不可欠です」
27【グルテンフリー】大ブームに → 日本人には必ずしも必要ではない
「パンやラーメンなど小麦製品に含まれるたんぱく質『グルテン』を避けることで、体調がよくなるケースがあります。しかし、不調を招く原因とされるセリアック病の患者は、人口の1%といわれる欧米と比べて日本では非常に少なく、ほかにもグルテンで下痢やだるさが現われる人もいますが、ほとんどの日本人にとっては、あまり意味のない健康法だといえます」
28【一日30品目】国のガイドライン → 目指す必要はない
「今も『30品目』を目標にしている人がいるかもしれません。1985年に厚生省(当時)が発表した指針に由来しますが、毎日30品目を食べるのは難しいし、カロリーオーバー。すでにその表現は削除されています」
29【体脂肪燃焼】運動開始から20分後 → すぐに燃え始める
「運動時に体脂肪が燃え始めるのは、開始から20分後だといわれます。そんな時間は確保できないと思われるかもしれませんが、じつは最初から脂肪は燃えています。10分間のウオーキングでも、意味はあるのです」
30【紫外線】浴びないほうがいい → 適度に浴びるべき
「ずっと悪者扱いだった紫外線ですが、朝や夕方に15分程度、手や顔に太陽光を浴びるだけで、ビタミンDを合成してくれます。骨粗鬆症や骨折のリスクを大きく下げ、がん予防との関連性も指摘されているんです」
監修・五良会クリニック白金高輪 五藤良将医師
写真・長谷川 新、AC