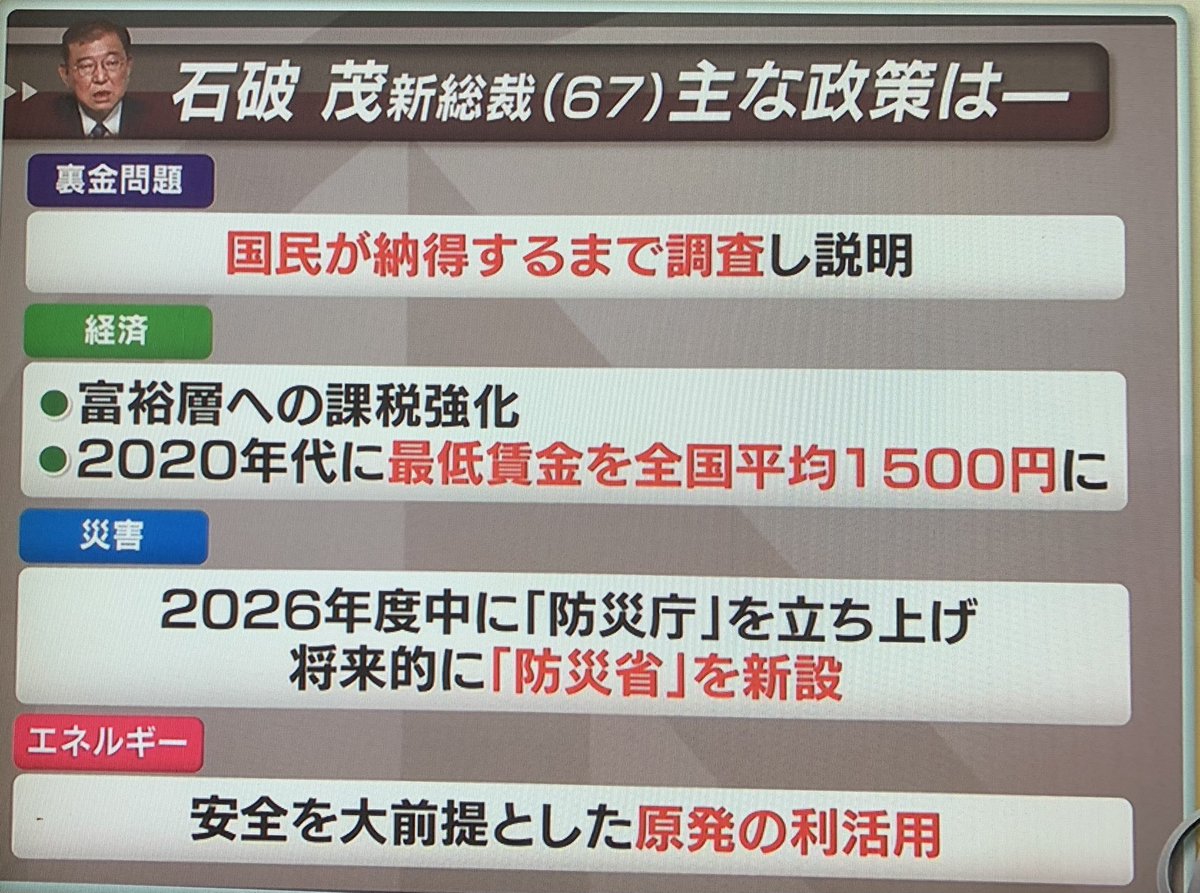とある民間救急ドライバーの日常さんのサイトより
https://ameblo.jp/namachocoponzu/entry-12869491097.html
<転載開始>
さて、今朝はこんなニュースを見かけました。
本当に怖かったんですよ。
私の知り合いの訪問理美容をしていた方は、お得意先だった病院から「ワクチンを打たないと出入り禁止にする」と脅され、嫌々接種し、その後しばらく記憶喪失になりました。
そういう空気を作ったのは、政府の声であり、政府お抱えの専門家であり、行政であり、メディアなのですよ。
2)「私も打ちます。」
これは語弊がありますよね多分。
だって、その言い方では「まだ未接種だけどこれから打つと思います」というニュアンスにも聞こえるからです。
もちろん既に接種済みなのでしょうが、それなら「これからも私は打ちます。」が正しいのではないでしょうか(細かいですが)。
そして打つのはレプリコンでしょうか。それとも通常のmRNAでしょうか。
打ち続けるのは当人の勝手ですが、この期に及んでまだ専門家として打つことを国民に推奨し、ご自身も打ち続ける選択をするのなら、
3)重症化予防効果はかなりあるんですよね
本当に科学的知見に基づく言葉なのでしょうか・・・
最初は打てば感染しないという驚異的有効性を大々的に謳っておりましたが、結局大勢が感染しました。
そしたら、打てば発症しないという、やはり驚異的有効性の声が高まりましたが、結局大勢が発症しました。
最後は打てば重症化しないという論調に落ち着きましたが、結局大勢が重症化しています。
正直、もう引くに引けなくなってきていると言いますか、
発言の責任と現実との間で落としどころを探しているようにしか私には見えません。
https://ameblo.jp/namachocoponzu/entry-12869491097.html
<転載開始>

私ならそれを詐欺と呼ぶ
こんにちは!生チョコぽん酢です。
投稿に時間が空いてすみません、お元気にお過ごしですか?
私の事業所では毎年夏場に少し依頼件数が落ち着き、10月頃から4月頃まで繁忙期が続くのですが、今年は既に馬鹿みたいに忙しいので、来年が思いやられます・・・。
投稿に時間が空いてすみません、お元気にお過ごしですか?
私の事業所では毎年夏場に少し依頼件数が落ち着き、10月頃から4月頃まで繁忙期が続くのですが、今年は既に馬鹿みたいに忙しいので、来年が思いやられます・・・。
さて、今朝はこんなニュースを見かけました。
もう拝見された方も多いと思いますが、インタービューを受けている尾身茂さんは日本でコロナ対策の事実上のトップを務めていた方だと記憶しています。
全部読ませて頂いた感想は、この方なりに色々な葛藤があったのだろうという事や、優れた人間性をお持ちの方という点は伝わってくるのですが、
やはり個人的には色々思うところがあるので、抜粋しながらコメントを入れさせて頂こうと思います。
(以下抜粋太字こちら側)
全部読ませて頂いた感想は、この方なりに色々な葛藤があったのだろうという事や、優れた人間性をお持ちの方という点は伝わってくるのですが、
やはり個人的には色々思うところがあるので、抜粋しながらコメントを入れさせて頂こうと思います。
(以下抜粋太字こちら側)
「政府の検証は不十分だと思います。すべての人が大変な思いをした、100年に一度の危機ですよ。誰かを非難するためではなく、次のパンデミックに備えるため、政治家、官僚、専門家、地方自治体、マスコミといったあらゆる関係者が、公開されているデータ、資料等をもとに検証する必要があります」
この方も次にまたパンデミックが来ることをはっきりと明言しています。
以前私も次に別のパンデミックが起こった際には対処できそうもない現場の空気感と、財政的な問題点を書いたことがありましたが、
まぁこれだけ大勢の専門家が"次また来る"ことを言っているわけですし、来るんですよ多分。
その時はどうなる事やらです。
(以下抜粋太字こちら側)
以前私も次に別のパンデミックが起こった際には対処できそうもない現場の空気感と、財政的な問題点を書いたことがありましたが、
まぁこれだけ大勢の専門家が"次また来る"ことを言っているわけですし、来るんですよ多分。
その時はどうなる事やらです。
(以下抜粋太字こちら側)
2024年4月からワクチン接種は自費になった。今ワクチンを打つべきなのだろうか。
「若い人は副反応もあるということで、打たない人も多いと思います。これはご本人たちの判断です。高齢者や基礎疾患のある人たちは打ったほうがいいと思いますね。私も打ちます。感染防止効果はそれほどでもないけれど、重症化予防効果はかなりあるんですよね。ワクチンは有効ですが、万能ではなかった」
とのことで、やはりワクチンを打つべきだと推していますが、私はこの言葉が妙に引っかかってしまうのでした。
1)若い人は副反応もあるということで、打たない人も多いと思います。これはご本人たちの判断です。
本当にその通りだと思います。
だからこそ当時もそう言って欲しかったのです。
意味分かりますか?
当時はね、どこからも打て打てしか聞こえてこず、打たないやつは非国民のような恐ろしい空気感が立ち込めていました。
1)若い人は副反応もあるということで、打たない人も多いと思います。これはご本人たちの判断です。
本当にその通りだと思います。
だからこそ当時もそう言って欲しかったのです。
意味分かりますか?
当時はね、どこからも打て打てしか聞こえてこず、打たないやつは非国民のような恐ろしい空気感が立ち込めていました。
フランスのマクロン元大統領の発言が当時の空気感の全てを物語っています、被害妄想ではないのです。
[未接種が不安]と検索すると[若年層向け!新型コロナワクチン接種の正しい知識]という打て打て押せ押せの行政のページが出てきて、
ワクチンは感染を予防して収束させる切り札で、
若者を中心に感染が増えていて医療機関が迷惑している
などというメッセージが出てくる時代ですよ。
本当に怖かったんですよ。
分かってますか?
私の知り合いの訪問理美容をしていた方は、お得意先だった病院から「ワクチンを打たないと出入り禁止にする」と脅され、嫌々接種し、その後しばらく記憶喪失になりました。
そういう空気を作ったのは、政府の声であり、政府お抱えの専門家であり、行政であり、メディアなのですよ。
少しはその自覚を持っていただきたいです。
2)「私も打ちます。」
これは語弊がありますよね多分。
だって、その言い方では「まだ未接種だけどこれから打つと思います」というニュアンスにも聞こえるからです。
あれだけ推しているのだから、未接種なんてことはないですよね?
もちろん既に接種済みなのでしょうが、それなら「これからも私は打ちます。」が正しいのではないでしょうか(細かいですが)。
そして打つのはレプリコンでしょうか。それとも通常のmRNAでしょうか。
打ち続けるのは当人の勝手ですが、この期に及んでまだ専門家として打つことを国民に推奨し、ご自身も打ち続ける選択をするのなら、
きちんと有効性について感情論や希望的観測ではなく、化学的知見に基づいて示して頂きたいと思うのです。
そろそろ客観的なデータも出そろってきた頃ではないでしょうか。
3)重症化予防効果はかなりあるんですよね
本当に科学的知見に基づく言葉なのでしょうか・・・
最初は打てば感染しないという驚異的有効性を大々的に謳っておりましたが、結局大勢が感染しました。
そしたら、打てば発症しないという、やはり驚異的有効性の声が高まりましたが、結局大勢が発症しました。
最後は打てば重症化しないという論調に落ち着きましたが、結局大勢が重症化しています。
正直、もう引くに引けなくなってきていると言いますか、
発言の責任と現実との間で落としどころを探しているようにしか私には見えません。
で、最も問題なのが以下の部分。
(以下抜粋、太字とアンダーラインこちら側)
「ワクチンによる被害や死亡は、残念ながら日本では詳細なデータを取れるようなシステムになっていません。死亡した原因がワクチンなのか他のものなのか、ほとんどわからないという状況で、今は結論を出せないということになっている。精査するためのモニタリングシステムを日本は早く構築したほうがいいと思います」
堂々と言い切った;
勘弁してください。
いや、私は知っていましたよ。
でも、このことをあなた方は一切公表しなかったじゃないですか。
誰一人、そんなことを言ってくれる政府側の人間はいませんでしたよ。
覚えていますか?
ワクチンで万が一のことがあれば国が責任を取ってくれるという話を。
「それなら安心ね」と言って打つことを決めた人を大勢知っています。
これは死亡や体調不良の原因がワクチンなのか他のものなのかを判断できるという前提での発言だと、誰もが思っていたわけです。
でも、このことをあなた方は一切公表しなかったじゃないですか。
誰一人、そんなことを言ってくれる政府側の人間はいませんでしたよ。
覚えていますか?
ワクチンで万が一のことがあれば国が責任を取ってくれるという話を。
「それなら安心ね」と言って打つことを決めた人を大勢知っています。
これは死亡や体調不良の原因がワクチンなのか他のものなのかを判断できるという前提での発言だと、誰もが思っていたわけです。
[判断できない=保障できない]となり、誰だって普通はそんなことしないと思うじゃないですか。
万全な体制を整えて勧めてくれているって、誰だって思うじゃないですか。
果たして「正確に判断する仕組みは整ってませんけど」ときちんと補足してくれたら、どれだけの人が打たない選択をしたでしょうか。
そして現実では健康被害が起こり始めており、集団訴訟問題に発展してしまっています。
しかも、こんなものは氷山の一角ですからね?
私が見てきた接種後の体調不良者は誰一人としてワクチン被害の申請などしておりませんから。
患者も医者も「ワクチンのせいだよね」と思っていても、当人が死亡してしまい申請されないケースすらあります。
もちろん私は保障なんかできるわけないだろと思っていましたが、私のような雑魚の発言に耳を貸す人などいません。
皆、専門家の言う事を信じていたのですよ。
要するにこれ、ただの詐欺じゃないですか。
誤解を与える表現で日本人を騙して、莫大な借金や税金を使い込み、更に健康上のリスクを与え、しかも効果がまるで見えてこない、でもまだ続ける。
パチンカスと同じですよ。
どうせ私の声なんて届かないでしょうが、このコロナ禍を民間救急という最前線(かその一歩後ろくらい)の立場で俯瞰して観測し続けてきた私からすると、
やはり今も尚、科学とは程遠い信仰心のようなものが見え隠れして、恐怖せざるを得ないのでした。
皆、専門家の言う事を信じていたのですよ。
要するにこれ、ただの詐欺じゃないですか。
誤解を与える表現で日本人を騙して、莫大な借金や税金を使い込み、更に健康上のリスクを与え、しかも効果がまるで見えてこない、でもまだ続ける。
パチンカスと同じですよ。
どうせ私の声なんて届かないでしょうが、このコロナ禍を民間救急という最前線(かその一歩後ろくらい)の立場で俯瞰して観測し続けてきた私からすると、
やはり今も尚、科学とは程遠い信仰心のようなものが見え隠れして、恐怖せざるを得ないのでした。
あ、最後に次の問いかけについて答えます。
「皆さんが私の立場ならどう思うでしょうか」
何をやっても、どこかから必ず批判されるから、本当に苦労も多かったと思います。
その上で言わせて頂くと、
もし私が同じ立場なら、コロナワクチンの有効性を示すデータと、危険性を示すデータを包み隠さず五分五分で公表し、国民一人ひとりに判断を仰ぎます。
むしろ、他に選択肢がありますか?
偏った情報だけでこんな重大な判断をさせようとしている事自体がもう狂気の沙汰なのです。
そして都合の悪い情報を全て陰謀論として一蹴する姿勢は、医者や科学者として適切ではないと私は思います。
おわり